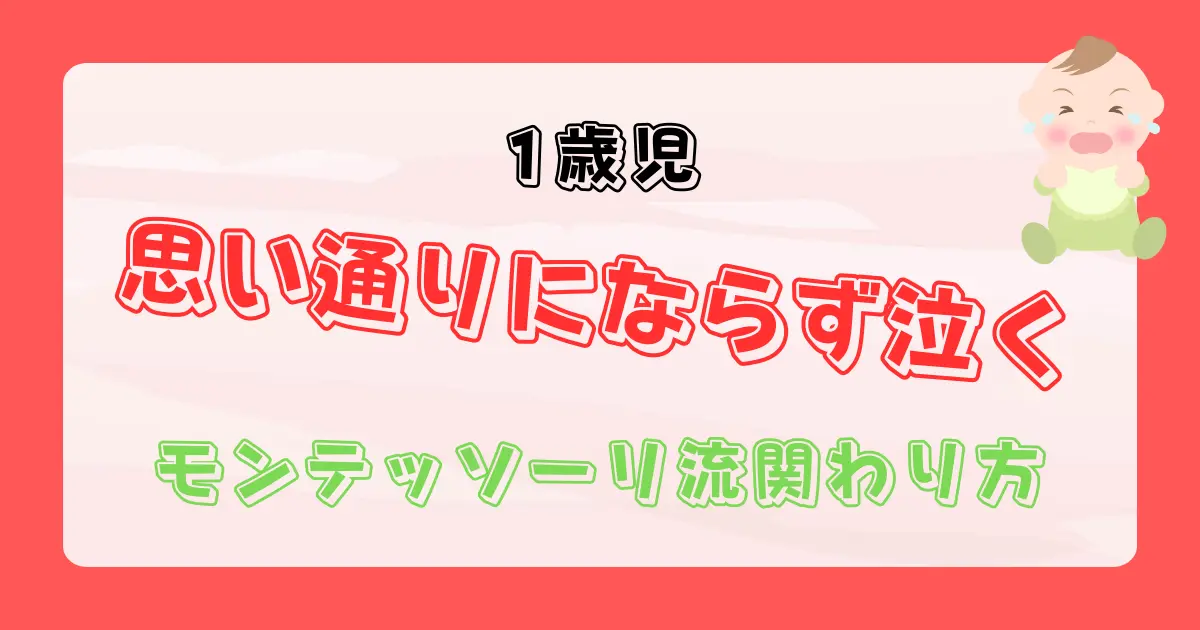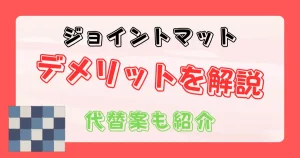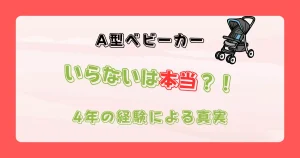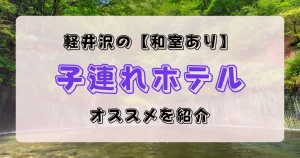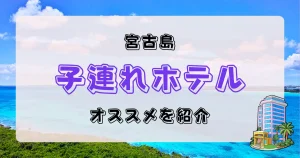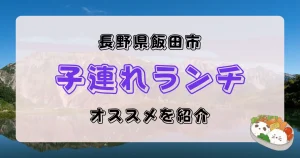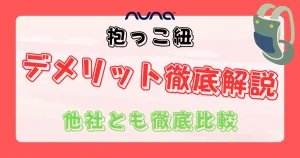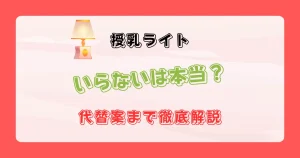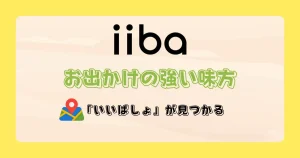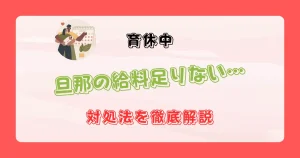- 「1歳の子どもが、思い通りにならないとすぐに火がついたように泣き叫ぶ…」
- 「イヤイヤ期?癇癪?どう対応したらいいかわからない…」
- 「モンテッソーリがいいって聞くけど、具体的にどうすればいいの?」
- 「自分の対応が間違っていて、子どもの成長に悪影響だったらどうしよう…」
1歳のお子さんの「思い通りにならない!」という強い感情表現に、日々向き合っているパパ・ママは多いのではないでしょうか。
床に転がって泣き叫ぶ姿を見ると、どうしたらよいか分からなくなったり、「もう少し頑張ればできるのに!」と、ついイライラしてしまったり…僕も4歳と2歳の息子を育てるパパとして、その気持ち、すごくよく分かります。
でも、安心してください。
その行動は、お子さんが「自分」という存在に気づき、心と体が大きく成長している大切なサインなんです。
そして、モンテッソーリ教育の考え方を知ることで、その癇癪との向き合い方が変わり、親子の関わりがより豊かになるかもしれません。
この記事では、1歳児の癇癪の原因をモンテッソーリ教育の視点も交えて深く掘り下げ、具体的な対応ステップ、そして親自身の心のケアまで、僕自身の経験も少しだけ交えながら詳しく解説します。
この記事を読むことで、以下の点がクリアになりますよ。
- 1歳児が思い通りにならないと泣く理由(発達段階とモンテッソーリ視点)
- モンテッソーリ教育の癇癪に対する基本的な考え方
- 家庭で実践できるモンテッソーリ流の具体的な対応ステップ
- 癇癪を悪化させる可能性のあるNG対応
- 親自身のイライラとの向き合い方と心のケア
- 癇癪予防にもつながる環境づくりのヒント
この記事を最後まで読めば、1歳児の癇癪に対する理解が深まり、自信を持って子どもと向き合えるようになります。
もう一人で悩まず、モンテッソーリの知恵を借りて、この時期ならではの成長を一緒にサポートしていきましょう。
1歳児が思い通りにならないと激しく泣く理由
まず、なぜ1歳のお子さんが、思い通りにならない時にあれほど激しく感情を爆発させるのでしょうか。
それは単なる「わがまま」ではなく、この時期特有の発達段階と深く関わっています。
その理由を知ることで、親として冷静に、そして共感的に子どもと向き合う第一歩になります。
理由1:強烈な「自分でやりたい!」自我の芽生え
1歳頃は、「自分」という存在を意識し始める「自我の芽生え」の時期です。
自分と他者を区別し、「自分はこうしたい!」という強い意志を持つようになる重要な発達段階といえます。
こども家庭庁の資料にも「自分でできることが増えるにつれ、なんでも自分でやりたいという気持ちが芽生えてきます」とある通り、この内側から湧き出るエネルギーが、子どもを突き動かすのです。
この「自分でやりたい」気持ちを理解するポイントは以下の通りです。
- 自己主張の始まり:自分の意志を表現する最初のステップ。
- 探求心の表れ:世界を知り、自分の能力を試したいという意欲。
- 成長の証:依存から自立へと向かう健全な発達プロセス。
しかし、その強い意欲に対して、まだ身体能力や理解力が追いつきません。
この理想と現実のギャップが、癇癪の大きな引き金となります。
子どもにとっては、自分の意志が阻まれることへの強い抵抗の表れなのですね。
引用元:育児のしおり – こども家庭庁
理由2:言葉で伝えられないもどかしさ
大人は自分の気持ちや要求を言葉で表現できますが、1歳児はまだ言葉の発達が十分ではありません。
心の中には複雑な感情が渦巻いていても、それをうまく言葉にして伝えるすべを持たないのです。
その結果、泣く、叫ぶといった行動が、彼らにとって最も直接的なコミュニケーション手段となります。
この時期のコミュニケーションの特徴をまとめます。
- 非言語的表現が中心:泣き、叫び、身振り手振りで意思を伝えようとする。
- 理解先行:大人の言葉はある程度理解できても、自分の気持ちを話すのは難しい。
- 感情の言語化が困難:「悔しい」「悲しい」といった感情を言葉で区別できない。
言葉で表現できないもどかしさが、激しい感情表現につながっているのですね。
僕の息子たちを振り返っても、あの頃の癇癪は、言葉にならない心の叫びだったのかもしれません。
親が子どもの気持ちを代弁してあげることで、子どもは自分の感情を理解し、言葉を覚えていく助けになります。
理由3:「やりたい」と「できる」のギャップ(+他者との関わり)
1歳児の強い「自分でやりたい!」意欲と、それを実現する能力との間には大きなギャップがあります。
この理想と現実のギャップが、フラストレーションを生み出します。
例えば、僕の息子がよく癇癪を起こしたのは、おもちゃのBRIOで線路をうまく繋げられない時や、組み立て途中で壊れた時でした。
「こうしたい!」というイメージ通りにいかないもどかしさが爆発するのです。
具体的なギャップの例を見てみましょう。
| 「やりたい」こと | 「できない」こと(ギャップ) |
|---|---|
| 自分で靴を履きたい | 指先がうまく使えず、かかとが入らない |
| コップで飲みたい | うまく口に運べずこぼしてしまう |
| おもちゃを組み立てたい | パーツがうまくはまらない、途中で壊れる |
| 自分のペースで遊びたい | 兄弟や友達に邪魔される |
さらに、兄弟や他のお友達との関わりも原因になります。
おもちゃを邪魔されたり取られたりすると、自分の「やりたい」が妨げられ、強い抵抗を示すことがあります。これも自我の芽生えゆえの反応といえます。
理由4:感情コントロール能力が未発達
大人は思い通りにいかなくても感情をある程度コントロールできますが、1歳児の脳、特に感情のコントロールに関わる前頭前野はまだ未発達です。
そのため、強い感情が湧き上がっても、それを自分で抑えることが非常に難しいのです。
感情のブレーキがうまく効かない状態、といえば分かりやすいでしょうか。
感情コントロールが未熟なことによる特徴は以下の通りです。
- 感情の切り替えが難しい:一度泣き出すとなかなか泣き止まない。
- 衝動的な行動:欲求不満が即座に行動に現れる(叩く、投げるなど)。
- 共感能力の発達途上:他者の気持ちを理解するのがまだ難しい。
フラストレーションや怒りがダイレクトに行動に結びついてしまいます。
これは意図的に親を困らせているわけではなく、感情の波に飲み込まれている状態なのです。
大人が子どもの感情を受け止め、落ち着く手助けをすることで、子どもは徐々に感情コントロールを学んでいきます。
理由5:モンテッソーリでいう「敏感期」の影響
モンテッソーリ教育には「敏感期」という考え方があります。
これは、子どもがある特定の事柄に強い興味を示し、驚くほどの集中力で取り組む時期のことです。
1歳頃には、特に「秩序の敏感期」が強く表れることがあります。
これは、いつもと同じ場所、同じ順番、同じやり方に強くこだわる時期です。
「秩序の敏感期」に見られるこだわりの例を挙げます。
- 場所へのこだわり:物の定位置が決まっている、自分の席が決まっている。
- 順番へのこだわり:靴を履く順番、服を着る順番、食事の手順など。
- 所有者へのこだわり:これはママの物、これは自分の物という区別。
- 習慣へのこだわり:寝る前の絵本の順番、お風呂の入り方など。
大人から見れば些細な変化でも、子どもにとっては世界の安定が揺らぐような大きな出来事となり、強い不安から癇癪を起こすことがあります。
このようなこだわりが見られたら、「秩序の敏感期かな?」と考え、できるだけその子の秩序感を尊重することが、癇癪の予防や対応につながります。
モンテッソーリ教育の視点で癇癪は「成長のチャンス」? 知っておきたい基本
モンテッソーリ教育は、子どもの癇癪を単なる問題行動ではなく、子どもの内面で起こっていることを理解し、成長するための重要な機会と捉えます。
癇癪を理解し、対応するための基本的な考え方を見ていきましょう。
子どもの主体性と「自己肯定感」を尊重する
モンテッソーリ教育の根幹には、「子どもは自ら成長する力を持っている」という信頼があります。
「自分でやりたい!」という気持ちはその力の表れであり、最大限尊重されるべきと考えます。
癇癪の根底にある意志や欲求を否定せず、まずは気持ちに寄り添い、受け止めることを大切にします。
「〇〇したかったんだね」と気持ちを代弁することで、子どもは理解されたと感じ、安心します。
自己肯定感を育むための関わりのポイントです。
- 子どもの気持ちや意思を否定しない。
- 結果だけでなく、やろうとした努力やプロセスを認める。
- 失敗しても、挑戦したことを称える。
- 「あなたは大切な存在だ」というメッセージを伝え続ける。
この「受け止められる経験」が、子どもの自己肯定感を育む土台となるのです。
大人の役割は「観察」と「環境設定」
モンテッソーリ教育において、大人の役割は「教え込む」ことではなく、子どもを注意深く「観察」し、その子が自ら成長していけるように「環境を整える」ことです。
癇癪が起きた時も、すぐに介入せず、「なぜ癇癪を起こしているのか?」「何につまずいているのか?」を冷静に観察します。
そして、観察から得られた気づきをもとに、環境を調整します。
環境設定で考慮すべき点をまとめます。
| 環境要素 | 具体的な工夫例 |
|---|---|
| 物的環境 | ・子どものサイズに合った家具や道具 ・発達段階に合ったおもちゃ ・自分で出し入れしやすい収納 |
| 時間的環境 | ・予測可能な日課 ・十分な活動時間 ・急かさないゆとり |
| 人的環境 | ・落ち着いた大人の態度 ・子どもの活動を見守る姿勢 ・適切なタイミングでの援助 |
例えば、おもちゃがうまく使えないなら扱いやすいものを用意する、いつも同じことで癇癪を起こすなら原因を取り除くように物の配置を変えるなどです。
このように、大人は子どもの成長をサポートする「援助者」としての役割を担います。
「敏感期」を理解し、子どもの内的欲求に応える
「敏感期」を理解することはモンテッソーリ教育で非常に重要です。
子どもが特定の活動に強い興味を示す時、それはその能力を獲得しようとする内的な欲求の表れです。
大人はそのサインを見逃さず、子どもが欲求を満たせるような活動や環境を用意することが求められます。
敏感期に応えるメリットは以下の通りです。
- 子どもが深い集中と満足感を得られる。
- 必要な能力を効率よく獲得できる。
- 情緒が安定し、癇癪が減る可能性がある。
- 知的好奇心や学習意欲が育まれる。
例えば、「秩序の敏感期」なら物の定位置を決める、指先を使う「運動の敏感期」なら指先を使うおもちゃを用意するなどです。
子どもの内的な発達欲求に応える環境を整えることで、子どもは満たされ、集中して活動でき、結果的に癇癪を起こしにくくなると考えられます。
【実体験】モンテッソーリ実践の難しさ
モンテッソーリ教育の理念は素晴らしいですが、正直なところ、日常生活で常に完璧に実践するのは難しいと感じています。
僕自身、話を聞いて感心しても、いざ癇癪に直面すると冷静に対応できなかったり、つい感情的になったりすることがありました。
特に忙しい時や疲れている時は、子どもの気持ちにじっくり寄り添う余裕を持てないことも…
実践の難しさを感じるポイントを挙げてみます。
- 親自身の感情コントロール:忙しさや疲れから、冷静な対応が難しい時がある。
- 時間的な制約:子どものペースに合わせる時間的余裕がない場面もある。
- 環境整備の限界:理想的な環境を常に用意できるわけではない。
- 兄弟間の調整:複数の子どもの欲求を同時に満たすことの難しさ。
理想を追い求めすぎると、かえって自分が苦しくなるかもしれません。
大切なのは、完璧を目指すことよりも、「子どもの気持ちを理解しよう」という姿勢を持ち続け、できる範囲で少しずつ取り入れていくことなのかもしれませんね。
モンテッソーリ流!思い通りにならないと泣く子への具体的な対応3ステップ(+α現実的対応)
では、実際に子どもが癇癪を起こした時、モンテッソーリの考えに基づいてどう対応すればよいのでしょうか。
具体的な3つのステップと、理想通りにいかない時の現実的な対応例をご紹介します。
これらを意識するだけでも、親の関わり方が変わり、子どもの反応にも変化が見られるかもしれません。
ステップ1:まずは共感!子どもの気持ちを受け止める
癇癪が始まったら、まず子どもの感情を否定せずに受け止めることが最優先です。
「そんなことで泣かないの!」ではなく、「〇〇したかったんだね」「悔しかったね」と、子どもの気持ちを言葉にして代弁します。
可能であれば子どもの目線に合わせ、穏やかな表情で寄り添いましょう。
共感を示す際のポイントです。
- 目線を合わせる:子どもの視界に入り、安心感を与える。
- 感情を言葉にする:「~だったね」と子どもの気持ちを代弁する。
- 穏やかな声と表情:親が落ち着いていることが子どもに伝わる。
- スキンシップ:(子どもが嫌がらなければ)抱きしめる、背中をさする。
重要なのは、「あなたの気持ちを分かっているよ」というメッセージを伝えることです。
これにより、子どもは安心感を得て、少しずつ落ち着きを取り戻せます。
この最初の共感が、その後の対応をスムーズに進める鍵となります。
ステップ2:「ダメ」は明確に、でも人格は否定しない
子どもの気持ちを受け止めつつも、危険な行為や他者を傷つける行為など、許容できないことには、はっきりと「ダメ」と伝える必要があります。
モンテッソーリは「野放し」とは違い、社会のルールや安全を守るための境界線を示すことは大人の大切な役割です。
伝える際は、感情的にならず、冷静かつ一貫した態度で、「なぜダメなのか」を短い言葉で簡潔に説明します。
「ダメ」を伝える際の注意点をまとめます。
- 感情的にならない:冷静なトーンで伝える。
- 簡潔に伝える:長い説明は理解しにくい。
- 一貫性を持つ:その時々で言うことを変えない。
- 人格否定をしない:行動と人格を分けて伝える(例:「悪い子」ではなく「叩くのはダメ」)。
- 理由を添える:(可能であれば)なぜダメなのかを簡単に説明する(例:「痛いからダメ」)。
ポイントは、子どもの「行動」を注意するのであって、子どもの「人格」そのものを否定しないことです。
ステップ3:落ち着いたら、選択肢を与えたり、代案を示したりする
子どもが少し落ち着いたら、癇癪の原因となった欲求に対して、代替案や選択肢を示すことで、気持ちの切り替えをサポートします。
「今は〇〇できないけど、代わりに△△ならできるよ」「どっちの遊びにする?」といった声かけが有効です。
選択肢や代案を示す例を挙げます。
- 状況:おやつの時間にもっとお菓子を欲しがる。
対応例:「お菓子は終わりだけど、りんごかバナナ、どっちか食べる?」 - 状況:公園から帰りたがらない。
対応例:「もう帰る時間だけど、滑り台をあと1回滑るか、ブランコをあと3回漕ぐか、どっちにする?」 - 状況:特定のおもちゃを貸してあげられない。
対応例:「これは今使っているから貸せないけど、こっちのおもちゃならどうぞ」
ここで重要なのは、子ども自身に「選ばせる」機会を与えることです。
たとえ小さな選択でも、自分で決める経験は、子どもの自尊心や主体性を育み、「自分で状況を変えられた」という感覚にも繋がります。
このステップを通して、子どもは自分の欲求と折り合いをつける練習をしていきます。
(+α)どうしても落ち着かない時の現実的な対応例
3ステップを試しても癇癪が収まらず、親も限界…という場面もあるかもしれません。
そんな時の緊急避難的な対応として、一時的に子どもの好きな動画やタブレットの知育ゲーム(我が家も利用する「こどもちゃれんじ」アプリなど)で気をそらし、クールダウンさせる方法も、現実的な選択肢のひとつです。
僕自身も頼ることがありました。
このような対応を取る際の注意点は以下の通りです。
- あくまで一時的な対応:常用せず、最終手段と位置づける。
- 時間やルールを決める:事前に視聴時間などを決めておく。
- 罪悪感を持ちすぎない:親が冷静さを保つための手段と割り切ることも時には必要。
- 落ち着いたら改めて向き合う:なぜ癇癪を起こしたのかを後で話す機会を持つ。
もちろん、これが常態化するのは避けたいところです。
しかし、親が感情的に爆発する前の「最終手段」として頭の片隅に置くのはアリかもしれません。
環境を整えるというモンテッソーリの考え方を長期的に取り入れるなら、子どもの発達や興味に合った知育玩具を継続的に提供する「おもちゃのサブスク」などを検討するのも一案です。
質の高いおもちゃに触れる機会が、子どものフラストレーションを減らす助けになるかもしれません。
これは避けたい!モンテッソーリ流癇癪を悪化させる可能性のあるNG対応
子どもの癇癪に直面すると、ついやってしまいがちな対応があります。
しかし、良かれと思った行動が、かえって状況を悪化させたり、子どもの心に傷を残したりすることも。
ここでは、モンテッソーリ教育の観点からも避けたい、代表的なNG対応を5つご紹介します。
NG1:感情的に怒鳴る、叱りつける
子どもの激しい泣き声に、親も感情的になってしまうことはあります。
しかし、大声で怒鳴ったり、強い口調で叱りつけたりするのは逆効果です。
子どもは恐怖で一時的に行動をやめるかもしれませんが、なぜダメだったのかを理解できません。
感情的に叱ることのデメリットをまとめます。
- 子どもに恐怖心を与えるだけで、根本的な解決にならない。
- 自己肯定感を傷つけ、親への不信感を招く。
- 子どもが感情を表現することを恐れるようになる。
- 親自身の感情コントロールの手本を示せない。
むしろ、親の感情的な反応を見て、子どもはさらに不安になったり、心を閉ざしたりする可能性があります。
僕も「なるべく感情的にならないように」と意識していましたが、これが一番難しく、かつ重要なポイントだと感じています。
NG2:子どもの気持ちを無視・放置する
「どうせ言っても分からない」「泣き止むまで放っておこう」と完全に無視したり、一人で放置したりするのも避けたい対応です(※安全確保や親のクールダウンのための短時間を除く)。
子どもは自分の強い感情にどう対処してよいか分からず、助けを求めているかもしれません。
そこで無視されると、「見捨てられた」と感じ、深い孤独感や不安を抱く可能性があります。
無視・放置が子どもに与える影響です。
- 孤独感と不安:見捨てられたと感じ、情緒不安定になる。
- 不信感:親は助けてくれない存在だと学習してしまう。
- 感情の抑圧:自分の気持ちを表現することを諦めてしまう。
- 問題解決能力の欠如:困難な状況への対処法を学べない。
また、自分の感情を表に出すことを諦め、内に溜め込んでしまうことも考えられます。
たとえすぐには泣き止まなくても、「そばにいるよ」という姿勢を示すことが大切です。
NG3:「ダメ!」と頭ごなしに阻止する
子どもが何かをしようとした時に、理由も説明せずに「ダメ!」と頭ごなしに行動を阻止するのも、子どもの意欲を削いでしまう可能性があります。
特に1歳頃は「自分でやりたい」気持ちが強い時期。
その探求心や挑戦意欲を一方的に否定されると、「どうせやってもダメなんだ」と無気力になるかもしれません。
頭ごなしに阻止することの問題点を挙げます。
- 意欲の低下:「自分でやりたい」気持ちや探求心を削ぐ。
- 思考力の妨げ:なぜダメなのかを考える機会を奪う。
- 指示待ち傾向:自分で判断せず、親の指示がないと動けなくなる。
- 反発心の増大:理由なく押さえつけられると、かえって反発が強くなることも。
もちろん危険な行為は止める必要がありますが、その場合でも、なぜダメなのかを簡単に説明することが大切です。
安全な範囲であれば、まずは見守るという姿勢も時には必要でしょう。
NG4:交換条件を出す、お菓子などで釣る
癇癪を早く収めるために、「〇〇したらお菓子あげる」といった交換条件を出すのは、長い目で見ると望ましくありません。
このような対応を繰り返すと、子どもは「泣けば要求が通る」「言うことを聞く見返りに何かをもらえるのが当たり前」と学習してしまう可能性があります。
交換条件の問題点を整理します。
| 問題点 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 誤った学習 | 癇癪を起こせば要求が通ると学習する |
| 依存心の助長 | 物がないと言うことを聞かなくなる |
| 要求のエスカレート | より大きな見返りを求めるようになる |
| 内発的動機付けの阻害 | 自分の意志で行動する力が育ちにくい |
そうなると、物がないと言うことを聞かなくなったり、より大きな見返りを要求したりするようになるかもしれません。
本来、自分の内的な動機で行うべき行動が、外的な報酬のためになってしまい、自律性が育ちにくくなる恐れもあります。
NG5:嘘をついたり、ごまかしたりする
その場を切り抜けるために、子どもに対して嘘をついたり、曖昧な言葉でごまかしたりするのも避けたい対応です。
例えば、「あとでね」と言って約束を守らなかったり、「鬼が来るからやめなさい」と脅したりすることです。
子どもは大人が思っている以上に、嘘やごまかしに敏感です。
嘘やごまかしがもたらす悪影響です。
- 親への不信感:信頼関係が揺らぎ、言うことを聞かなくなる。
- 子どもの模倣:子ども自身が嘘をついたり、ごまかしたりするようになる。
- 問題解決能力の欠如:現実と向き合う力が育たない。
- 不安感の増大:状況が理解できず、かえって不安になることがある。
このような対応を繰り返されると、子どもは親に対して「信じられない」という気持ちを抱くようになります。
親子の信頼関係は、子どもが安心して成長するための基盤です。
一時的に楽になっても、長期的に見ると信頼関係を損なうリスクの方が大きいでしょう。
親自身のイライラとどう向き合う?心のケアとヒント
1歳児の癇癪に向き合う日々は、親にとっても大きなエネルギーが必要です。
繰り返される癇癪にイライラしたり、疲れてしまったりするのは当然のこと。
親が心の余裕を失うと、子どもへの対応も余裕がなくなりがちです。
ここでは、親自身の心をケアするためのヒントをご紹介します。
完璧じゃなくていい。「まあ、いっか」の精神
モンテッソーリ教育の理念は素晴らしいですが、毎日完璧に実践しようとすると、親自身が追い詰められてしまいます。
「今日も共感できなかった」「また叱ってしまった」と自分を責めてしまうこともあるかもしれません。
でも、そんな日があっても大丈夫。
大切なのは、100点満点の対応を目指すことではなく、「まあ、いっか」「次から少し意識しよう」と、ある種の「ゆるさ」を持つことではないでしょうか。
完璧主義を手放すための考え方です。
- 100点を目指さない:60点くらいできれば上出来と考える。
- 失敗は学びの機会:できなかったことから次に活かせばよい。
- 自分を責めない:「疲れているから仕方ない」と自分を労わる。
- 他人と比べない:「うちはうち」と割り切る。
子育ては長期戦です。
「できる範囲でやればOK」と自分を許すことが、長く続けていくための秘訣かもしれません。
自分の感情に気づき、クールダウンする方法を見つける
癇癪対応中に、自分がイライラし始めていることに気づいたら、意識的にクールダウンすることが大切です。
「あ、今イライラしてるな」と認識するだけでも、少し冷静になれます。
仕事や他のきょうだいの世話などで余裕がない時は特に、意識的にクールダウンする時間を持つことが、感情的な対応を防ぐ助けになります。
クールダウンの方法は人それぞれですが、以下のようなものが考えられます。
- 深呼吸をする:ゆっくり息を吸って、長く吐く。
- その場を少し離れる:(子どもの安全を確保した上で)数秒でもよいので別の部屋に行く。
- 数を数える:心の中で1から10まで数える。
- 別のことを考える:意識的に楽しいことや好きなことを思い浮かべる。
- (最終手段として)一時的に動画などに頼る:親が限界になる前に一時的に頼る。
自分に合った方法を見つけておくことがオススメです。
パートナーや家族と協力体制を作る
子育ては一人で抱え込むものではありません。
パートナーや他の家族と、子どもの癇癪について情報を共有し、協力体制を築くことが非常に重要です。
「どんな時に癇癪を起こしやすいか」「どんな対応が効果的か」などを話し合い、お互いの状況や気持ちを理解し合いましょう。
協力体制を作るメリットを挙げます。
- 負担の軽減:一人で抱え込まず、精神的・肉体的な負担を分担できる。
- 客観的な視点:別の視点からの意見やアドバイスが得られる。
- 一貫した対応:家族間で対応方針を統一できる。
- 親自身の休息:対応を交代することで、休息時間を確保できる。
例えば、我が家では、夫婦間で「同時に叱らない」というルールを決めていました。
どちらかが感情的になりそうな場面でも、もう一方がフォローに回る、あるいは冷静な方が対応を代わる、といった連携で、親も子も追い詰められる状況を防げます。
祖父母などの協力が得られる場合は、積極的に頼りましょう。
外部のサポート(一時保育、子育て支援センターなど)を頼る勇気
家族の協力だけでは限界がある場合や、近くに頼れる人がいない場合は、外部のサポートを積極的に活用しましょう。
一時保育を利用して自分の時間を作ったり、地域の子育て支援センターや保健センターの相談員に話を聞いてもらったりするだけでも、気持ちが楽になります。
利用できるサポートの例です。
- 一時保育・ファミリーサポート:自分の時間や休息を確保する。
- 子育て支援センター・児童館:親子で過ごせる場所、他の親子との交流、相談。
- 保健センター・保健所:育児相談、発達相談、専門機関への紹介。
- 電話相談・オンライン相談:匿名で気軽に相談できる窓口。
厚生労働省のウェブサイトなどでも情報が公開されています。
「人に頼るのは申し訳ない」と感じる必要はありません。
親が心身ともに健康でいることが、子どもの健やかな成長にとって何よりも大切なのです。
引用元:子育て支援 – 厚生労働省
同じ悩みを持つ親と繋がる(オンラインコミュニティなど)
「こんなに大変なのは自分だけじゃないか」と感じる時、同じような悩みを持つ他の親と繋がることも、大きな支えになります。
子育て支援センターでの交流や、SNS・オンラインコミュニティなどを活用しましょう。
他の親と繋がるメリットを挙げます。
- 共感と安心感:「自分だけじゃない」と感じられる。
- 情報交換:具体的な対応策や工夫のヒントが得られる。
- 気分転換:悩みを話すことで気持ちが整理され、スッキリする。
- 孤独感の解消:社会との繋がりを感じられる。
他の親の経験談を聞いたり、悩みを共有したりすることで、「自分だけじゃないんだ」と安心できたり、解決策のヒントが見つかったりします。
共感し合える仲間がいる感覚は、孤独感を和らげ、子育てに向かうエネルギーを与えてくれます。
心地よい距離感での利用を心がけましょう。
モンテッソーリをおうちで実践するための環境づくりのヒント
モンテッソーリ教育では、子どもの自発的な活動を促し、癇癪を予防するためにも「環境設定」を非常に重視します。
特別な教具がなくても、日常生活の中で少し工夫するだけで、子どもが「自分でできた!」と感じ、落ち着いて過ごせる環境を作ることができます。
ここでは、家庭でできる環境づくりのヒントをご紹介します。
子どもの発達に合ったおもちゃを選ぶ
おもちゃは子どもの発達を促す重要なツールです。
特に1歳頃は、指先を使ったり、試行錯誤したりできるおもちゃが適しています。
子どもの現在の興味や発達段階に合った、少しだけ挑戦しがいのあるおもちゃを選ぶことがポイントです。
難しすぎるとフラストレーションの原因に、簡単すぎると飽きてしまいます。
1歳児に適したおもちゃ選びのポイントです。
- 指先を使うもの:つまむ、はめる、押す、回すなど。
- 達成感を得やすいもの:完成形が分かりやすいパズルや積木。
- シンプルなもの:遊び方が限定されず、想像力が広がるもの。
- 五感を刺激するもの:様々な素材、形、重さ、音に触れられるもの。
とはいえ、常に最適なおもちゃを選び続けるのは大変ですよね。
そんな時に便利なのが、知育玩具のサブスクリプションサービスです。
例えば「Cha Cha Cha」のようなサービスでは、モンテッソーリ教育の考え方を取り入れたプランもあり、専門家が選んだおもちゃが定期的に届きます。
様々なおもちゃを試せ、手間や収納場所に悩む必要もありません。
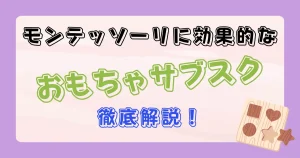
子どもが自分でできる仕組みを作る
日常生活の中で、子どもが「自分でできた!」と感じられる場面を増やすことも、自立心と自己肯定感を育み、癇癪の予防につながります。
そのためには、子どもの目線に立ち、子どもが自分でできるように環境を整えることが大切です。
例えば、以下のような工夫が考えられます。
- 収納:おもちゃや服を、子どもが自分で出し入れしやすい高さや場所に置く。どこに何をしまうか分かるように、収納ボックスに写真やイラストを貼る。(我が家でも実践!)
- 衣服:着脱しやすいデザインの服を選ぶ。
- 手洗い・食事:踏み台を用意して手が届くようにする。割れにくい食器や持ちやすいスプーンを用意する。
- お手伝い:簡単な拭き掃除や洗濯物運びなど、できる範囲のお手伝いを任せる。
大人が手伝えば早くても、ぐっと我慢して子ども自身にやらせてみる。
その「待つ姿勢」も、大切な環境設定のひとつです。
大人の真似ができる道具を用意する
子どもは大人の行動をよく見ていて、真似をしたがるものです。
これはスキルを習得していく上で自然な欲求であり、モンテッソーリ教育ではこの模倣欲求に応えることを大切にします。
危険がない範囲で、子ども用のサイズの「本物に近い」道具を用意すると、子どもは喜んで大人の真似をし、遊びを通して生活スキルを学んでいきます。
模倣活動におすすめの道具例です。
- 掃除道具:子どもサイズのほうき、ちりとり、雑巾、スプレーボトル(水)。
- キッチン道具:安全な子ども用ナイフ、小さな泡だて器、エプロン。
- 園芸・水遊び道具:小さなじょうろ、スコップ、バケツ。
- 身支度道具:手鏡、ブラシ、ハンカチ。
これらの道具を使って「お仕事」に集中する経験は、満足感や達成感につながり、情緒の安定にも貢献します。
集中できる静かなスペースを作る
子どもが落ち着いて遊びや活動(お仕事)に集中できるような、静かで刺激の少ないスペースを家の中に確保することも有効です。
部屋の隅にマットを敷いたり、低い棚で区切ったりするだけでも、「ここは集中する場所」という意識が生まれます。
集中できるスペース作りのポイントです。
- 場所:テレビや人の出入りが少ない、比較的静かな場所。
- 設え:マットや低い棚で空間を区切る。
- おもちゃ/活動:数を絞り、整理して置く。
- 明るさ:自然光が入る、または落ち着いた照明。
そのスペースには、子どもの興味に合わせたおもちゃや活動をいくつか用意し、整理しておきましょう。
テレビや騒がしい音から離れた場所を選び、静かに過ごせる環境を整えることで、過剰な刺激による興奮や癇癪を減らす効果が期待できます。
おもちゃのサブスクを利用すれば、定期的に入れ替わるおもちゃをこのスペースに配置し、常に新鮮な興味を引き出す助けにもなりますね。
まとめ
今回は、1歳のお子さんの「思い通りにならない!」という癇癪について、その理由とモンテッソーリ教育に基づいた向き合い方をご紹介しました。
大変に感じるこの時期の癇癪も、実はお子さんの大切な成長の証であり、モンテッソーリの視点を取り入れることで、親子の関わり方がより建設的で穏やかなものに変わる可能性があります。
1歳児の癇癪は、「自分でやりたい」自我の芽生え、言葉で伝えられないもどかしさ、そして理想と現実の能力のギャップから生じることが多いです。
モンテッソーリ教育は、子どもの内なる力を信じ、その気持ちに共感し、子どもが自ら成長できる環境を整えることを重視します。この考え方が、癇癪への理解と対応のヒントを与えてくれます。
この記事でお伝えした大切なポイントをまとめます。
- 癇癪対応の基本3ステップ:
- まずは共感して気持ちを受け止める
- ダメなことは冷静に線引きする
- 落ち着いたら選択肢や代案を示す
- 避けたいNG対応:
感情的に叱る、無視する、頭ごなしに阻止する、交換条件、嘘やごまかしは避ける。 - 親自身の心のケア:
完璧を目指さず「まあ、いっか」の精神で。クールダウン法を見つけ、パートナーや外部サポートも頼る。 - 環境づくりのヒント:
発達に合ったおもちゃ選び(サブスク活用も◎)、自分でできる仕組み、模倣できる道具、集中できるスペースを用意する。
モンテッソーリ流の関わり方をすべて完璧に行う必要はありません。
大切なのは、お子さんの気持ちに寄り添おうとする姿勢です。
できることから少しずつ取り入れ、試行錯誤しながら、ご家庭に合ったスタイルを見つけていくことが、親子双方にとって心地よい関わりにつながります。
環境を整える一環として、知育玩具のサブスク「Cha Cha Cha」などを検討してみるのもよいでしょう。
専門家が選んだモンテッソーリ教育にも適したおもちゃは、お子さんの興味を引き出し、集中力を育む助けとなり、結果的に癇癪が減る穏やかな時間をもたらすかもしれません。
おもちゃ選びに悩んだら、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
1歳のこの時期は、親にとっても試練の時かもしれませんが、子どもの目覚ましい成長を日々感じられる、かけがえのない時間です。
焦らず、お子さんのペースを大切に、一緒にこの時期を乗り越えていきましょう。
この記事が、あなたの悩みを少しでも軽くし、前向きな子育ての一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
\初月1円からおもちゃのサブスクでモンテッソーリ教育/