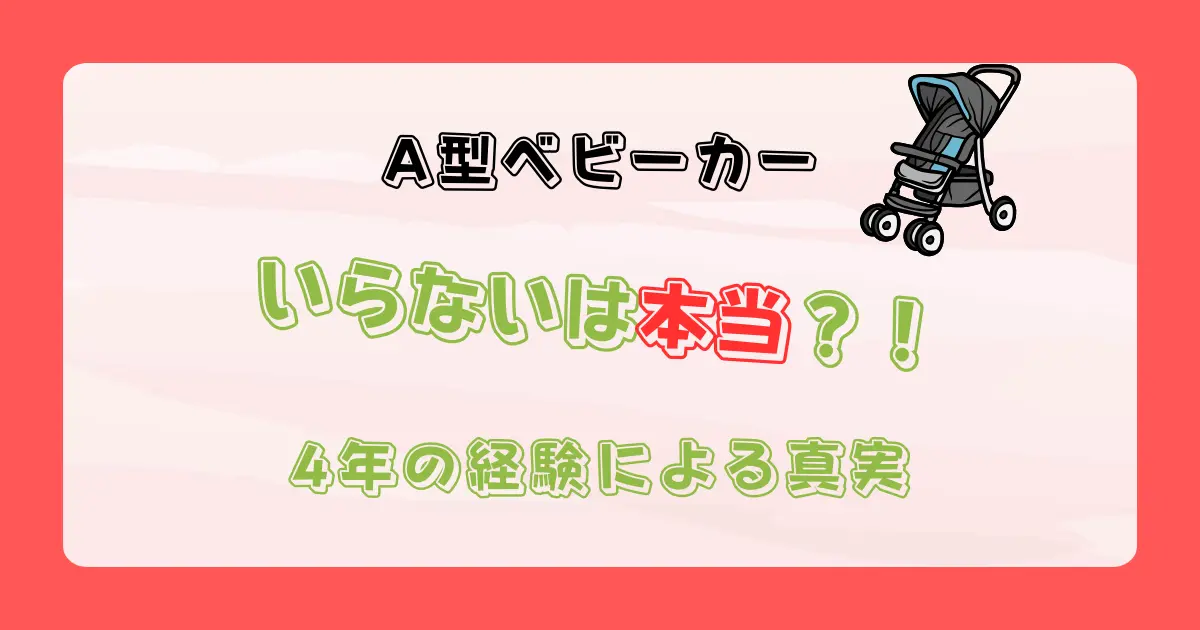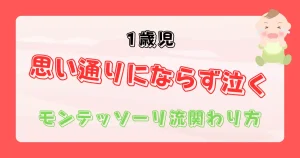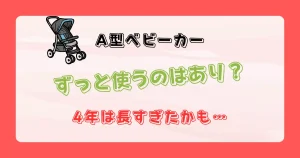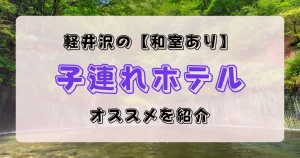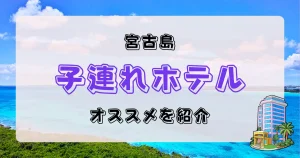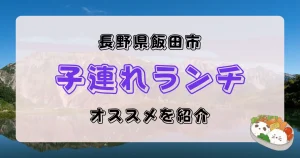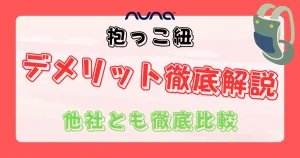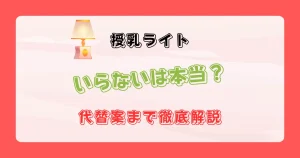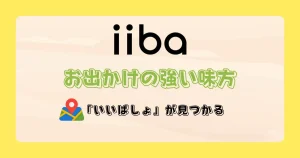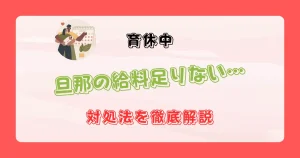- A型ベビーカーは値段も高いし、本当に元が取れるの?
- 大きくて重いって聞くけど、うちの生活スタイルに合うかな?
- 結局すぐ使わなくなるなら、もったいないかも…
- 抱っこ紐があれば、新生児期は乗り切れるんじゃない?
ベビーカー選び、特にA型にするかどうかは、多くのパパママが頭を悩ませるポイントですよね。
僕も4歳と2歳の息子たちを育てる中で、ベビーカー選びには本当に時間をかけましたし、様々な情報を集めました。
A型ベビーカーは「いらない」という声も確かにありますが、一方で「やっぱりあってよかった!」という声も少なくありません。
この記事では、僕が実際にA型ベビーカーを4年以上使い倒した経験を元に、A型ベビーカーの必要性について徹底解説します。
「いらない派」の意見から、僕が感じたメリット、リアルな使い方、そして後悔しないための選び方のポイントまで、具体的にお伝えしますね。
この記事を読むことで、以下の点が明確になりますよ。
- A型ベビーカーが「いらない」と言われる具体的な理由
- 実際にA型ベビーカーを使ったパパが感じるリアルなメリット
- A型・B型・AB型ベビーカーの具体的な違いと比較
- A型ベビーカーを選ばない場合の賢い代替手段
- 後悔しないベビーカー選びのための重要なチェックポイント
A型ベビーカー選びで迷っているあなたの疑問や不安を解消し、納得のいく一台を見つけるお手伝いができれば嬉しいです。
ぜひ最後まで読んで、あなたのベビーカー選びの参考にしてください。
子育てで気になるもののひとつが、知育に効果的なおもちゃはなにか?ということ。
我が家でも、おもちゃ選びに多くの時間を割いてきました。
しかし、結局子どもがハマるかどうかが大事で、それは実際に遊ばせてみないと分からないことも多いです。
そのため、その都度おもちゃを買っていくと出費がかさむだけでなく家におもちゃが溢れることに…
そんな時にオススメしたいのがおもちゃのサブスクです!
子どもの月齢に合わせて最適な知育玩具を毎月 or 隔月などで届けてくれるので、おもちゃ選びに悩む時間を子どもの別のことに使えます。
以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方は是非チェックしてみてください。
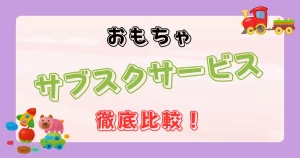
中でも、日本サブスクビジネス大賞2024を受賞したCha Cha Cha(チャチャチャ)は、初月1円から始められるのでまず試してみたいという方にオススメ!
他社で扱っていないキャラクターおもちゃも扱っているので、子どもの好みを確認しやすくてよいです。
\初月1円からスタートできる/
※おもちゃの破損や部品の紛失も原則無料です
※一つひとつ手洗いしていて衛生面も安心です
A型のベビーカーはいらない派の5つの理由
A型ベビーカーの購入を迷うとき、まず気になるのが「本当に必要なの?」という点ですよね。
ここでは、A型ベビーカーが「いらない」といわれる主な理由を5つ紹介します。
価格が高くて費用対効果が気になる
A型ベビーカーは、B型ベビーカーや簡易的なバギーと比べると、一般的に価格が高めに設定されています。
多機能で頑丈な作りになっているためですが、その分「本当にこの金額を出す価値があるのか…」と費用対効果を考えてしまうのは自然なことです。
特に、使用期間が限られているかもしれないと思うと、高価なA型ベビーカーへの投資をためらう気持ちはよくわかります。
出産準備には他にも様々な費用がかかるため、ベビーカーの予算はシビアに考えたいところですよね。
- A型ベビーカーの価格帯:一般的に3万円~10万円以上
- B型ベビーカーの価格帯:一般的に1万円~5万円程度
- 機能と価格のバランスを検討する必要がある
実際に、育児関連用品の価格や機能に関する消費者の声は、国民生活センターのような公的機関にも寄せられることがあるようです。
高価な買い物だからこそ、慎重になるのは当然といえます。
大きくて重たい
A型ベビーカーは、新生児をしっかりと守るためにフレームが頑丈に作られており、その結果として本体が大きく重たくなる傾向があります。
この「大きくて重たい」という点が、日本の住環境やライフスタイルと合わないと感じる人が多いようです。
例えば、マンションでエレベーターがなかったり、玄関スペースが狭かったりすると、毎日の出し入れや保管が負担になることも。
また、公共交通機関をよく利用する場合や、車への積み下ろしを頻繁に行う場合も、その大きさと重さがネックになる可能性があります。
- 持ち運びの負担:特にママひとりで赤ちゃんを抱えながら運ぶのは大変。
- 収納場所の確保:玄関や車のトランクで場所を取る。
- 取り回しの悪さ:混雑した場所や狭い道では動かしにくいことも。
製品の安全性を確保するため、ベビーカーには強度や安定性に関する厳しい基準(例えば、一般財団法人製品安全協会が定めるSG基準など)がありますが、その結果としてある程度の重量はやむを得ない部分もあるのかもしれません。
しかし、日々の使い勝手を考えると、軽量性を重視したいという声も多く聞かれます。
A型は活躍できる期間が短い
A型ベビーカーは、SG基準では生後1ヶ月から最長48ヶ月(4歳)まで使用できるとされていますが、実際に「A型ならでは」のフルリクライニング機能などをフル活用する期間は、意外と短いと感じる方が多いようです。
多くの赤ちゃんは生後7ヶ月頃になると腰がすわり、お座りが安定してきます。
そうなると、より軽量でコンパクトなB型ベビーカーやバギーに魅力を感じ、買い替えを検討するケースも少なくありません。
結果として、「高かったのに、A型として使ったのは半年くらいだった…」という声も聞かれます。
- フルリクライニングが必要な時期:主に生後1ヶ月~7ヶ月頃まで
- 腰すわり後の選択肢:軽量なB型やAB型への移行を検討する家庭が多い
- 子どもの成長や性格によっても使用期間は変動する
もちろん、製品によっては4歳頃まで長く使える設計になっているものもありますが、途中でB型ベビーカーの軽快さが魅力的に映ることは十分に考えられます。
この「実質的な使用期間」と価格のバランスが、費用対効果への疑問に繋がる要因のひとつといえるでしょう。
新生児期は抱っこ紐で十分なことも
新生児期から生後数ヶ月の間は、A型ベビーカーよりも抱っこ紐の方が活躍する場面が多い、という声もよく聞きます。
特に、首がすわる前で頻繁な外出が少ない時期や、赤ちゃんと密着していたい時期には、抱っこ紐の安心感と利便性が際立ちます。
抱っこ紐なら両手が空きますし、電車やバスなどの公共交通機関での移動や、階段の上り下りもスムーズです。
そのため、「A型ベビーカーを買ったものの、結局ほとんど抱っこ紐で過ごした」という経験を持つ方も少なくありません。
- 密着感:赤ちゃんとママ・パパの距離が近く、安心感を与えられる。
- 機動力:階段や狭い場所でも移動しやすい。
- 両手がフリー:上の子がいる場合や、ちょっとした家事にも便利。
親子間の愛着形成の重要性は、こども家庭庁などの公的機関からも情報発信されていますが、抱っこ紐はそのような観点からも有効な育児アイテムといえるでしょう。
A型ベビーカーの必要性を考える上で、抱っこ紐の存在は無視できない要素です。
レンタルや中古で済ませることも可能
「A型ベビーカーの機能は新生児期に少しだけ使いたいけど、購入するのはちょっと…」という場合には、レンタルサービスや中古品を利用するという選択肢もあります。
必要な期間だけA型ベビーカーをレンタルしたり、状態のよい中古品を手頃な価格で購入したりすることで、初期費用を抑えることができます。
特に、使用期間が短いかもしれないと感じている場合や、まずは試してみたいという場合には、これらのサービスは非常に魅力的です。
最近では、ベビー用品のレンタル市場も多様化しており、様々な機種を選べるようになっています。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| レンタル | ・初期費用を抑えられる ・短期間だけ利用できる ・保管場所に困らない | ・長期間だと割高になることも ・希望機種が必ずあるとは限らない ・衛生面が気になる場合も |
| 中古品 | ・新品より安価に購入できる ・人気機種も手に入りやすい | ・状態の確認が必要 ・保証がない場合が多い ・リコール情報を自分で確認する必要がある |
経済産業省などの調査でも、近年サブスクリプションサービスやリユース市場が拡大している傾向が報告されることがありますが、ベビー用品もその例外ではありません。
新品購入にこだわらず、柔軟な選択肢を検討する家庭が増えているといえるでしょう。
それでもあってよかったA型ベビーカーの3つのメリット
「いらない派」の意見も気になるところですが、僕自身はA型ベビーカーがあって本当によかったと感じています。
ここでは、僕が実際に4年以上使って感じたA型ベビーカーのメリットを紹介しますね。
新生児期の安心感!フルリクライニングと頑丈な作り
A型ベビーカーの最大のメリットは、やはり新生児期から使える安心感だと僕は思います。
特にフルリクライニング機能は、まだ首も腰もすわっていない赤ちゃんを、負担の少ない姿勢で寝かせられるので非常に重宝しました。
B型ベビーカーと比較すると、A型は作りがしっかりしていて、ガタつきが少ない点も安心材料でした。
ちょっとした段差や振動も、頑丈なフレームと大きめのタイヤが吸収してくれるような感覚があり、初めての子育てで何かと不安が多かった僕にとっては、この「守られている感」が何より心強かったです。
- フルリクライニング:首すわり前の赤ちゃんも安心・快適な姿勢を保てる。
- 頑丈なフレーム:走行時の安定性が高く、振動も吸収しやすい。
- 対面式機能:赤ちゃんの顔を見ながら押せるので、親も子も安心。
消費者庁などの公的機関からも、ベビーカーの安全な使用に関する注意喚起が度々出されていますが、A型ベビーカーは、安全基準を満たした上で、さらに新生児への配慮がなされている製品が多いと感じます。
低月齢のうちは昼寝に最適
低月齢の赤ちゃんは、本当によく寝ますよね。
お散歩の途中や、ちょっとしたお出かけ先でも、気づけばスヤスヤ…なんてことが日常茶飯事でした。
そんなとき、A型ベビーカーのフルリクライニングは、まさに簡易ベッドのように大活躍しました。
特に上の子はベビーカーに乗るとよく寝るタイプだったので、外出先で寝てしまっても、無理に起こさずにそのまま寝かせておけるのは本当に助かりました。
カフェで少し休憩したいときや、買い物中など、赤ちゃんが快適に眠ってくれることで、親も少しだけ自分の時間を持てたり、用事を済ませたりすることができました。
- 外出先での急な眠気にも対応しやすい。
- フラットに近い状態で寝かせられるため、赤ちゃんの体に負担がかかりにくい。
- 親の精神的な余裕にもつながる。
厚生労働省が推進する「健やか親子21」といった取り組みの中でも、赤ちゃんの健やかな睡眠の重要性が指摘されていますが、外出時にも質の高い睡眠環境を少しでも提供できるのは、A型ベビーカーの大きな利点だと感じています。
意外と長く使えることも!我が家では4年以上
A型ベビーカーは「使用期間が短い」といわれることもありますが、我が家の場合は結果的に4年以上、かなり長く活躍してくれました。
もちろん、途中でB型ベビーカーを譲り受ける機会があり、下の子が2歳になる頃からはそちらも併用するようになりましたが、上の子は4歳を過ぎても、疲れたときや遠出の際にはA型ベビーカーに乗ることがありました。
5歳になった今でも、テーマパークなど長時間歩く場所では「乗りたい!」ということがあるくらいです(さすがにもう耐荷重的に厳しいですが…笑)。
これは、うちの子が比較的ベビーカーに乗るのが好きなタイプだったことや、A型ベビーカーのシートが広めで、大きくなっても窮屈さを感じにくかったからかもしれません。
- 子どもがベビーカー好きだった。
- シートがある程度広く、成長しても快適に乗れた(と感じた)。
- 親が「まだ使えるなら使おう」というスタンスだった。
もちろん、これはあくまで我が家のケースであり、全ての子どもや家庭に当てはまるわけではありません。
ただ、「A型=短期間」と決めつけずに、製品の耐久性や子どもの成長、ライフスタイルによっては、予想以上に長く頼れる存在になる可能性もある、ということはお伝えしたいです。
A型ベビーカーの使い方のリアルを実体験を元に紹介
ここでは、僕が実際にA型ベビーカーをどのように使ってきたか、そのリアルな体験談をお話しします。
これからベビーカーを選ぶ方の参考になれば嬉しいです。
我が家のA型ベビーカーの活躍期間とB型への移行
我が家では、長男が生まれるタイミングでA型ベビーカーを購入しました。
前述の通り、上の子は4歳くらいまでそのA型ベビーカーをメインで使っていました。
下の子が生まれてからは、下の子がそのA型ベビーカーを使い、上の子は状況に応じて歩いたり、疲れたら抱っこしたり、という形でした。
B型ベビーカーに完全に切り替えたのは、下の子が2歳になる少し前くらいです。
きっかけは、使っていたA型ベビーカーのタイヤに少しガタがきていたことと、ちょうどそのタイミングで兄からB型の折りたたみベビーカーを譲ってもらえたことでした。
また、次男は長男と比べてベビーカーであまり寝ず、周りをキョロキョロ見ていることが多かったので、視界が広く軽いB型の方が合っているかな、と感じたのも理由のひとつです。
- A型使用期間:上の子は約4年間、下の子は約2年間(その後B型へ)
- B型移行のきっかけ:A型の老朽化、B型を譲り受けた、下の子の成長と性格
結果的に、我が家ではA型ベビーカーは兄弟合わせて4年以上活躍してくれたことになります。
B型への移行は、製品の寿命や子どもの成長など、様々な要因が絡み合って自然な流れで決まることが多いのかもしれません。
抱っこ紐との併用のメリットとデメリット
ベビーカーを使っていない時は、基本的にエルゴの抱っこ紐を愛用していました。
特に新生児期や、電車での移動が多い時、ぐずった時などは抱っこ紐が大活躍でしたね。
ベビーカーと抱っこ紐の併用は、多くのご家庭で実践されていると思いますが、僕が感じたメリットとデメリットは以下の通りです。
- 段差や悪路に強い:ベビーカーでは進みにくい場所も抱っこ紐ならスムーズ。
- 赤ちゃんの安心感:親と密着することで赤ちゃんが落ち着きやすい。
- 機動性:両手が空くので、買い物や上の子のケアもしやすい。
- 親の身体への負担:特に長時間の使用や、僕も妻も腰痛持ちなので、腰への負担は大きかったです。
- 夏の暑さ:密着している分、夏場は親子共に汗だくになることも。
- 荷物の問題:抱っこ紐使用時は、荷物を持つのが大変。
僕の経験からいうと、ベビーカーと抱っこ紐は、どちらか一方というより、それぞれのメリットを活かして状況に応じて使い分けるのがベストだと感じています。
特に腰痛持ちのパパママは、抱っこ紐の連続使用時間や正しい装着方法に気をつけることが大切ですね。
ベビーカー選びにおいて重視したポイント
長男が生まれる前にA型ベビーカーを選んだ際、そしてその後B型を譲り受けて使う中で、僕がベビーカー選びで「これは大事だな」と感じたポイントがいくつかあります。
まず、住環境への配慮は欠かせませんでした。
僕たちは子どもが生まれてから一度引越しを経験し、どちらもマンション住まいでした。
そのため、エレベーターの有無(幸いどちらもありました)や、エントランスからエレベーター、そして自宅玄関までの動線にスロープがしっかり整備されていて、ベビーカーでスムーズに移動できるかは非常に重視しました。
- 住環境への適合:マンションならエレベーター、スロープの有無、玄関スペース。
- 走行安定性:特に新生児期はガタつきが少ない、しっかりした作りのもの。
- シートの快適性:リクライニング角度、シートの広さ、クッション性。
- 操作性:押しやすさ、小回りの利きやすさ(これはB型を使ってより実感)。
我が家の主な移動手段は徒歩、電車、バスで、車での移動はほとんどありません。
そのため、車への積み下ろしのしやすさよりは、駅の改札を通りやすいか、バスに持ち込みやすいかといった点を少し気にしました(ただ、これがベビーカー選びに決定的な影響を与えたわけではありません)。
それよりも、日々の散歩や買い物での押しやすさ、子どもの乗り心地を優先した記憶があります。
【盲点】タイヤの耐久性と耐荷重
ベビーカー選びで、僕が後から「これは盲点だったな…」と痛感したのが、タイヤの耐久性と耐荷重です。
我が家のA型ベビーカーは4年ほどでタイヤにガタがきてしまい、最終的にはそれがB型へ移行するひとつのきっかけにもなりました。
毎日使っていると、タイヤは確実に摩耗していきますし、フレームにも少しずつ負荷がかかります。
街で他のベビーカーを見ていると、明らかにタイヤが大きくて頑丈そうなものもあり、「ああいうタイプならもっと長持ちしたのかな」と思うこともありました。
- タイヤの材質・大きさ:耐久性や走行性に影響。シングルタイヤかダブルタイヤかなど。
- フレームの強度:長期間の使用に耐えられるか。
- メーカー推奨耐荷重:子どもの体重+荷物の重さを考慮。
- 使用想定期間:何歳くらいまでそのベビーカーに乗せる予定か。
さらに恥ずかしながら、後で確認したら我が家で使っていたA型ベビーカーの耐荷重は15kgまでだったのですが、長男はそれを超えてからも乗せてしまっていました…。
幸い事故には繋がりませんでしたが、これは本当に反省点です。
これからベビーカーを選ぶ方は、何歳くらいまでその一台に乗せる予定なのかをある程度想定し、それに合った強度や耐荷重の製品を選ぶことを強くオススメします。
安全に関わることなので、ここは妥協しない方がよいポイントです。
A型ベビーカーはいらない?B型ベビーカーでいい?両社を徹底比較
A型ベビーカーの必要性を考える上で欠かせないのが、B型ベビーカーとの比較です。
それぞれの特徴を理解し、自分のライフスタイルや赤ちゃんの成長に合わせて選ぶことが大切です。
ここでは、A型、B型、そしてAB型ベビーカーの違いを詳しく見ていきましょう。
【一覧表】A型・B型・AB型の違いを比較表で一目瞭然
まずは、各ベビーカータイプの特徴を一覧表で比べてみましょう。
これにより、それぞれの違いが視覚的に分かりやすくなります。
| 項目 | A型ベビーカー | B型ベビーカー | AB型ベビーカー |
|---|---|---|---|
| 対象月齢の目安 | 生後1ヶ月~最長48ヶ月 | お座りができる生後7ヶ月頃~最長48ヶ月 | 生後1ヶ月~最長48ヶ月 |
| リクライニング | フルリクライニング可能(150度以上) | 簡易的または無し(100度以上が目安) | フルリクライニング可能(A型に準ずる) |
| 対面使用 | 可能な機種が多い | ほぼ不可(背面式が主流) | 可能な機種が多い |
| 本体重量 | 重め(6kg~10kg程度) | 軽め(3kg~6kg程度) | A型とB型の中間(4kg~7kg程度) |
| サイズ感 | 大きめ | コンパクト | A型よりはコンパクト |
| 価格帯の目安 | 高価(3万円~) | 比較的安価(1万円~) | A型に近いかやや安価 |
| 主なメリット | 新生児期の安全性、多機能、安定性 | 軽量、コンパクト、持ち運びやすい、手頃な価格 | 新生児から使え、A型より軽量・コンパクトな場合が多い |
| 主なデメリット | 重い、大きい、価格が高い、使用期間が短いと感じることも | 新生児不可、機能がシンプル、走行安定性はA型に劣る場合も | B型ほどの軽さはない、中途半端と感じることも |
この表はあくまで一般的な傾向です。
個々の製品によって仕様は異なりますので、購入前には必ず詳細を確認してくださいね。
ベビーカーの安全な使用期間や機能については、一般財団法人製品安全協会のウェブサイト(SGマーク製品一覧「ベビーカー」)などでSG基準に関する情報を確認できます。
A型ベビーカーの特徴・メリット・デメリット
A型ベビーカーは、新生児期の赤ちゃんを安全かつ快適に乗せることを最優先に設計されています。
しっかりとしたフレームや衝撃吸収機能、フルリクライニングなど、デリケートな赤ちゃんを守るための機能が充実しているのが特徴です。
- 新生児から使える:退院後すぐから使用できる安心感があります。
- フルリクライニング:赤ちゃんを寝かせた状態で乗せられ、負担が少ないです(僕もこの点を重視しました)。
- 走行安定性が高い:頑丈な作りで、段差やデコボコ道でも比較的スムーズに進めます。
- 対面式可能:赤ちゃんの顔を見ながら押せるので、親も子も安心できます。
- 機能が豊富:大きな幌や収納バスケットなど、便利な機能が充実しています。
- 価格が高い:初期費用がB型に比べて高額になりがちです。
- 大きくて重い:持ち運びや収納に場所を取り、手間がかかることがあります。
- 使用期間が短いと感じることも:B型への買い替えを考えると、実質的なA型としての活躍期間は限定的かもしれません。
A型ベビーカーは、特に第一子で、初めての育児に不安を感じているパパママにとって、安心感という面で大きなメリットがあるといえるでしょう。
僕自身、この安心感には何度も助けられました。
B型ベビーカーの特徴・メリット・デメリット
B型ベビーカーは、赤ちゃんの腰がすわり、お座りができるようになってからの使用を想定して作られています。
最大の特徴は、その軽さとコンパクトさ。
持ち運びや収納がしやすく、セカンドベビーカーとしても人気があります。
- 軽量・コンパクト:持ち運びが楽で、収納場所にも困りにくいです。
- 操作性がよい:小回りが利き、狭い場所でも扱いやすいものが多いです。
- 価格が手頃:A型に比べて購入しやすい価格帯の製品が多いです。
- セカンドベビーカーに最適:旅行やお出かけ用として気軽に使えるのが魅力です。
- 新生児期には使えない:お座りができるようになるまでは使用できません。
- リクライニング機能が限定的:フルフラットにはならず、長時間の睡眠には向きません。
- 衝撃吸収性はA型に劣ることも:簡易的な作りのため、デコボコ道などでは振動が伝わりやすい場合があります。
- 対面式はほぼない:基本的に背面式なので、赤ちゃんの様子が見えにくいです。
B型ベビーカーは、赤ちゃんの活動範囲が広がり、親子でアクティブにお出かけする機会が増えてくると、その軽快さが非常に魅力的に感じられるでしょう。
我が家でも、次男が2歳近くなってからはB型の軽さが本当に重宝しました。
AB型ベビーカーの特徴・メリット・デメリット
AB型ベビーカーは、その名の通り、A型ベビーカーの新生児期からの対応機能と、B型ベビーカーの軽さ・コンパクトさを兼ね備えることを目指したタイプです。
SG基準上はA型に分類されますが、メーカーによっては「軽量A型」などとも呼ばれます。
- 新生児から使える:A型同様、退院後すぐから使用可能です。
- A型より軽量・コンパクトなモデルが多い:持ち運びや収納の負担が軽減されます。
- 1台で長く使える可能性がある:A型とB型の「いいとこ取り」で、買い替えずに済むことも。
- 両対面式も選択可能:新生児期は対面、成長したら背面に切り替えられる機種もあります。
- B型ほどの軽さはない:あくまでA型基準なので、超軽量B型には及びません。
- 価格はA型に近いことも:B型よりは高価になる傾向があります。
- 機能や安定性が中途半端と感じることも:「A型ほどの安定感はないが、B型ほど軽くもない」という印象を持つ場合も。
AB型ベビーカーは、「A型の安心感も欲しいけど、重いのはちょっと…」というパパママや、「できれば1台で長く使いたい」と考える方にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。
ただし、どこまでの機能を求めるかによって、その評価は変わってくるかもしれません。
A型ベビーカーはなしでもOK?賢い4つの代替手段
「やっぱりA型ベビーカーはうちには必要ないかも…」と感じた方のために、A型ベビーカーを選ばない場合の賢い代替手段を4つご紹介します。
それぞれのメリット・デメリットを理解して、ご家庭に合った方法を見つけてくださいね。
メインは抱っこ紐で首がすわるまで乗り切る
新生児期から首がすわるまでの数ヶ月間(一般的に生後3~4ヶ月頃まで)は、抱っこ紐をメインの移動手段として乗り切るという選択肢です。
この時期は外出の機会もそれほど多くなく、赤ちゃんとしっかり密着できる抱っこ紐は、親子ともに安心感があります。
僕の経験でも、ベビーカーと併用していたエルゴの抱っこ紐は、特に低月齢のうちは大活躍でした。
段差がある場所や混雑した場所でもスムーズに移動できるのは大きなメリットです。
ただし、長時間の使用は親の身体、特に腰への負担が大きいことは覚悟しておく必要があります。
- 新生児対応の抱っこ紐を選ぶ:インサートが必要なタイプや、首をしっかりサポートできるものを選びましょう。
- 正しい装着方法をマスターする:赤ちゃんの安全と親の負担軽減のために重要です。
- 親の体調管理:腰痛対策や適度な休憩を心がけましょう(僕も妻も腰痛持ちなので実感しています)。
- その後の移動手段:首すわり後、B型ベビーカーやAB型ベビーカーの購入を検討します。
この方法は、初期費用を抑えたい方や、できるだけコンパクトに育児グッズを揃えたい方には魅力的な選択肢といえるでしょう。
ただし、抱っこ紐だけでは荷物を持つのが大変だったり、夏場は暑かったりといったデメリットも考慮しておく必要があります。
最初からAB型ベビーカーを選ぶ
「新生児期から使えて、できれば1台で長く使いたい」というニーズに応えるのが、AB型ベビーカーです。
A型ベビーカーの安心機能と、B型ベビーカーの利便性をバランスよく取り入れたタイプで、最初からこれを選ぶというのも賢い選択のひとつです。
A型ベビーカーよりも軽量でコンパクトなモデルが多く、それでいて新生児を乗せるためのリクライニング機能や衝撃吸収性も備えています。
「A型は重すぎるけど、B型が使えるようになるまで待てない…」という場合に、有力な候補となるでしょう。
- 1台で済むため、買い替えの手間や費用を抑えられる可能性がある。
- A型に比べて持ち運びや収納がしやすいモデルが多い。
- 新生児期から安心して使用できる機能を備えている。
ただし、AB型ベビーカーも製品によって特徴は様々です。
「軽量性」を重視するあまり、A型本来の安定性や機能性がやや劣るモデルもあれば、逆にしっかりした作りでA型に近い重さのモデルもあります。
何を優先するかを明確にして選ぶことが大切です。
短期間だけならレンタルや中古を活用する
A型ベビーカーが最も活躍する新生児期から数ヶ月間だけ、レンタルサービスを利用したり、中古品を購入したりするのも非常に合理的な方法です。
特に「A型は短期間しか使わないかもしれない」と考えている方や、「購入前に一度試してみたい」という方にはオススメです。
僕自身はレンタルを利用した経験はありませんが、もし当時このようなサービスがもっと身近にあれば、検討したかもしれません。
レンタルなら最新機種を試すこともできますし、使い終われば返却するだけなので保管場所にも困りません。
中古品なら、人気の高機能モデルを比較的安価に手に入れられる可能性があります。
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| レンタル | ・初期費用が安い ・必要な期間だけ使える ・保管場所に困らない ・様々な機種を試せる | ・長期間だと割高になることも ・衛生面が気になる場合もある ・破損時の対応確認が必要 |
| 中古品 | ・新品より安価 ・掘り出し物が見つかることも | ・製品の状態を入念にチェック ・安全基準(SGマーク等)を確認 ・リコール対象でないか確認 |
ベビー用品のレンタルやリユース市場は近年拡大しており、多くの選択肢があります。
中古品を購入する際には、製品の状態確認やリコール情報の確認など、消費者庁のような公的機関が発信する注意点も参考にするとよいでしょう。
安全面には十分配慮しつつ、賢く活用したいですね。
車がメインならトラベルシステムを活用する
普段の移動が車中心というご家庭であれば、「トラベルシステム」という選択肢も非常に便利です。
トラベルシステムとは、対応するチャイルドシート(ベビーシート)とベビーカーをドッキングさせて使えるもので、眠っている赤ちゃんを起こさずに車からベビーカーへ、ベビーカーから室内へと移動させることが可能です。
ベビーシート自体が新生児の身体をしっかりサポートするように設計されているため、A型ベビーカーの代わりとして十分に機能します。
赤ちゃんをチャイルドシートに乗せたまま移動できる手軽さは、車移動が多い家庭にとっては大きなメリットとなるでしょう。
- 赤ちゃんを起こさずに車とベビーカー間で移動できる。
- ベビーシートがそのままベビーカーのシートになるため効率的。
- 退院時からすぐに使える。
ただし、トラベルシステムで使用するベビーシートは、一般的に使用期間が1歳~1歳半頃までと短い点には注意が必要です。
また、ベビーシートを装着した状態のベビーカーは、やや重くなる傾向があります。
ご家庭のライフスタイルと照らし合わせて、メリットが大きいかどうかを判断するとよいでしょう。
後悔しないベビーカー選びにするために!おさえるべき5つのポイント
A型、B型、AB型、あるいは代替手段…どんな選択をするにしても、後悔しないベビーカー選びのためには、いくつか押さえておくべき重要なポイントがあります。
僕の経験も踏まえながら、5つのポイントにまとめました。
ライフスタイルと住環境に合わせる
まず最も大切なのは、ご自身のライフスタイルと住環境にベビーカーが合っているかという点です。
どんなに高機能なベビーカーでも、生活の中で使いにくければ意味がありません。
例えば、僕のように主に徒歩や公共交通機関で移動するのか、それとも車移動が中心なのかで、求める機能は大きく変わってきます。
また、住んでいる場所も重要です。
マンションでエレベーターがない場合は軽量性が最優先になるかもしれませんし、玄関が狭ければコンパクトに折りたためることが必須条件になるでしょう。
僕もマンション住まいだったので、エレベーターの有無やスロープの使いやすさは、物件選びの際にもベビーカー使用を想定してチェックしました。
- 主な移動手段:徒歩、電車、バス、車?
- 住居タイプ:戸建て、マンション? エレベーターやスロープはある?
- 収納スペース:玄関や車に十分なスペースがあるか?
- 使用頻度と主な用途:毎日使う?週末だけ? 近所の散歩?遠出?
これらの点を具体的にイメージすることで、自分たちに必要なベビーカーの条件が見えてくるはずです。
カタログスペックだけでなく、実際の生活動線を思い浮かべながら検討することが大切です。
軽さとコンパクトさ vs 安心感・頑丈さのバランスを考える
ベビーカー選びでは、「軽さ・コンパクトさ」と「安心感・頑丈さ」が、しばしばトレードオフの関係になります。
一般的に、軽量でコンパクトなモデルは持ち運びや収納に便利ですが、安定性や衝撃吸収性の面では、どっしりとした頑丈なモデルに劣る場合があります。
どちらを優先するかは、まさにライフスタイルや重視するポイントによって異なります。
例えば、頻繁に持ち運んだり、公共交通機関を利用したりするなら軽さは重要です。
一方で、僕がA型を選んだ理由のひとつでもあるように、新生児期の安心感や走行時の安定性を重視するなら、ある程度の重さや大きさは許容範囲と考えることもできます。
| 重視するポイント | 向いているタイプ(傾向) | 考慮点 |
|---|---|---|
| 軽さ・コンパクトさ | B型、軽量なAB型 | 走行安定性、衝撃吸収性、機能のシンプルさ |
| 安心感・頑丈さ | A型、しっかりしたAB型 | 本体重量、サイズ、持ち運びの負担 |
実際に店舗で実物を押し比べてみたり、折りたたんで持ってみたりすると、そのバランス感覚が掴みやすいでしょう。
赤ちゃんだけでなく、主に操作するパパママにとっても使いやすいかどうかが、長く愛用できるかの分かれ道になります。
操作性(押しやすさ)はストレス軽減の鍵
毎日使うものだからこそ、ベビーカーの操作性(押しやすさ)は非常に重要です。
スムーズに押せない、小回りが利かない、ちょっとした段差でつまずく…そんなベビーカーでは、お出かけ自体がストレスになってしまいます。
逆に、スイスイと軽快に操作できるベビーカーなら、赤ちゃんとのお出かけがもっと楽しくなるはずです。
押しやすさに影響する要素としては、タイヤの大きさや種類(シングルタイヤかダブルタイヤか)、サスペンションの有無、ハンドルの高さや形状などが挙げられます。
特に、片手で操作する場面も意外と多いので、片手でもスムーズに方向転換できるかどうかもチェックしておくとよいでしょう。
- タイヤ:大きさ、材質、数(シングル/ダブル)、サスペンション機能。
- ハンドル:高さが調節できるか、握りやすいか。
- 小回り性能:狭い場所での旋回がスムーズか。
- 段差の乗り越えやすさ:軽い力で段差をクリアできるか。
僕も、B型ベビーカーを使い始めてから、A型にはなかった軽快な操作性に感動した経験があります。
もちろん、A型にはA型の安定した押し心地のよさがありましたが、何を重視するかで選ぶポイントは変わってきますね。
可能であれば、実際に店舗で荷物を乗せた状態で試走してみるのが一番です。
赤ちゃんの快適性と安全性
ベビーカー選びで絶対に妥協できないのが、赤ちゃんの快適性と安全性です。
赤ちゃんが長時間過ごす場所になるわけですから、乗り心地がよく、安心して任せられる製品を選びたいですよね。
特に新生児期から使うA型ベビーカーの場合は、この点がより重要になります。
快適性については、シートの広さやクッション性、リクライニングの角度、通気性、日差しを遮る幌の大きさなどをチェックしましょう。
安全性については、まず第一にSGマークが付いているかを確認します。
これは、製品安全協会が定めた安全基準に適合していることを示すマークです。
- SGマークの有無:製品安全協会の安全基準適合マーク。
- シートベルト:5点式がより安全性が高いといわれています。
- フレームの剛性:ぐらつきがないか、しっかりしているか。
- ブレーキ性能:確実にロックできるか、操作しやすいか。
僕がA型を選んだ大きな理由のひとつも、この「新生児期の安心感」でした。
フルリクライニングでぐっsり眠れること、しっかりしたフレームで守られている感覚は、親にとっても大きな安心に繋がりました。
消費者庁などの公的機関からもベビーカーの安全な使用に関する注意喚起がなされており、製品選びの段階から安全性を意識することが求められています。
収納力やその他の機能
主要なポイントに加えて、収納力やその他の便利機能も、日々の使い勝手を左右する重要な要素です。
赤ちゃんとのお出かけは、おむつやおしりふき、着替え、飲み物など、何かと荷物が多くなりがちです。
そのため、ベビーカーの下にある収納バスケットの容量や、荷物の出し入れのしやすさは意外と重要です。
その他にも、片手で簡単に折りたためる機能、シートの高さを調節できるハイシート機能、シートを取り外して丸洗いできる機能など、あると便利な機能は様々です。
デザインやカラーも、毎日使うものだからこそ、気に入ったものを選びたいですよね。
- 収納バスケット:容量が大きいか、間口が広くて出し入れしやすいか。
- 折りたたみ機能:片手で簡単にできるか、自立するか。
- ハイシート:地面からの熱やホコリを遠ざけ、乗せ降ろしもしやすい。
- メンテナンス性:シートや幌が洗濯できるか。
- デザイン:好みのデザインやカラーか。
全ての機能を満たす完璧なベビーカーを見つけるのは難しいかもしれませんが、自分たちの優先順位を明確にして、より多くの条件を満たす一台を選べるとよいですね。
僕も、もう少し下カゴが大きければ…と思ったことは何度かありました(笑)。
A型ベビーカーにあると便利な付属品
ベビーカー本体だけでなく、便利な付属品を揃えることで、お出かけはさらに快適になります。
ここでは、僕が実際に使ってみて便利だったものや、欲しかったものも含めていくつか紹介します。
レインカバー
急な雨や風から赤ちゃんを守ってくれるレインカバーは、必須アイテムといっても過言ではありません。
ベビーカーの機種によっては専用のものが用意されている場合もありますし、汎用品も多数販売されています。
透明で赤ちゃんの様子が見えるものや、通気性を考慮したものがオススメです。
特に梅雨の時期や、天候が不安定な季節のお出かけには欠かせません。
使わない時はコンパクトに畳んで収納バスケットに入れておくと安心ですね。
- 雨よけ、風よけ、花粉対策にも。
- 専用品か汎用品か、ベビーカーに合うサイズを選ぶ。
- 取り付けやすさや、視認性もチェック。
雨の日の外出は視界も悪くなりがちなので、レインカバーで赤ちゃんを守りつつ、パパママも安全に注意して操作することが大切です。
製品によっては、防寒対策としても役立つことがありますよ。
ドリンクホルダー
これは、我が家はなかったけど欲しかった…と心から思うアイテムです(笑)。
特に夏場のお散歩中など、自分の飲み物や赤ちゃんのマグをサッと置ける場所があると、本当に便利だと思います。
ベビーカーを押しながらだと、飲み物を手に持っているのは意外と大変なんですよね。
後付けできるタイプがたくさん販売されていて、ハンドルの好きな位置に取り付けられるものが多いようです。
スマホも一緒に置けるタイプなど、多機能なものも出ていますね。
- パパママの飲み物や哺乳瓶、マグの置き場所に。
- 取り付けが簡単で、様々な太さのハンドルに対応できるものが便利。
- 安定性があり、飲み物がこぼれにくい構造か確認。
これからベビーカーを購入される方は、ぜひ検討してみてください。
小さなアイテムですが、お出かけの快適度が格段に上がるはずです!
ベビーカーフック(荷物かけ)
買い物袋やマザーズバッグなど、ちょっとした荷物をかけるのに便利なのがベビーカーフックです。
ハンドル部分に取り付けて使います。
両手が空くので、ベビーカーの操作もしやすくなりますし、荷物の置き場所に困ることが減ります。
ただし、あまり重いものをかけすぎるとベビーカーのバランスが崩れて転倒する危険性があるので、注意が必要です。
耐荷重をしっかり確認し、安全な範囲で使用することが大切です。
- 耐荷重を守る:かけすぎは転倒の原因になります。
- バランスを考える:左右均等にかけるなど工夫しましょう。
- フックの形状:荷物が滑り落ちにくい、しっかり固定できるものが安心です。
ベビーカーのハンドルに荷物をかけすぎたことによる転倒事故は、消費者庁などの注意喚起でも取り上げられることがあります。
便利なアイテムですが、安全第一で使いましょう。
ベビーカーアンダーバッグ
ベビーカーの下カゴだけでは収納が足りない…という場合に便利なのが、アンダーバッグです。
デッドスペースになりがちなベビーカーシートの下に取り付けて、収納容量をアップさせることができます。
おむつやおしりふき、着替えなど、すぐには使わないけれど持っておきたいものを入れておくのに便利です。
メッシュ素材で中身が見やすいものや、取り外してそのまま持ち運べるバッグタイプなど、様々な種類があります。
ベビーカーの構造によっては取り付けられない場合もあるので、適合するかどうか確認が必要です。
- 収納スペースを増やし、荷物整理に役立つ。
- 下カゴに入りきらない大きめの荷物も収納できる場合がある。
- 重心が低くなるため、ベビーカーの安定に寄与することも(ただし、重すぎる荷物はNG)。
- フックにかけると重くて倒れてしまう荷物も、アンダーバッグに入れれば倒れる心配が減る。
アンダーバッグを活用することで、ベビーカーフックにかける荷物を減らし、より安全に走行できるというメリットも期待できますね。
荷物が多いパパママの強い味方です。
扇風機
夏の暑い日のお出かけには、ベビーカー用の扇風機があると赤ちゃんも快適に過ごせます。
クリップ式でベビーカーの幌やフレームに簡単に取り付けられるものが主流です。
充電式や電池式など、電源タイプも様々です。
選ぶ際には、羽根に指が直接触れないように安全ガードが付いているか、風量の調節ができるかなどをチェックするとよいでしょう。
また、音が静かなものを選ぶと、赤ちゃんの眠りを妨げません。
- 安全性:羽根ガード、素材の安全性(BPAフリーなど)。
- 風量調節機能:赤ちゃんの状態に合わせて調節できると便利。
- 静音性:作動音が小さいものが望ましい。
- 電源タイプ:USB充電式、電池式など。使用時間も確認。
近年は特に夏の暑さが厳しく、熱中症対策は非常に重要です。
環境省などの公的機関も、乳幼児の熱中症予防に関する情報を発信しています。
ベビーカー扇風機は、そのような対策のひとつとして役立つアイテムです。
スマホホルダー
地図アプリを見たり、急な連絡に対応したりと、ベビーカーを押しながらスマートフォンを操作したい場面は意外とありますよね。
そんな時に便利なのが、スマホホルダーです。
ベビーカーのハンドルに取り付けて、スマートフォンを安全かつ見やすい位置に固定できます。
様々なサイズのスマートフォンに対応できる汎用タイプや、360度回転して角度調節ができるものなどがあります。
運転中の「ながらスマホ」は非常に危険ですが、安全な場所に停止してサッと情報を確認したい場合には重宝します。
- ナビアプリの確認や、音楽再生などに便利。
- 着信や通知をすぐに確認できる(安全な場所で)。
- スマホをポケットやバッグから取り出す手間が省ける。
ただし、スマートフォンに気を取られて赤ちゃんの安全確保や周囲への注意が疎かにならないよう、使用には十分な配慮が必要です。
あくまで補助的なアイテムとして、賢く活用しましょう。
まとめ
A型ベビーカーが「いらない」かどうか、その答えはひとつではありません。
家族のライフスタイルや住環境、そして何よりも「何を重視するか」によって、最適な選択は変わってきます。
この記事では、「いらない派」の主な理由から、僕自身が4年以上A型ベビーカーを使って感じたメリット、リアルな使い方、そして後悔しないための選び方のポイントまで、様々な角度から情報をお伝えしてきました。
A型ベビーカーには確かに価格が高い、大きいといったデメリットもありますが、新生児期の圧倒的な安心感や、製品によっては長く使えるというメリットもまた、確かな事実として存在します。
大切なのは、周りの意見や情報に流されるのではなく、この記事で得た知識や僕の体験談を参考にしながら、ご自身の家庭にとって何がベストなのかをじっくり考えることです。
抱っこ紐との併用、B型やAB型への移行、レンタルや中古の活用など、選択肢はたくさんあります。
特に、僕が盲点だと感じたタイヤの耐久性や耐荷重といったポイントも、ぜひ購入時の参考にしてください。
最終的にどんな選択をするにしても、赤ちゃんとパパママが安全で快適にお出かけできることが一番です。
この記事が、あなたのベビーカー選びの一助となり、後悔のない、満足のいく一台と出会えることを心から願っています。
子育てで気になるもののひとつが、知育に効果的なおもちゃはなにか?ということ。
我が家でも、おもちゃ選びに多くの時間を割いてきました。
しかし、結局子どもがハマるかどうかが大事で、それは実際に遊ばせてみないと分からないことも多いです。
そのため、その都度おもちゃを買っていくと出費がかさむだけでなく家におもちゃが溢れることに…
そんな時にオススメしたいのがおもちゃのサブスクです!
子どもの月齢に合わせて最適な知育玩具を毎月 or 隔月などで届けてくれるので、おもちゃ選びに悩む時間を子どもの別のことに使えます。
以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方は是非チェックしてみてください。
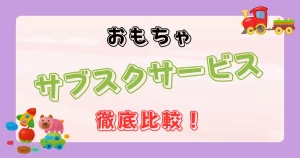
中でも、日本サブスクビジネス大賞2024を受賞したCha Cha Cha(チャチャチャ)は、初月1円から始められるのでまず試してみたいという方にオススメ!
他社で扱っていないキャラクターおもちゃも扱っているので、子どもの好みを確認しやすくてよいです。
\初月1円からスタートできる/
※おもちゃの破損や部品の紛失も原則無料です
※一つひとつ手洗いしていて衛生面も安心です