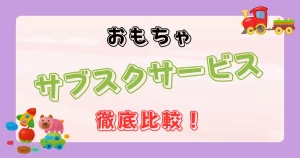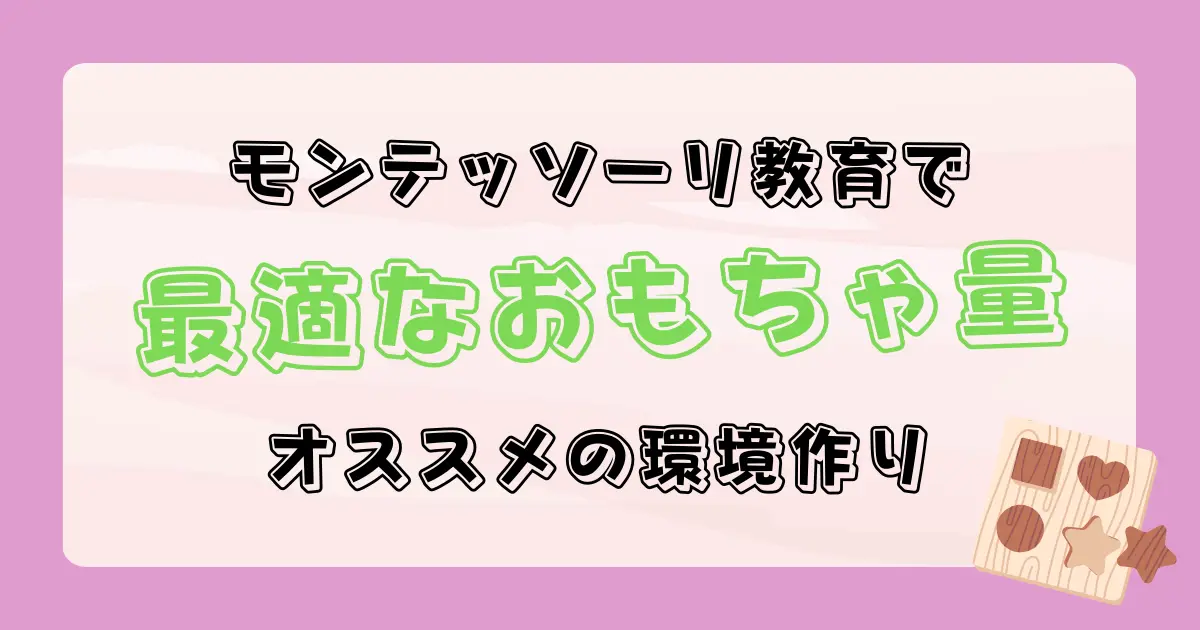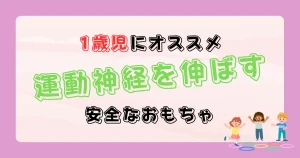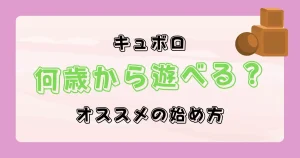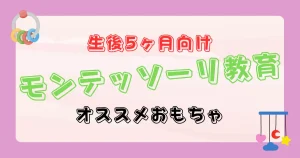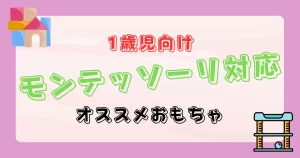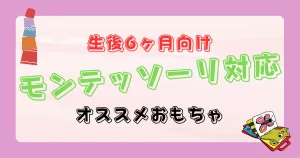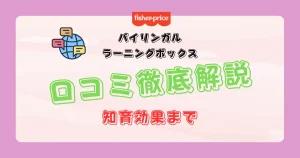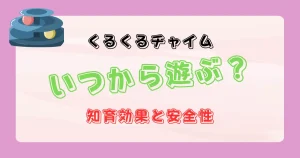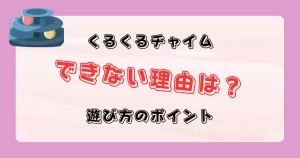- 「子どものおもちゃ、気づけば部屋にあふれてる…どうしよう?」
- 「モンテッソーリ教育がいいって聞くけど、おもちゃの量はどうすればいいの?」
- 「おもちゃが多すぎると良くないって本当?減らしたいけど、子どもが手放してくれない…」
- 「毎日のおもちゃの片付け、正直もう限界!」
子育て中のパパママなら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。
僕も5歳と2歳の息子を育てるパパとして、日に日に増えるおもちゃの量と、それに伴う片付けの大変さには本当に頭を悩ませています。
特に我が家の場合、おもちゃを全部集めると2~3畳分くらいになってしまい、「これはさすがに多いな…」と感じています。(こどもちゃれんじの教材が約3割、車・電車・BRIOなどの乗り物系が合わせて5割、残りがブロックなどです…)
この記事では、モンテッソーリ教育の考え方を元に、「子どもが伸びる」おもちゃの適正量や環境づくりについて、具体的なヒントや実践方法を解説します。
おもちゃを与えすぎることの影響から、具体的な減らし方、収納のコツ、そして量を減らせなくてもできる工夫まで、僕自身の経験も交えながら幅広くカバーしていますよ。
- モンテッソーリ教育におけるおもちゃの「量」の考え方
- おもちゃを与えすぎることによる具体的な影響
- 家庭でできるおもちゃの適正量の見極め方
- モンテッソーリ流のおもちゃ選びと環境づくりのポイント
- おもちゃの減らし方・整理術(減らせなくてもできる工夫)
- 子どもが自分で片付けたくなる収納のコツと声かけ
- おもちゃを増やさないための賢い付き合い方
この記事を最後まで読めば、おもちゃの量に関する漠然とした不安が解消され、お子さんの成長をより効果的にサポートするための具体的なアクションプランが見えてくるはずです。
理想的な環境を整えて、子どもの持つ無限の可能性を引き出してあげましょう。
もし、日々のおもちゃ選びや質の高い遊びの提供に悩んでいるなら、専門家が選んだ知育玩具が定期的に届くおもちゃのサブスクを利用してみるのも、忙しいパパママにとって賢い選択肢のひとつですよ。
トイサブは、おもちゃのサブスクサービスで知名度トップクラス!
生後1ヶ月から利用でき、月齢に合わせた知育に最適なおもちゃが届きます。
そのほか、トイサブを利用することで以下のようなメリットがあります。
- 返却期限や延滞料金なし
- おもちゃが壊れても、基本的に弁償は不要
- 気に入った場合はお得に買い取ることも可能
初月は約2,000円OFFの1,990円~使用できるので、まずは利用してみるとよいでしょう。
>2ヶ月990円で利用できる妊娠中から生後1.5か月までの方はこちら
おもちゃのサブスクレンタルサービス12つを徹底比較した以下の記事も、合わせて参考にしてみてください。
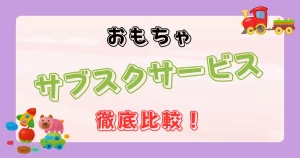
モンテッソーリ教育におけるおもちゃの「量」の考え方
モンテッソーリ教育と聞くと、特別な教具を思い浮かべるかもしれませんが、実は「おもちゃの量」にも独特の考え方があります。
なぜ量が重要視されるのか、その背景にある教育理念から見ていきましょう。
モンテッソーリでおもちゃの「量」が重視される理由
モンテッソーリ教育では、子どもの集中力と自己選択能力を育むために、おもちゃの量が重要視されます。
なぜなら、おもちゃが多すぎると子どもの注意は散漫になりがちで、ひとつのおもちゃにじっくり向き合う前に次へと目移りしてしまう可能性があるからです。
これは深い学びや満足感を得る機会を妨げます。
逆に、適切に厳選された量のおもちゃは、子どもが「自分で選ぶ」練習を促し、自分の興味に基づいて主体的に活動を選び取る経験は、自己肯定感や自立心を育む上で非常に重要になります。
実際に、量が管理された環境では、子どもはより主体的に活動に関わりやすくなります。
具体的に、量が重視されることで期待される効果には、以下のようなものがあります。
- 集中力の育成: 選択肢が絞られることで、ひとつの活動に深く没頭しやすくなる。
- 自己選択能力の向上: 自分で考え、決定する経験を積むことができる。
- 満足感と達成感: ひとつの活動をやり遂げることで、自信につながる。
- 物の価値の理解: 限られたものを大切に扱う気持ちが育まれる。
このように、おもちゃの量を適切に保つことは、子どもの内面的な成長を支えるための大切な配慮なのです。
モンテッソーリ教育の基本的な考え方は「整えられた環境」
モンテッソーリ教育の根幹には、「整えられた環境 (Prepared Environment)」という重要な考え方があります。
これは、単に整理整頓されているだけでなく、子どもの発達段階に合わせて、知的好奇心や自立心を自然に引き出せるように物理的・心理的に配慮された空間を指します。
おもちゃの量や配置も、この「整えられた環境」を構成する大切な要素のひとつです。
環境が整っていると、子どもは「自分でやってみたい」という内なる衝動に従って、自発的に活動(モンテッソーリ教育では「お仕事」と呼ぶこともあります)に取り組み始めやすくなります。
整えられた環境がもたらすメリットには、以下のようなものが挙げられます。
- 子どもが自分で活動を選びやすい
- 集中して活動に取り組める
- 自立心や秩序感が育まれる
- 安全で、精神的にも落ち着ける空間
大人が細かく指示しなくても、子ども自身が環境から学び、成長していく力を最大限に引き出すために、モンテッソーリ教育では環境設定、特におもちゃの量や提示方法が慎重に考えられているのです。
おもちゃ(教具)の役割は子どもの自立と集中を促すツール
モンテッソーリ教育で使われるおもちゃは、単なる遊び道具ではなく「教具 (Materials)」と呼ばれ、子どもの発達を助ける「ツール」としての明確な役割を持っています。
それぞれの教具には、特定の感覚を刺激したり、特定のスキル(例えば、つまむ、注ぐ、分類するなど)を練習したりといった、明確な「目的」がひとつだけ含まれている「目的の孤立化」という特徴があります。
これにより、子どもは何を学ぶべきかが明確になり、活動に集中しやすくなります。
さらに、教具には間違いを自分で発見できる「誤りの訂正」機能が備わっていることが多く、大人の介入なしに試行錯誤しながら自己成長できる仕組みになっています。
モンテッソーリ教具の主な特徴と、それが子どもの学びにどう影響するかをまとめると、以下のようになります。
| モンテッソーリ教具の特徴 | 子どもの学びへの効果 |
|---|---|
| 目的の孤立化 | ひとつの課題に集中しやすくなる |
| 誤りの訂正機能 | 自分で間違いに気づき、修正する力が育つ |
| 感覚への訴求 | 五感を通して世界を理解する助けとなる |
| 活動への誘い | 子どもの知的好奇心を引き出し、自発的な活動を促す |
このように、教具は子どもの自立した学びと、深い集中状態(マリア・モンテッソーリはこれを「正常化」と呼びました)を引き出すための、非常に重要な役割を担っているのです。
量よりも「質」と「選び方」が重要
モンテッソーリ教育においては、おもちゃの量を管理することと同様に、あるいはそれ以上に、おもちゃの「質」と「選び方」が極めて重要視されます。
たくさんのおもちゃをただ与えるのではなく、子どもの発達段階や興味関心にぴったりと合った、質の高い教具や玩具を注意深く「厳選」することが求められます。
なぜなら、質の高いおもちゃは子どもの五感を豊かに刺激し、創造性を引き出し、深い学びへと導く力を持っているからです。
質の高いおもちゃを選ぶ際には、例えば以下のような点を意識するとよいでしょう。
- 発達段階への適合: 子どもの「今」できること、興味があることに合っているか。
- 素材の質: 自然素材など、本物の感触を体験できるか。
- 目的の明確さ: 子どもが何をするためのものか理解しやすいか。
- 多様な関わり方: 創造性を刺激し、発展的な遊びが可能か。
- 安全性: 子どもが安全に扱えるか(STマークなども参考に)。
子どもの発達段階や「敏感期」(特定のことに対して強い感受性を示す時期)を注意深く観察し、最適な質のおもちゃを提供することで、子どもの学びの効果は最大限に高まるのです。
子どもが自分で「選べる」量、「管理できる」量が基本
モンテッソーリ教育におけるおもちゃの「適量」の基本は、子ども自身が主体的に関われる量、具体的には「自分で選べる量」であり「自分で管理できる量」であるということです。
「〇個まで」といった厳密な数ではなく、子どもの能力や主体性を基準に考えます。
選択肢が多すぎると選ぶこと自体が負担になり、また、管理できないほどの量があると、片付けが困難になり環境の秩序が保てません。
ご家庭のおもちゃが適量かどうかを見極めるには、以下のような点に注意してみましょう。
- 選択肢が多すぎないか?: 子どもが圧倒されたり、選ぶのに時間がかかりすぎたりしていないか。
- 自分で片付けられるか?: 大人の手助けなしで、元の場所に戻せる量・仕組みになっているか。
- すべてのおもちゃが見渡せるか?: 奥にしまい込まれて、存在を忘れられているおもちゃはないか。
子どもが自分の力で環境をコントロールできる感覚を持つことが、自立心や責任感を育む上で大切なのです。
モンテッソーリ的におもちゃを与えすぎるとどうなる?考えられる影響
「おもちゃはたくさんあった方が、子どもの刺激になるのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、モンテッソーリ教育の視点から見ると、おもちゃの与えすぎは子どもの成長にいくつかのマイナスの影響を与える可能性があると考えられています。
集中力が散漫になる可能性
おもちゃが多すぎる環境は、子どもの集中力を散漫にさせてしまう可能性があります。
なぜなら、魅力的なものがたくさんあると、子どもの注意はあちこちに移りやすくなります。
ひとつの遊びにじっくりと取り組む前に、次の新しい刺激へと意識が向かってしまうのです。
例えば、我が家の5歳の長男は興味の対象が次々に変わり、遊びが長続きしないことがあります。
モンテッソーリ教育で重視される「集中現象」(深い集中状態)は、自己肯定感や学びの深化にとって非常に重要ですが、おもちゃが多いとこの機会が減る可能性があります。
お子さんに以下のようなサインが見られたら、おもちゃが多すぎることを示唆しているかもしれません。
- 遊びが長続きしない
- すぐに「飽きた」という
- おもちゃを次々に出しては散らかす
- 呼びかけに気づかないほど没頭する経験が少ない
選択肢を適切に絞ることが、子どもがひとつの活動に深く没頭するための助けとなるのです。
一つのおもちゃと深く向き合えなくなる
おもちゃを与えすぎると、子どもはひとつひとつのおもちゃと深く向き合う機会を失いがちになります。
たくさん選択肢があると、それぞれのおもちゃの持つ面白さや可能性を十分に探求する前に、次のものへと移ってしまう傾向があるためです。
遊びが表面的になり、深化しにくくなる可能性があります。
例えば、積み木ひとつをとっても、最初は積むだけかもしれませんが、次第に形を作ったり、何かに見立てたりと、遊び方はどんどん発展します。
しかし、他にも魅力的なおもちゃがたくさんあると、このような遊びの深化が起こりにくくなるかもしれません。
与えすぎによる影響として、具体的には以下のような点が考えられます。
- 遊び方が表面的になりがち
- 工夫したり、応用したりする機会が減る
- おもちゃの「本来の目的」に気づきにくい
- 探求心や粘り強さが育ちにくい
ひとつの物とじっくり向き合い試行錯誤する経験は、創造性や問題解決能力を育む上で欠かせません。
量が限られているからこそ、子どもは今あるものでどう遊ぶかを工夫するのです。
物を大切にする気持ちが育ちにくい
おもちゃが豊富にありすぎると、子どもが物を大切にする気持ちを育む機会が減ってしまう可能性があります。
なぜなら、おもちゃが簡単に手に入り、次から次へと新しいものが与えられる環境では、ひとつひとつのおもちゃに対するありがたみを感じにくくなることがあるからです。
「壊れても、飽きても、次がある」という感覚が当たり前になると、物を丁寧に扱ったり、長く使ったりする態度が育ちにくくなるかもしれません。
例えば、次のような行動が見られる場合は、物を大切にする気持ちが育ちにくくなっているサインかもしれません。
- おもちゃを乱暴に扱いがちになる
- 壊れても平気な様子を見せる
- おもちゃへの愛着が薄い
- 「もったいない」という感覚が育ちにくい
モンテッソーリ教育では、美しく整えられた環境の中で、限られた質の高い教具を丁寧に扱うことを学びます。
この経験を通して、子どもは物への敬意や感謝の気持ちを自然と身につけていきます。
おもちゃの量を絞ることは、情操教育の観点からも、物を大切にする心を育むことにつながるのです。
自分で選ぶ力が育ちにくい
意外かもしれませんが、おもちゃが多すぎると、かえって子どもが自分で選ぶ力が育ちにくくなることがあります。
なぜなら、選択肢が多すぎると、どれも魅力的に見えてしまい、どれから手をつけていいか分からず、「選べない」状態に陥ることがあるためです。
このような経験が続くと、自分で判断・決定する自信を失い、主体性が育まれにくくなる可能性があります。
モンテッソーリ教育では、子どもが自分の意志で選択し、その結果を体験することを非常に重視します。
限られた選択肢の中から「これにする!」と決める経験は、自己肯定感を高める大切なステップです。
選ぶ力が育ちにくい場合、以下のようなサインが見られることがあります。
- 決断に時間がかかるようになる
- 他の子が遊んでいるものを欲しがる
- 「なんでもいい」と言うことが増える
- 自分の好みがはっきりしない
おもちゃの量を適切に管理することは、子どもの主体性や「選ぶ力」を効果的に育むための環境設定でもあるといえるでしょう。
片付けが困難になり、環境が乱れる
おもちゃが多すぎると、子どもだけでなく親にとっても片付けが非常に困難になり、結果的に環境が乱れやすくなります。
子ども自身で管理できる量を超えると、どこに何をしまうか分からなくなったり、「全部片付けるのは大変だ」と感じて意欲を失ったりするためです。
物理的に収納スペースが足りなくなることも、環境が乱れる大きな原因です。
我が家の子どもたちも「基本的に片付けは嫌い」で、特に2歳の次男はほとんど自分から片付けようとはしません。
これは多くの家庭で聞かれる悩みですが、おもちゃの量が多すぎることが、その一因となっている可能性も考えられます。
片付けがうまくいかない背景に量の問題があるかもしれないサインとして、以下の点をチェックしてみましょう。
- おもちゃ箱や棚からあふれている
- 床におもちゃが散乱しているのが常態化している
- 子どもが自分で片付けられない、または片付けようとしない
- 探し物が見つからないことが多い
- 親が片付けに費やす時間とストレスが大きい
散らかった環境は見た目だけでなく、子どもの集中力や精神的な落ち着きにも影響を与える可能性があります。
モンテッソーリ教育の「整えられた環境」は、物理的な秩序が心の秩序にもつながるという考えに基づいています。
そのため、子どもが自分で維持できる量におもちゃを管理することは、片付けの習慣化だけでなく、落ち着いて活動できる環境を作るための第一歩となります。
創造性や工夫する力が低下する可能性ある
完成度の高い機能的なおもちゃが多すぎると、子どもの創造性や遊びを工夫する力が低下してしまう可能性があります。
なぜなら、ボタンを押せば決まった反応が返ってくるような、遊び方が限定されたおもちゃに囲まれていると、子どもは受け身の遊びに慣れてしまい、自分から何かを生み出したり、遊び方を工夫したりする機会が減ってしまうためです。
例えば、ただの木の棒でも、想像力を働かせれば様々なものに見立てて遊べます。
しかし、常に「遊び方が決まっている」おもちゃばかりだと、そのような自由な発想や創造性を発揮する場面が少なくなるかもしれません。
創造性が低下しているサインとして、以下のような点が考えられます。
- 決まった遊び方しかしない
- おもちゃ以外のもの(段ボールなど)で遊ぼうとしない
- 「遊び方がわからない」とすぐに聞いてくる
- 自由な発想の遊び(ごっこ遊びなど)が広がらない
おもちゃの数が限られていれば、子どもは自然と今あるものを活用して新しい遊びを生み出そうとします。
この「ないから工夫する」経験が、子どもの創造力や問題解決能力を豊かに育むのです。
親子の関わりが減る可能性がある
少し意外かもしれませんが、おもちゃが多すぎることが、結果的に親子間のコミュニケーションの質に影響を与える可能性も指摘されています。
なぜなら、おもちゃがたくさんあれば子どもは一人で遊び続けられるため、親が関わる必要性が減る、あるいは、どのおもちゃでどう関わればよいか親も迷ってしまう、といったことが考えられるからです。
こども家庭庁の委託調査研究報告書の中では、おもちゃの数が少ない方が、特に乳幼児期において、親と子が同じものに注意を向け、感情を共有する「共同注意」の質が高まる可能性を示唆する研究に言及されています。(引用元:こども家庭庁 成育基本方針に基づいた妊娠期からの児童虐待予防に資する研究)
ただし、この報告書では、これらの知見はまだ限定的であり、解釈には注意が必要とも述べられています。
とはいえ、物が少ない環境がもたらすかもしれない、親子関係へのプラスの影響には以下のようなものがあります。
- 子どもが親に遊びへの参加を求めやすくなる
- 一緒に遊びを工夫したり、発展させたりする機会が増える
- おもちゃを介した会話ややり取りが生まれやすくなる
- 子どもの興味や成長をより近くで感じられる
結果的に、物が少ない環境が親子のより豊かなコミュニケーションを促すきっかけになることもあるのかもしれません。
我が家のおもちゃは多い?少ない?適正量を見極めるヒント
「うちのおもちゃ、やっぱり多すぎるのかな…?」と感じ始めた方もいるかもしれません。
でも、具体的にどれくらいが「適量」なのか、判断するのは難しいですよね。
ここでは、ご家庭のおもちゃの量を見極めるためのヒントをいくつかご紹介します。
子どもの年齢別のおもちゃとの関わり方の変化
おもちゃの適正量を考える上で、まず子どもの年齢による発達段階の違いを理解することが大切です。
なぜなら、年齢によって興味の対象や遊び方、必要とされる刺激は大きく異なるからです。
すべての年齢に共通の「適正量」というものは存在しません。
例えば、我が家の5歳と2歳の息子も、興味の対象が全く違います。
5歳の長男はごっこ遊びや少し複雑なルールの遊びに夢中になるかもしれませんが、2歳の次男は乗り物のおもちゃで繰り返し遊んだり、指先を使う遊びに集中したりする時期かもしれません。
年齢ごとの一般的な発達の特徴を知っておくと、おもちゃ選びや量の判断に役立ちます。
0歳~1歳頃:感覚を刺激する厳選された数点
この時期の赤ちゃんは、五感を通して世界を学びます。
舐めても安全な素材で、握る、振る、叩くといった単純な動作で音や感触を楽しめるおもちゃが中心になります。
視覚、聴覚、触覚などを優しく刺激する、厳選された数点があれば十分でしょう。
この時期に適したおもちゃの例としては、以下のようなものが挙げられます。
- ラトル(ガラガラ): 振ると音が鳴り、握る練習にもなる。
- オーボール: 網目状で掴みやすく、口に入れても安全な素材が多い。
- 布絵本: 様々な素材の感触や、めくる楽しさを体験できる。
- 歯固め: 歯の生え始めのむずがゆさを和らげ、噛む練習にも。
色々なものを口に入れて確かめる時期でもあるため、誤飲の危険がない大きさや形状であること、安全な素材であること(STマークなども参考に)が特に重要です。
1歳~2歳頃:指先を使う、動きを伴う遊びが増える時期
歩き始め、手指の動きも器用になってくるこの時期は、行動範囲が広がり、様々なものに興味を示します。
積む、崩す、入れる、出す、押す、引くといった動作を楽しむおもちゃや、指先を使う遊びが適しています。
例えば、我が家の2歳の次男も車や電車のおもちゃに夢中で、自分の好きなものへのこだわりが出始める時期でもあります。
簡単なパズルや型はめなども、集中力や思考力を養うのによいでしょう。
この時期におすすめのおもちゃには、次のようなものがあります。
- 積み木: 積む、崩す、並べるなど多様な遊び方ができる。
- 型はめ・パズル: 形や大きさの認識、指先の器用さを育む。
- 押し車・引き車: 歩行の練習や、物を運ぶ楽しさを体験できる。
- 車や電車のおもちゃ: 走らせたり、並べたり、ごっこ遊びのきっかけにも。
- 簡単な楽器(タンバリンなど): 音を出す楽しさを体験できる。
3歳~:ごっこ遊び、ルールのある遊び、より複雑な操作へ
言葉の発達とともに、想像力が豊かになり、ごっこ遊びが盛んになる時期です。
おままごとセットや人形、乗り物のおもちゃなどが活躍します。
また、簡単なルールのあるゲームや、少し複雑な組み立てが必要なブロック、パズルなどにも挑戦できるようになります。
我が家の5歳の長男も、こどもちゃれんじの教材(特にしまじろう)に夢中で、キャラクターやストーリーへの興味も高まっています。
手先もさらに器用になるため、ハサミを使ったり、折り紙を折ったりする活動も楽しめます。
これらの年齢別の特徴とおもちゃの例をまとめると、以下のようになります。
| 年齢 | 主な遊びの特徴 | 適したおもちゃの例 |
|---|---|---|
| 0歳~1歳頃 | 五感を使う、単純な動作 | ラトル、オーボール、布絵本、歯固め |
| 1歳~2歳頃 | 手指を使う、動きを伴う、模倣 | 積み木、型はめ、押し車、簡単な楽器 |
| 3歳~ | ごっこ遊び、ルール遊び、想像力、複雑な操作 | おままごと、ブロック、パズル、ボードゲーム、折り紙、粘土 |
このように、お子さんの発達段階に合わせて、おもちゃの種類や量を見直していくことが重要です。
子どもの興味や集中度合いを観察する
年齢別の目安以上に重要なのが、目の前のお子さんの興味や集中度合いを日頃からよく観察することです。
なぜなら、子どもの個性は様々であり、一般的な発達段階に当てはまらないことも多いからです。
その子自身の「今」の状態を見ることが、最適なおもちゃ環境を知る一番の手がかりとなります。
どんなおもちゃに興味を示し、どれくらいの時間集中して遊んでいるでしょうか。
我が家の息子たちも、上の子は目移りしやすいですが、下の子はひとつのことに没頭すると周りの声が聞こえなくなるタイプです。
また、「今日はしまじろう!」「明日は車!」というように、気分によってその日に遊ぶものが変わるのも日常茶飯事です。
観察する際のポイントは以下の通りです。
- 今、何に夢中になっているか?: 熱心に遊んでいるおもちゃは何か。
- どれくらい集中しているか?: ひとつの遊びがどれくらい続くか。周りの声が聞こえないほど没頭することもあるか。
- 遊び方は発展しているか?: 同じおもちゃで、以前とは違う遊び方をしているか。工夫が見られるか。
- 全く遊んでいないおもちゃはないか?: 長期間手付かずのおもちゃはないか。
- 「遊びたいものがない」と言っていないか?: おもちゃはたくさんあるのに、満たされていない様子はないか。
もし、多くのおもちゃがほとんど遊ばれることなく放置されていたり、どのおもちゃでもすぐに飽きてしまったりする様子が見られるなら、それはおもちゃが多すぎる、あるいは今の興味に合っていないサインかもしれません。
逆に、数が少なくても、今あるおもちゃで様々な遊びを展開し、生き生きと遊んでいるのであれば、それがその子にとっての適量といえるでしょう。
子どもが自分で片付けられる量か?
おもちゃの適正量を見極めるもうひとつの重要なヒントは、「子どもが自分で片付けられる量か?」という視点です。
なぜなら、モンテッソーリ教育では、子どもが自分の使ったものを自分で管理できることを大切にするからです。
自分で片付けられないほどの量は、子どもの自立を妨げ、環境の秩序を乱す原因となります。
遊び終わった後、お子さんは自分でおもちゃを元の場所に戻せているでしょうか。
もし、いつもおもちゃが散らかりっぱなしで、親が片付けるのが当たり前になっているなら、それは子どもにとって管理できる量を超えている可能性が高いです。
もちろん、年齢や性格によって片付けができるレベルは異なりますし、「片付け嫌い」というお子さんも多いでしょう。
しかし、おもちゃの量が膨大で、どこに何をしまうのか分かりにくい状態では、片付けのハードルはさらに上がってしまいます。
片付けられない原因が量にあるかもしれない場合、以下の点をチェックしてみましょう。
- おもちゃの定位置が決まっていない、または曖昧
- 収納スペースに対しておもちゃの量が明らかに多い
- 子どもが自分で出し入れするには重すぎる、または高すぎる場所にある
- 片付けのルールが複雑すぎる、または一貫していない
- 親が先回りして片付けてしまうことが多い
子どもが「これなら自分でできそう」と思えるくらいの量に絞り、分かりやすい収納方法(後述)を組み合わせることが、片付けの習慣化につながります。
全てのおもちゃで定期的に遊んでいるか?
家にあるすべてのおもちゃが、定期的に子どもの遊びに登場しているかを確認することも、適正量を見極める上で有効です。
なぜなら、長期間全く遊ばれていないおもちゃが多い場合、それは量が多すぎるか、あるいはそのおもちゃがもはや子どもの興味や発達段階に合わなくなっているサインと考えられるからです。
家にあるおもちゃを思い浮かべてみてください。
ここ数週間、あるいは数ヶ月の間、一度も手に取られていないおもちゃはありませんか?子ども部屋の隅や、おもちゃ箱の底で忘れ去られているような存在です。
もちろん、一時的にブームが去っているだけで、また遊び始めることもあります。
しかし、定期的に遊ばれていないおもちゃは、現在の「一軍」からは外れている可能性が高いでしょう。
まずはおもちゃを以下のように分類してみることから始めてみましょう。
- 「一軍」のおもちゃはどれか?: 毎日~週に数回は遊んでいるおもちゃ。
- 「二軍」のおもちゃはどれか?: たまに思い出したように遊ぶおもちゃ。
- 「控え」のおもちゃはどれか?: ここ最近、全く遊んでいないおもちゃ。
- 「戦力外」のおもちゃはどれか?: 壊れている、部品がない、年齢的に明らかに合わないおもちゃ。
このように、遊ばれていないおもちゃを見直すことが、適正量に近づくための具体的な第一歩となります。
モンテッソーリ教育で推奨される目安と、実体験による意見
おもちゃの適正量について、モンテッソーリ教育の現場での目安と、実際の家庭での感覚には少し違いがあるかもしれません。
なぜなら、教育現場では体系的な活動のためにある程度の種類が必要とされる一方、家庭ではより生活に密着した、柔軟な考え方が求められるためです。
モンテッソーリ教育の現場では、子どもが自分で選んで活動できるよう、棚に提示される教具(おもちゃ)の数は、一般的に8~10種類程度に絞られていることが多いようです。
これは、子どもが全体を見渡せて、自分で選びやすく、集中して取り組みやすい数と考えられています。
一方で、僕自身の経験からは、「全体量よりも、一度に目に入るおもちゃの種類が3~5種類くらいが良いのでは」と感じています。
これは、モンテッソーリの厳密な定義とは少し異なりますが、「選択肢を絞ることで集中しやすくなる」という点では共通する考え方かもしれません。
参考として、これらの考え方を比較してみましょう。
| 考え方 | 目安 | ポイント |
|---|---|---|
| モンテッソーリ教育の現場 | 棚に提示するのは8~10種類程度 | 子どもが全体を見渡し、自分で選べる数 |
| 僕(パパ)の実感 | 一度に目に入る種類が3~5種類程度 | 選択肢が多すぎず、集中しやすい数 |
どちらの考え方も、子どもの主体的な選択と集中を促すという目的は共通しています。
数字にこだわりすぎず、お子さんの様子を見ながら、ご家庭に合ったバランスを見つけることが大切です。
「多い」と感じていてもOK!量を減らすことだけが正解ではない
おもちゃの量が「多い」と感じていても、必ずしもすぐに減らす必要はなく、量を減らすことだけが解決策ではありません。
なぜなら、お子さん自身がおもちゃへの愛着が強く、手放すことを嫌がる場合、無理に減らすのは難しいですし、親子関係に影響が出る可能性もあります。
また、モンテッソーリ教育の目的は、量を減らすこと自体ではなく、子どもの発達を促す「整えられた環境」を作ることにあるからです。
僕自身も、モンテッソーリ教育の考え方を知った時にはすでに多くのおもちゃがあり、「減らそうにも子どものOKが出ないので、なかなか減らせない…」という現実に直面しています。
これは多くの家庭で起こりうることだと思います。
たとえおもちゃの絶対量が減らせなくても、提示の仕方(ローテーション)や収納方法を工夫することで、子どもが遊びに集中しやすい環境に近づけることは可能です。
「多い」と感じていても大丈夫なポイントをまとめました。
- 量を減らすことにこだわりすぎない。
- 子どもの気持ちも尊重する。
- 収納や提示方法の工夫で環境は変えられる。
- できることから、少しずつ試してみる。
「減らせない自分はダメだ」と罪悪感を感じる必要はありません。
現状を受け入れた上で、環境を整えるための他のアプローチを試していくことが大切です。
モンテッソーリ流!おもちゃの選び方と環境づくりのポイント
おもちゃの量だけでなく、どんなおもちゃを選び、どのように環境を整えるかも、子どもの発達を促す上で非常に重要です。
ここでは、モンテッソーリ教育の考え方に基づいた、おもちゃ選びと環境づくりの具体的なポイントをご紹介します。
子どもの発達段階に合っているか
おもちゃ選びの最も基本的な原則は、子どもの「今」の発達段階や興味に合っているかどうかです。
なぜなら、簡単すぎるおもちゃはすぐに飽きてしまい、逆に難しすぎるおもちゃは挑戦する意欲をくじき、「自分にはできない」という無力感を抱かせてしまう可能性があるからです。
適切な挑戦が子どもの成長を促します。
そのためには、日頃から子どもの遊びの様子をよく観察し、何に興味を持っているのか、どんなことができるようになったのかを把握しておく必要があります。
手指の使い方はどうか、言葉の発達はどうか、どんな動きを楽しんでいるかなど、子どもの発達段階を見極め、それに合ったおもちゃを提供しましょう。
発達段階に合ったおもちゃを選ぶ際のポイントは以下の通りです。
- 観察が第一: 子どもが今、何に興味を持ち、何ができるかを見る。
- 「敏感期」を意識する: 特定の能力を伸ばしたい時期に合ったものを選ぶ。
- 少し挑戦できるレベル: 簡単すぎず、難しすぎないものを選ぶ。
- 段階的にステップアップ: できるようになったら、少し難易度を上げたものを用意する。
子どもが「ちょっと頑張ればできそう!」と感じられるレベルのおもちゃを選ぶことが、意欲と成長を引き出す鍵となります。
五感を刺激し、本物の素材に触れられるか(木製など)
モンテッソーリ教育では、五感を通して世界を学ぶことを重視し、木や布、金属など多様な「本物の」素材に触れる経験を大切にします。
なぜなら、特に幼児期は感覚が非常に敏感であり、様々な質感、重さ、温度などを感じる経験が、脳の発達や物の性質に対する理解を深める上で重要だからです。
プラスチック製のおもちゃも手軽ですが、できれば木製の積み木や、金属製のスプーン、陶器のカップ(割れる経験も学びと捉えます)など、感覚を豊かに刺激する素材のおもちゃを取り入れたいものです。
例えば、木のおもちゃは、ひとつひとつ木目や重さが異なり、温かみのある手触りがあります。
様々な素材が育む感覚を以下の表にまとめました。
| 素材 | 特徴 | 育まれる感覚 |
|---|---|---|
| 木 | 温かみ、木目、重さ、香り | 触覚、視覚、嗅覚 |
| 布 | 柔らかさ、肌触りの違い(綿、麻など) | 触覚 |
| 金属 | 冷たさ、重さ、光沢、音 | 触覚、温度感覚、視覚、聴覚 |
| 陶器 | 重さ、滑らかさ、冷たさ、(割れる) | 触覚、温度感覚、(扱い方を学ぶ) |
このような「本物」の素材に触れる実体験を通して、子どもは世界に対する認識をより豊かで確かなものにしていくのです。
「お仕事」につながる目的のある活動ができるか
モンテッソーリの教具は、子どもが達成感を得られるように、明確な目的を持った活動(お仕事)ができるようにデザインされています。
なぜなら、日常生活で行う動作(ボタンかけ、注ぐなど)を練習することで、自立心を育み、具体的なスキルを習得できるためです。
目的がはっきりしていることで、子どもは集中して取り組みやすくなります。
市販のおもちゃを選ぶ際にも、このような「目的のある活動」ができるかどうか、という視点を持つとよいでしょう。
単に受動的に遊ぶだけでなく、子どもが何か具体的なスキルを練習したり、目標を達成したりできるようなおもちゃは、子どもの満足感や自己肯定感を高める助けになります。
目的のある活動につながるおもちゃの例をいくつかご紹介します。
- 指先の器用さを養う活動: ビーズ通し、シール貼り、粘土、ひも通しなど。
- 日常生活の模倣: おままごとセット(切る、盛り付ける)、着せ替え人形、簡単な工具セットなど。
- 感覚を洗練させる活動: 様々な素材のマッチング、音の聞き分け、重さ比べなど。
- 数や文字に親しむ活動: 数字や文字のパズル、そろばん、マグネットボードなど。
単なる暇つぶしではない、子どもの「できた!」という達成感を育む活動につながるおもちゃを選ぶことが大切です。
シンプルで、多様な遊び方ができるか
機能が限定されすぎず、シンプルで、子どもの想像力次第で多様な遊び方ができるおもちゃは、長く使え、創造性を豊かに育みます。
なぜなら、遊び方が固定されていないおもちゃは、子どもが自由に発想し、試行錯誤する余地を与えてくれるからです。
この自由な関わりの中で、創造性や問題解決能力が育まれます。
代表的なのが積み木やブロックです。
これらは、積んだり並べたりするだけでなく、家や乗り物に見立てたり、ごっこ遊びの道具になったりと、子どもの成長に合わせて遊び方が無限に広がります。
我が家にもあるBRIO(木製レール)やブロックは、まさに多様な遊び方ができるおもちゃの例といえるでしょう。
他にも、多様な遊び方ができるシンプルなおもちゃには、以下のようなものがあります。
- 積み木・ブロック: 構成遊び、見立て遊び、ごっこ遊びなど。
- 粘土・砂: 形を作る、感触を楽しむ、道具を使うなど。
- シンプルな人形や動物のフィギュア: ごっこ遊び、ストーリー作りなど。
- 布(スカーフなど): マント、おくるみ、仕切りなど、見立て遊びに活躍。
おもちゃを選ぶ際には、「決まった遊び方」だけでなく、「どんな風に発展させられるか?」という創造性を刺激する視点も持ってみるとよいでしょう。
美しく、子どもが手に取りたくなるデザインか
モンテッソーリ教育では、環境の美しさも重視されており、おもちゃ(教具)も子どもが思わず手に取りたくなるような、シンプルで美しいデザインが推奨されます。
なぜなら、美しい環境や道具は、子どもの美的感覚を養うだけでなく、物を丁寧に扱おうとする気持ちや、活動への意欲を引き出すと考えられているからです。
落ち着いた環境は、子どもの集中も助けます。
色合いが落ち着いていたり、素材の良さが活かされていたりするものがよいでしょう。
ごちゃごちゃとキャラクターが描かれたものよりも、シンプルで洗練されたデザインのおもちゃを選ぶことで、子どもは落ち着いた気持ちで活動に取り組むことができます。
美しいデザインの要素としては、以下が挙げられます。
- シンプルなデザイン: 余計な装飾が少なく、目的が分かりやすい。
- 落ち着いた色合い: 原色ばかりでなく、自然な色合いやパステルカラーなども取り入れる。
- 素材の美しさ: 木目や布の質感など、素材そのものの良さが感じられる。
- 手触りのよさ: 子どもが触れて心地よいと感じるもの。
収納する際も、美しくディスプレイすることを意識すると、子どもはおもちゃを大切にし、片付けへの意欲も高まるかもしれません。
安全性(STマークなども参考に)
おもちゃ選びにおいて、安全性は何よりも優先されるべき最も重要な要素です。
なぜなら、どんなに教育的価値が高くても、子どもが安全に遊べなければ意味がありません。
事故を防ぎ、安心して遊べる環境を提供することが大前提となります。
特に小さいお子さん向けのおもちゃは、誤飲の危険がない大きさか、舐めても有害な物質が含まれていないか、尖った部分や壊れやすい部品がないかなどを厳しくチェックする必要があります。
安全性を確認するひとつの目安として、STマーク(玩具安全マーク)があります。
これは、一般社団法人 日本玩具協会が定める玩具安全基準に適合したおもちゃに付けられるマークで、機械的・物理的特性、可燃性、化学的安全性などが検査されています。(引用元:一般社団法人 日本玩具協会)
他にも、PSCマークやSGマークなど、製品の安全に関するマークがあるので、参考にするとよいでしょう。
安全チェックのポイントをまとめました。
- 対象年齢を確認する: 子どもの年齢に合っているか。
- 誤飲の危険はないか?: 小さな部品が取れやすくなっていないか。(トイレットペーパーの芯を通るものは要注意)
- 尖った部分はないか?: 角が丸く処理されているか。
- 有害な物質は含まれていないか?: 塗料などが安全なものか(STマークなどを参考に)。
- 耐久性はあるか?: 簡単に壊れたり、破損したりしないか。
安全基準マークの確認や、おもちゃ自体の状態をよく見て、子どもが安心して遊べるものを選びましょう。
実践!モンテッソーリ式おもちゃの減らし方・整理術
「よし、おもちゃを見直してみよう!」と思っても、どこから手をつけていいか迷いますよね。
ここでは、モンテッソーリ教育の考え方を取り入れた、具体的なおもちゃの減らし方・整理術を4つのステップでご紹介します。
ステップ1:まず現状を把握する(全部出してみる)
おもちゃ整理の最初のステップは、家にあるおもちゃを全て把握することです。
なぜなら、全体像が見えないまま部分的に整理しても根本的な解決にならず、効果的な判断ができないためです。
現状を正確に知ることが、見直しのスタートラインとなります。
子ども部屋だけでなく、リビングや他の場所に置いてあるものも含め、可能であれば一箇所に集めてみましょう。
「こんなにあったの!?」と驚くかもしれません。
我が家の場合、集めると2~3畳分にもなりました。
全てを出すことで、どれくらいの量があるのか、どんな種類のおもちゃが多いのか、壊れていたり部品がなかったりするものはないかなど、現状を客観的に把握できます。
現状把握には、以下のようなメリットがあります。
- おもちゃの総量を正確に把握できる。
- 種類ごとの偏り(例:乗り物が多いなど)がわかる。
- 壊れているものや、不要なものを見つけやすい。
- 「こんなにたくさんあったんだ」という気づきが、見直しのモチベーションになる。
この作業は少し大変ですが、効果的な整理を進めるための重要な第一歩です。
お子さんと一緒に「おもちゃパーティーだ!」などと楽しみながら行うのもよいかもしれません。
まずは家全体のおもちゃの量を「見える化」することから始めましょう。
ステップ2:子どもの様子を見ながら分類する
次に、集めたおもちゃを子どもの様子や発達段階に基づいて分類していきます。
なぜなら、機械的に「いる」「いらない」を分けるのではなく、子どもにとって今何が必要か、という視点で分類することが重要だからです。
大人の判断だけでなく、子どもの気持ちも尊重する姿勢が大切です。
ただし、子どもは全てを「いる!」という可能性も高いので、大人が主導権を持ちつつ、可能であれば一緒に相談しながら進めましょう。
分類の基準としては、以下のようなものが考えられます。
- 「一軍」(よく遊ぶ): 今、子どもが夢中になっていて、これからも遊びたいおもちゃ。
- 「二軍」(たまに遊ぶ): 時々思い出したように遊ぶが、一軍ほどではないおもちゃ。
- 「保管」(今は遊ばない): 発達段階的にまだ早い、またはブームが去ったが、今後また遊ぶ可能性があるおもちゃ。兄弟用にとっておくもの。
- 「手放す」(不要): 壊れている、部品がない、年齢的に完全に合わない、全く興味を示さないおもちゃ。
この分類作業を通して、今子どもにとって本当に必要なおもちゃを選び出すことができます。
ステップ3:「一時保管」も活用する
分類した結果、「二軍」や「保管」となったおもちゃは、すぐに手放さずに「一時保管」という選択肢を活用するのが有効です。
なぜなら、子どもが手放すことに抵抗がある場合、無理に捨てると物を大切にする気持ちを損ねたり、親への不信感につながったりする可能性があるためです。
段階的なアプローチが、親子ともにストレスなく整理を進めるコツです。
僕自身も「子どものOKが出ないので、なかなか減らせない…」という壁にぶつかっていますが、これは多くの家庭で起こりうることだと思います。
そこで、「今は少しお休みしようね」「また遊びたくなったら出そうね」と伝え、目につかない場所に一時的に保管しておくのです。
一時保管する際のポイントは以下の通りです。
- 目につかない場所に保管する: クローゼットの上段、押し入れの奥など。
- 期間を決める(任意): 例えば「半年後に見直す」など、目安を決めておくと管理しやすい。
- 中身がわかるようにする: 箱にラベルを貼るなど、何が入っているか分かるようにしておく。
- 無理強いしない: 子どもが強く抵抗する場合は、無理に保管せず、一旦戻す柔軟性も持つ。
しばらくして子どもがそのおもちゃのことを忘れていたり、成長して興味が変わっていたりすれば、その時に改めて手放すことを検討できます。
一時保管は、おもちゃを減らすことへの心理的ハードルを下げ、スムーズな整理を助ける有効な手段です。
ステップ4:定期的に見直し、入れ替える(ローテーション)
おもちゃの整理は一度で終わりではなく、定期的に見直し、おもちゃを入れ替える「ローテーション」を継続することが重要です。
なぜなら、子どもの成長は早く、興味関心も常に変化していくため、環境もそれに合わせてアップデートしていく必要があるからです。
また、ローテーションは、おもちゃの総数を増やさずに遊びに新鮮さをもたらす効果的な方法です。
定期的(例えば、月に1回、季節ごとなど)に、一時保管していたおもちゃの中から、今の発達段階や興味に合いそうなものをいくつか出して、代わりに今あまり遊んでいない「一軍」のおもちゃを一時保管に回します。
ローテーションには、以下のようなメリットがあります。
- おもちゃの総数を増やさずに、遊びに変化と新鮮さをもたらせる。
- 子どもの現在の興味や発達に合った環境を維持できる。
- しまい込んでいたおもちゃを有効活用できる。
- 定期的な見直しが、おもちゃが増えすぎるのを防ぐきっかけになる。
こうすることで、子どもは常に新鮮な気持ちで遊びに取り組むことができます。
忘れられていたおもちゃが、再び輝きを取り戻すこともよくあります。
このローテーションは、量を減らすのが難しいと感じているご家庭でも、すぐに取り入れられる有効な方法です。
定期的なローテーションによって、子どもは常に最適な環境で遊びに取り組むことができ、おもちゃが増え続けるのを防ぐ効果も期待できます。
モンテッソーリ式おもちゃ収納のコツ
おもちゃの量や選び方と同じくらい大切なのが、収納方法です。
モンテッソーリ教育の「整えられた環境」を実現するためには、子どもが自分で選びやすく、片付けやすい収納の工夫が欠かせません。
ここでは、具体的な収納のコツをご紹介します。
子どもの目線に合わせた低い棚を選ぶ
モンテッソーリ式収納の基本は、子どもの目線や手の届く高さに合わせた、オープンな棚を用意することです。
なぜなら、子どもが大人に頼らず、自分の意志でおもちゃを選び、手に取り、そして片付けることができるようにするためです。
この「自分でできる」経験が自立心を育みます。
蓋付きのおもちゃ箱のように中身が見えない収納や、高すぎる棚は、子どもの主体的な活動を妨げてしまいます。
低いオープン棚であれば、子どもはいつでも遊びたいおもちゃにアクセスでき、どこに戻せばよいかも一目でわかります。
低いオープン棚を選ぶメリットは以下の通りです。
- 子どもが自分で選べる: 大人に頼らず、主体的に遊びを始められる。
- 中身が見やすい: どんなおもちゃがあるか一目でわかり、選びやすい。
- 片付けやすい: どこに戻すか明確で、自分で片付ける習慣がつきやすい。
- 安全性が高い: 子どもがよじ登ったり、倒したりするリスクが低い。
子どもの自主性と安全性を考慮し、高さが低く安定したオープン棚を選ぶことが、モンテッソーリ式収納の第一歩です。
おもちゃの種類ごとにトレーやカゴで区切る
棚に置くおもちゃを、種類ごとにトレーや浅いカゴを使って仕切ることで、より整理された分かりやすい収納になります。
なぜなら、どこに何があるかが視覚的に明確になり、子どもが自分で目的のおもちゃを見つけやすく、また片付けやすくなるからです。
これにより、環境の秩序が保たれやすくなります。
例えば、「積み木はこのトレー」「パズルはこのカゴ」というように、グループごとに定位置を決めてあげます。
トレーやカゴで区切ることのメリットは以下の通りです。
- 視覚的な分かりやすさ: どこに何があるか一目瞭然になる。
- 秩序感の育成: 物が分類され、整理されている感覚を養う。
- 片付けの容易さ: 対応するトレーやカゴに戻すだけでよい。
- 活動の区切り: トレーごと持ち運べば、活動スペースを確保しやすい。
素材は、木製や自然素材のカゴなど、見た目にも美しいものを選ぶと、環境全体の統一感も出ます。
トレーやカゴの活用は、見た目の整理整頓だけでなく、子どもの論理的な思考や秩序感を育む助けにもなります。
一つのおもちゃ(活動)を一つのトレーにまとめる
さらに効果的な工夫として、ひとつの活動に必要なものを全てセットにして、ひとつのトレーにまとめる方法があります。
なぜなら、子どもが活動を始めたいと思った時に、必要なものを探す手間なく、すぐに取り組めるようにするためです。
これにより、活動への集中力が高まり、準備や片付けもスムーズになります。
例えば、パズルなら、パズルのピースと台紙を一緒にひとつのトレーに。
お絵描きセットなら、色鉛筆、紙、鉛筆削りをひとつのトレーにまとめます。
この方法は、特に複数のパーツからなるおもちゃや、道具が必要な活動(工作など)に適しています。
活動ごとにまとめる例を以下の表に示します。
| 活動内容 | トレーにまとめるもの(例) |
|---|---|
| パズル | パズルのピース、台紙 |
| お絵描き | 色鉛筆(またはクレヨン)、紙、鉛筆削り |
| 粘土 | 粘土、粘土板、型抜き、ヘラ |
| ビーズ通し | ビーズ、ひも |
| シール貼り | シール、台紙 |
「1活動=1トレー」の原則は、子どもの活動への集中と自立した片付けを効果的にサポートします。
見やすく、美しくディスプレイする(詰め込まない)
おもちゃの収納は、ただしまうだけでなく、ゆとりを持って見やすく、美しくディスプレイすることを意識しましょう。
なぜなら、美しく整えられた環境は、子どもの美的感覚を養い、物を大切に扱おうとする気持ちを引き出すからです。
また、詰め込みすぎず見やすくすることで、子どもが「遊びたい」という意欲を持ちやすくなります。
ぎゅうぎゅうに詰め込むのではなく、ひとつひとつのおもちゃが魅力的に見えるように、隣のおもちゃとの間隔を空けたり、向きを揃えたりするだけでも、印象は大きく変わります。
美しく見せるためのポイントは以下の通りです。
- 詰め込みすぎない: 棚板に対して7割程度の収納を目安にする。
- 間隔を空ける: おもちゃ同士が重ならないように配置する。
- 向きを揃える: 見た目に統一感を出す。
- 色合いを考慮する: 全体の色味がごちゃごちゃしないように配置する。
- 定期的に掃除する: 棚やトレーをきれいに保つ。
ごちゃごちゃと散らかった状態よりも、すっきりと整頓された状態の方が、子どもは集中して遊びに取り組むことができます。
見た目の美しさも意識した収納は、子どもの情緒安定や活動意欲にも繋がる大切な要素です。
おもちゃの「住所」を決める
全てのおもちゃに対して、「決まった置き場所=住所」を明確に決めることが、片付けの習慣化には不可欠です。
なぜなら、どこに戻せばよいかが分かっていれば、子どもは迷うことなく片付けに取り組めるからです。
「使ったら元の場所に戻す」というルールが明確になり、秩序感が育まれます。
「この積み木は、この棚の、このトレーの中」というように、具体的で明確な場所を設定します。
我が家でも、収納に入れ物の名前を書くラベルを貼ってみたところ、以前よりは片付けやすくなったように感じます。
写真やイラストのラベルを活用するのもよい方法です。
「住所」決めを成功させるためのポイントをいくつかご紹介します。
- 全てのおもちゃに定位置を: 例外を作らない。
- 子どもにも分かりやすく: ラベル(写真・イラスト・文字)を活用する。
- 場所を一貫させる: 頻繁に置き場所を変えない。
- 片付けやすい場所に設定する: 無理なく戻せる場所を選ぶ。
最初は親が一緒に手伝いながら、「積み木さんのお家はここだよ」と教えてあげることで、子どもは場所を覚えていきます。
明確な「住所」は、子どもが自分で片付けられるようになるための道しるべとなります。
片付けやすい動線を意識する
収納場所だけでなく、遊ぶ場所と収納場所の位置関係(動線)も考慮することで、片付けがよりスムーズになります。
なぜなら、遊ぶ場所から収納場所までの距離が遠かったり、途中に障害物があったりすると、片付けるのが億劫になりやすいためです。
物理的な環境を整えることで、行動をサポートします。
例えば、おもちゃ棚のすぐ近くに、子どもが座って遊べるラグやマットを敷いておくと、遊び終わった後に棚に戻す動作がスムーズになります。
また、おもちゃを出す・しまうという一連の流れを考慮して、棚の周りには十分なスペースを確保しておくとよいでしょう。
動線を意識する際のポイントは以下の通りです。
- 遊ぶ場所の近くに収納を: 移動距離を短くする。
- 棚の周りにスペースを確保: 出し入れしやすいように。
- 床に物を置きっぱなしにしない: 通路を確保する。
- 一時置き場を作る(任意): すぐに片付けられない場合の一時的なカゴなどを用意する。
子どもが動きやすく、ストレスなく片付けられるような空間づくりを意識してみてください。
ほんの少しの動線の工夫で、片付けのハードルはぐっと下がります。
片付けを促す効果的な声かけ例
収納環境を整えるだけでなく、子どもの気持ちに寄り添った効果的な声かけも、片付けの習慣化には重要です。
なぜなら、特に「片付け嫌い」のお子さんには、一方的な指示や叱責は逆効果になることが多く、やる気を引き出す工夫が必要だからです。
僕の経験でも、「ただ『片付けて』というだけではうまくいかない」ことが多いです。
では、どんな声かけが効果的なのでしょうか?
我が家で試して効果があったのは、「競争」と「片付け後の楽しみ」を提示することです。
例えば、「ママ(パパ)とどっちが早くおもちゃをお家に帰せるかな?よーいドン!」とゲーム感覚で誘ったり、「このおもちゃを片付けたら、公園に行こうか!」と、片付けた後の楽しい予定を伝えたりすると、やる気が出ることがあります。
ただし、効果的な声かけは日によって変わるため、その時々の子どもの様子を見ながら、響く言葉を探っていく根気も必要かもしれません。
避けるべき声かけと、試してみたい声かけの例をまとめました。
- 「早く片付けなさい!」(命令口調、一方的)
- 「なんで片付けないの!」(詰問、否定)
- 「もう捨てるよ!」(脅し、子どもの気持ちを無視)
- 「いつも散らかして…」(人格否定につながる可能性)
- 「おもちゃさん、お家に帰りたがってるよ」(擬人化)
- 「あと5分で片付けタイムにしようか」(予告、見通し)
- 「赤いブロックだけ、カゴに入れてくれる?」(具体的な指示、スモールステップ)
- 「ママ(パパ)と一緒にやろうか」(共感、協力)
- 「きれいになったら気持ちいいね」(片付いた後の心地よさを伝える)
環境を整えることと並行して、子どものやる気を引き出すポジティブな声かけを心がけましょう。
おもちゃを増やしたくない時の賢い付き合い方
どんなに整理や収納を工夫しても、誕生日やクリスマス、祖父母からのプレゼントなどで、おもちゃは増えてしまいがちです。
また、「そもそも、これ以上物を増やしたくない」と考えている方もいるでしょう。
ここでは、おもちゃを増やさずに、子どもの遊びを豊かにするための賢い付き合い方をご紹介します。
おもちゃのサブスクリプション(レンタル)サービスを活用する
物を増やさずに多様なおもちゃを試したい場合、おもちゃのサブスクリプション(レンタル)サービスは有効な選択肢のひとつです。
なぜなら、月額料金で定期的におもちゃが交換されるため、家に物が増え続けるのを防ぎながら、子どもの発達や興味の変化に合わせて常に新しいおもちゃを提供できるからです。
特に、モンテッソーリ教育に関心があるけれど高価な教具を揃えるのが難しい場合や、おもちゃ選びに自信がない場合に、専門家が選んだ質の高い知育玩具を試せるのは大きなメリットです。
僕自身は利用経験がありませんが、「もっと早く知っていたら利用したかった」と感じています。
メリットとデメリットを理解した上で、利用を検討してみるとよいでしょう。
- 家に物が増えない、保管場所に困らない
- 子どもの発達や興味の変化に合わせておもちゃを交換できる
- 自分では選ばないような多様なおもちゃに出会える
- 高価な知育玩具を試すことができる
- 専門家が選んでくれるので、おもちゃ選びの手間が省ける
- 月額(または年額)の費用がかかる
- 気に入ったおもちゃでも返却する必要がある(買取可能な場合も)
- 紛失や破損した場合に弁償が必要な場合がある(補償付きプランも多い)
- 届くおもちゃを選べない場合がある
おもちゃのサブスクは、賢く使えば、おもちゃの量をコントロールしながら、子どもの遊びを豊かにできる便利なサービスです。
様々な会社がサービスを提供しているので、ご家庭のニーズに合ったものがあるか、ぜひ一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
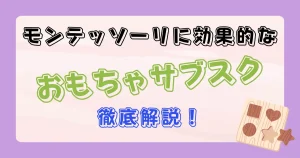
おもちゃのサブスクは、物を増やさずに多様な遊びを提供したい家庭にとって、有力な選択肢となります。
図書館や児童館、支援センターなどの公共施設を利用する
おもちゃを増やさずに遊びの機会を提供する方法として、図書館や児童館、子育て支援センターなどの公共施設を積極的に活用するのも非常に有効です。
なぜなら、これらの施設では、無料で、あるいは低コストで、家庭にはない様々なおもちゃや遊具で遊ぶことができるからです。
また、他の子どもたちと関わる機会も得られます。
多くの図書館では絵本の貸し出しだけでなく、紙芝居や、時にはおもちゃやボードゲームなどを備えているところもあります。
児童館や子育て支援センターなどには、大型の遊具や様々なおもちゃが用意されています。
公共施設の利用には、以下のようなメリットがあります。
- 費用がかからない、または低コスト: 家計に優しい。
- 多様な遊び環境: 家にはないおもちゃや遊具で遊べる。
- 他の子どもとの交流: 社会性を育む機会になる。
- 親の情報交換の場: 他の保護者と交流できる。
- 専門家への相談: 保育士や職員に育児相談ができる場合も。
定期的に通うことで、家におもちゃをたくさん置かなくても、子どもは多様な遊びを体験できます。
身近な公共施設は、おもちゃを増やさずに子どもの遊びの世界を広げるための貴重なリソースです。
おもちゃ以外の室内遊びも楽しむ(お絵描き、折り紙など)
子どもの遊びは必ずしもおもちゃが必要なわけではなく、お絵描き、折り紙、工作など、おもちゃ以外の室内遊びも創造性や集中力を育む上で非常に有効です。
なぜなら、これらの活動は、特別な道具をたくさん揃えなくても手軽に始められ、子どもの自由な表現や工夫を引き出すことができるからです。
我が家の子どもたちも、室内ではお絵描きや折り紙に夢中になります。
画用紙とクレヨン、折り紙、小麦粉粘土など、基本的な材料があれば十分楽しめます。
また、空き箱やトイレットペーパーの芯、ペットボトルなどの廃材を使った工作も、子どもの想像力をかき立てる楽しい遊びになります。
おもちゃ以外の遊びと、それによって育まれる力の例をいくつか紹介します。
| 遊びの種類 | 育まれる力(例) | 必要なもの(例) |
|---|---|---|
| お絵描き | 表現力、色彩感覚、手指の巧緻性 | 紙、クレヨン、色鉛筆、絵の具 |
| 折り紙 | 集中力、空間認識能力、手順の理解 | 折り紙 |
| 粘土 | 想像力、創造性、触覚刺激 | 粘土、粘土板、ヘラ |
| 工作 | 創造性、問題解決能力、工夫する力 | 空き箱、ハサミ、のり、テープ |
おもちゃだけに頼らず、多様な創作活動を取り入れることで、物を増やさずに子どもの経験をより豊かなものにすることができます。
外遊びや自然体験を大切にする
室内遊びだけでなく、外に出て体を動かしたり、自然に触れたりする経験も、子どもの心身の健やかな成長には欠かせません。
なぜなら、屋外での活動は五感をフルに使い、探求心や好奇心を刺激し、体力向上やストレス解消にもつながるからです。
自然そのものが最高の遊び場となり得ます。
公園で走り回る、砂場で遊ぶ、虫や植物を観察するなど、様々な活動があります。
我が子も、「遊具が充実している公園なら無限に遊びます」。
天気のよい日には積極的に外に連れ出し、思い切り体を動かす機会を作ってあげましょう。
特別な場所に行かなくても、近所の公園を散歩したり、道端の草花を観察したりするだけでも、子どもにとっては発見に満ちた貴重な体験となります。
外遊びには、以下のような多くのメリットがあります。
- 体力向上: 運動能力やバランス感覚が養われる。
- 五感の刺激: 風、光、土、緑など、自然の要素を全身で感じられる。
- 探求心・好奇心の育成: 様々な発見を通して、知りたいという気持ちが育つ。
- ストレス解消・気分のリフレッシュ: 開放的な空間で、心身ともにリラックスできる。
- 社会性の発達: 公園などで他の子どもと関わる機会が生まれる。
おもちゃの量を気にするよりも、外遊びや自然体験といった多様な経験を豊かにすることに意識を向けるのも、子どもの成長にとって非常に大切な視点です。
まとめ
この記事では、モンテッソーリ教育の考え方に基づき、子どもの成長を促すおもちゃの量や環境づくりについて解説してきました。
最後に、大切なポイントを振り返ってみましょう。
- モンテッソーリ教育では、子どもの集中力や自己選択能力を育むため、おもちゃの「量」も「整えられた環境」の重要な要素と考える。
- おもちゃの与えすぎは、集中力の散漫、物の価値観の低下、片付け困難などの影響がある可能性。
- 適正量は、年齢、子どもの興味・集中度、自分で管理できるかなどをヒントに見極める。量を減らせなくてもOK。
- おもちゃ選びは、発達段階、質(素材)、目的、多様性、美しさ、安全性がポイント。
- 減らす・整理する際は、現状把握→分類→一時保管→ローテーションのステップで。
- 収納は、低い棚、トレーでの区切り、おもちゃの住所決め、動線、効果的な声かけがコツ。
- 増やさないためには、サブスク、公共施設、おもちゃ以外の遊び、外遊びなどを活用。
おもちゃの量に絶対的な正解はありません。
大切なのは、量そのものにこだわりすぎず、お子さんの様子を注意深く観察し、その子にとって最適で「整えられた環境」を、ご家庭でできる範囲で工夫していくことです。
僕自身も、モンテッソーリ教育に詳しくはありませんが、「子どもの自主性を重視し、やりたいことはできるだけやらせてあげたい」と考えています。
難しく考えすぎずに、子どもの「やってみたい」という気持ちを尊重し、見守る姿勢そのものが、モンテッソーリ教育の根底にある考え方にも通じるといえるでしょう。
この記事が、あなたのご家庭のおもちゃとのよりよい関わり方を見つけるためのヒントとなれば幸いです。
お子さんの輝く未来のために、今日からできることを見つけていきましょう。
もし、日々の知育玩具選びや、質の高い遊びの機会づくりに迷ったら、専門家がセレクトしたおもちゃが届くおもちゃのサブスクを試してみるのも、忙しい現代のパパママにとって、手軽で有効な選択肢のひとつですよ。
トイサブは、おもちゃのサブスクサービスで知名度トップクラス!
生後1ヶ月から利用でき、月齢に合わせた知育に最適なおもちゃが届きます。
そのほか、トイサブを利用することで以下のようなメリットがあります。
- 返却期限や延滞料金なし
- おもちゃが壊れても、基本的に弁償は不要
- 気に入った場合はお得に買い取ることも可能
初月は約2,000円OFFの1,990円~使用できるので、まずは利用してみるとよいでしょう。
>2ヶ月990円で利用できる妊娠中から生後1.5か月までの方はこちら
おもちゃのサブスクレンタルサービス12つを徹底比較した以下の記事も、合わせて参考にしてみてください。