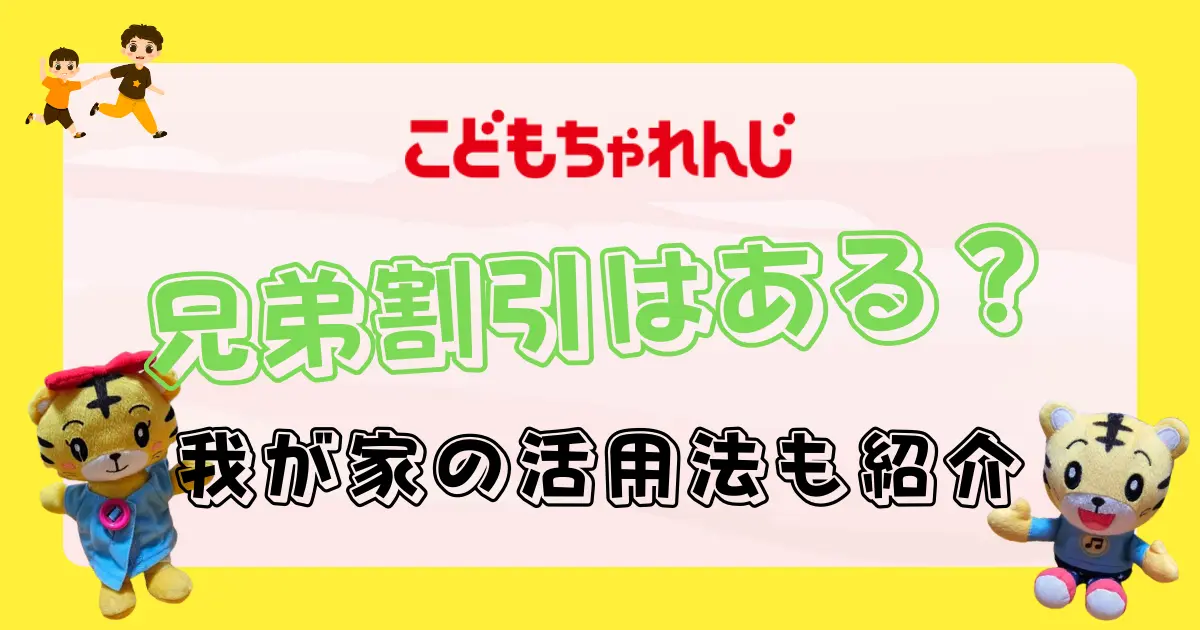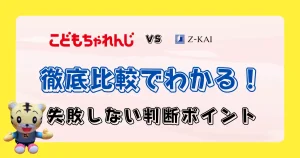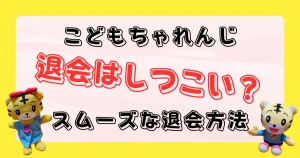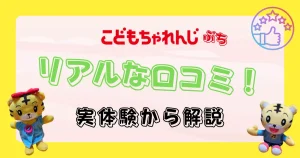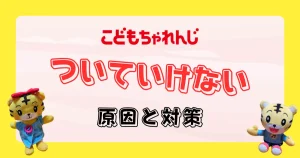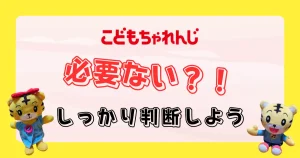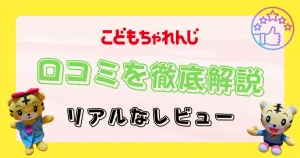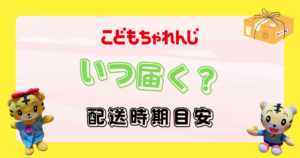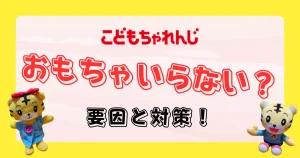兄弟がいるご家庭なら、「ふたり目のこどもちゃれんじ、どうしようかな?」「兄弟で入会したら割引はある?」など、色々な疑問や悩みが出てきますよね。
僕も5歳と3歳の息子を育てるパパとして、ふたり目のこどもちゃれんじ利用については本当に色々と検討しました。
特に、こどもちゃれんじを兄弟で利用する場合、こんな具体的な悩みや疑問を抱えている方が多いのではないでしょうか。
- 兄弟がいる家庭でのこどもちゃれんじ、どうするのがベストか悩む…
- できるだけ費用は抑えたいけど、子どものためには良い選択をしたい
- お下がりにするメリット・デメリットを知りたい
- 最新のお得な入会方法やキャンペーン情報が知りたい
この記事では、僕自身の体験(我が家はお下がり活用中!)も踏まえ、「こどもちゃれんじの兄弟割引」の真実、お下がりのリアル、お得な「紹介制度」について、分かりやすく解説します。
この記事を読めば、これらの点がスッキリ解消しますよ。
- こどもちゃれんじの兄弟割引の有無
- お得な「紹介制度」の詳細と最新特典
- お下がり利用のリアルな体験談(メリット・デメリット)
- 兄弟で別々に受講するメリット・デメリット
- 兄弟利用に関するQ&A
最後まで読めば、あなたのご家庭にとって「こどもちゃれんじを兄弟でどう利用するのがベストか」が明確になり、後悔しない選択ができるはずです。
費用面だけでなく、お子さんの成長にとっても一番よい方法を一緒に考えましょう。
もし「うちの子にも!」と思ったら、お得な制度を活用して、こどもちゃれんじを始めてみてくださいね。
【結論】こどもちゃれんじに「兄弟割引」はあるか
まず、皆さんが一番気になっているであろう結論から。
こどもちゃれんじに、いわゆる「兄弟割引」という名前の、恒常的な料金割引制度はあるのでしょうか?
原則として月額・年額料金の「兄弟割引」制度はない
残念ながら、2025年4月現在、こどもちゃれんじには「兄弟姉妹で同時に入会・受講しているから」という理由だけで、月額料金や年額料金が自動的に割引になる、といった恒常的な制度は原則としてありません。
これは公式サイトでも明記されており、「ふたり目だから安くなる」という期待は持たない方がよいでしょう。
この点は、入会を検討する上でまず押さえておきたいポイントです。
具体的に注意したい点は以下の通りです。
- 恒常的な割引なし: 通常、兄弟がいても受講費は一人分ずつ必要。
- 進研ゼミとの組み合わせも同様: 上の子が進研ゼミ、下の子がこどもちゃれんじでも原則割引なし。
- 期待しすぎない: 他の方法でお得にならないか検討するのが賢明。
ですが、がっかりするのはまだ早いです!
お得に入会する方法は他にもありますよ。
ただし期間限定の「特別割引キャンペーン」が存在する可能性も
恒常的な割引はありませんが、期間限定で、特定の条件を満たす兄弟を対象とした「特別割引キャンペーン」が実施される可能性はあります。
これは常に実施されているわけではなく、対象者も限定的なことが多いようです。
例えば、過去には以下のような条件で案内があったという情報もあります。
- 兄弟がすでに会員であること
- 一括払いを選択すること
- 特定の学年の兄弟がいる家庭にDMで案内が届くなど
これらはベネッセ側からのアプローチが中心のようなので、もし案内が届けばラッキー、くらいの認識でいるのがよさそうです。
会員向けメールで案内が来ることもあるので、チェックしておくとよいかもしれません。
「兄弟割引」より現実的なのは紹介制度!その詳細を徹底解説
恒常的な兄弟割引がない代わりに、もっとも確実でお得に入会できる可能性が高いのが「お友だち・ごきょうだい紹介制度」です。
これはぜひ活用したい制度なので、詳しく見ていきましょう!
紹介制度の仕組み:紹介者・入会者どちらも特典ゲット!
紹介制度は、すでに会員の方(紹介者)の紹介で新しい方(入会者)が入会すると、紹介した人と入会した人の両方に、好きなプレゼントなどの特典があるという、とても嬉しい仕組みです。
つまり、紹介する側もされる側もお得になるWin-Winの制度なんです。
この制度の嬉しいポイントをまとめると、以下のようになります。
- 双方に特典: 紹介者も入会者も、それぞれプレゼントなどがもらえる。
- 選べる楽しさ: 複数の選択肢から好きな特典を選べる場合が多い。
- 簡単な手続き: 入会時に紹介者の情報を伝えるだけでOK。
- 兄弟利用OK: お友達だけでなく、兄弟姉妹間の紹介でも利用可能!
入会を考えているなら、この制度を活用しない手はありませんね。
【2025年4月時点】最新の紹介特典(プレゼント&キャッシュバック情報)
「どんな特典があるの?」と気になりますよね。
特典内容は時期によって変わりますが、僕が受け取った会員向けメール(2025年4月4日配信)の情報を例としてご紹介します。
この時の特典をまとめると、以下のようになっていました。
| 特典の種類 | 対象者 | 詳細(2025/4/4時点のメール情報例) |
|---|---|---|
| キャッシュバック | 紹介者のみ | 5月号受講費30%キャッシュバック |
| 選べるプレゼント | 紹介者・入会者 各1点 | 下記リストのグッズ・ギフトカード等から選択 |
さらに、選べるプレゼントのラインナップも豊富でした!
- ★パティシエしまじろうのブロックセット
- ★しまじろう <ループ付き>ダイカットタオル
- ★すみっコぐらし <ループ付き>ダイカットタオル
- ★おえかきくるりんぴつ
- ★しまじろうのランチボックス
- ★しまじろうのつみきセット
- ★かたちであそぼう! スタンプセット
- ★Amazonギフトカード(500円分)
- ★しまじろうのえいごトランプ
- ★しまじろうのおやつケース
- ★こどもちゃれんじ×ILLUMS ベビースリーパー
- ★しまじろう おねしょガード
おもちゃから実用品、ギフトカードまで幅広い選択肢があるのは嬉しいですね。
最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
兄弟(姉妹)での利用方法:同時入会でも活用できる!
このお得な紹介制度は、もちろん兄弟姉妹の間でも使えます!
兄弟での利用パターンと申し込みのポイントは、主に以下のようになります。
- 上の子が会員、下の子が新規入会: 上の子が紹介者、下の子が入会者として申し込むのが基本です。
- 兄弟が同時に新規入会: ひとりを先に入会させ、その会員情報を使ってもうひとりを紹介で申し込む方法があります(要確認)。
- 手続き: Webまたは電話。同時入会の場合は電話が確実かもしれません。
これで、兄弟姉妹でも紹介制度のメリットをしっかり受けられますね。
紹介制度の申し込み手順(Web・電話)
紹介制度を利用する際の申し込み手順は、主にWebと電話の2通りです。
Webサイトからの申し込み手順(例)は以下の通りです。
- こどもちゃれんじ公式サイトの入会申し込みページへ。
- コースや支払い方法を選択。
- 情報入力画面で「ご紹介者の情報」欄を探す。
- 紹介者の氏名・会員番号などを正確に入力。
- 入会者・紹介者それぞれの希望プレゼントを選択。
- 情報を確認し、申し込み完了。
電話での申し込みは、オペレーターに紹介制度利用の旨と紹介者情報を伝えればOK。
Webでの入力が不安な場合や同時入会時は、電話の方がスムーズでしょう。
いずれの場合も、紹介者の情報(特に会員番号)を事前に準備しておくとよいですね。
紹介制度を利用する際の注意点
お得な紹介制度ですが、利用する際にはいくつか注意点があります。
スムーズに特典を受け取るために、特に以下の点には注意しましょう。
- 入会後の申請期限: 入会時に伝え忘れても、入会後30日以内なら後から申請できる場合があります(要確認)。できれば入会時に確実に伝えましょう。
- 紹介者情報の正確性: 氏名や会員番号を間違えると特典が適用されない可能性あり。正確に!
- 対象外の講座: オプション講座のみの入会は対象外の場合があります。
- プレゼント送付先: 原則、入会者・紹介者それぞれの登録住所に別々に送られます。
- キャンペーン併用: 他のキャンペーンと併用できるかは要確認。
これらの点に気をつければ、紹介制度のメリットを最大限に活かせますよ。
【体験談】こどもちゃれんじ、ふたり目は「お下がり」も活用できる
ここからは僕自身の体験談も交え、「お下がり」という選択肢についてお話しします。
兄弟割引がないなら…と考える方も多いですよね。
我が家も4歳長男の教材を2歳次男がお下がりで使っています。そのリアルな声をお届けします。
我が家がお下がりを選んだ理由
次男に新規入会せず、長男のお下がりを選んだ主な理由はシンプルです。
なぜお下がりを選んだか、その背景には、特に以下の点が大きかったです。
- 費用節約: やはりこれが一番。費用が倍になるのを避けたかった。
- 物の増加抑制: すでにおもちゃで溢れ気味…収納スペースの問題。
- 教材の耐久性: 長男使用後も十分使える状態だったこと。
- 年齢差(2歳差): 少し先取りでも遊べるのでは?と考えたこと。
これらの点を総合的に考え、我が家ではお下がりを選択しました。
お下がりのメリット:2歳差でも「先取り学習」で発達を伸ばせる!
実際にお下がりを使ってみて感じている、費用面以外のメリットもあります。
特に大きいと感じているのが、「先取り学習」ができる点です。
我が家で実感している主なメリットはこちらです。
- コスト削減: 受講費がかからないのが最大のメリット。
- 先取り学習: 上の子の教材で知的好奇心を刺激できる。(我が家の弟は兄のおもちゃで楽しそうに遊んでいます!)
- 物の管理が楽(?): 新しく物が増えず管理対象が増えない(はず)。
- エコ: 教材を無駄なく活用。
弟は、兄が使っていた少し上のコースのおもちゃにも興味津々。
対象年齢より早くても、本人が興味を示せば、それは絶好の学びのチャンス。
子どもの発達段階を親が決めつけず、可能性を広げられるのは、お下がりの大きなメリットだと感じています。
お下がりのデメリット:おもちゃの取り合いで喧嘩も…
もちろん、お下がりにはデメリットもあります。
我が家で一番の課題は、やはり「おもちゃの取り合い」による兄弟喧嘩です。
正直なところ、お下がりならではの悩みとして、以下のような点が挙げられます。
- 兄弟喧嘩の勃発: おもちゃの所有権をめぐって喧嘩に。(「それ、ぼくの!」が日常茶飯事…)
- 教材の劣化・消耗: シール貼り済み、書き込み済み、破損などで完全な状態で使えないことも。
- パーツの紛失: 細かいパーツがないと遊びが制限される。
- 下の子の特別感の欠如: 「自分だけのもの」という喜びが少ない。
- 最新教材ではない: リニューアル内容で学べない。
特にパーツの紛失は困りますね。
下の子が「あれがないと完成しない!」と癇癪を起こすことも…。
また、下の子自身に「これは自分のだ」という特別感を与えにくいのも事実です。
我が家流!お下がり教材の活用術と工夫
デメリットを減らしメリットを活かすため、我が家なりに工夫もしています。
完璧ではありませんが、以下のようなことを心がけています。
- 興味尊重型: 下の子が興味を示したものから自由に遊ばせる。
- 順番にこだわらない: 対象年齢や教材の順番より「やりたい!」気持ち優先。
- パーツ探しも遊びに: 「あれがない!」時は親子で一緒に探す時間にする。
- 代替・工夫: ないパーツは他のもので代用したり、別の遊び方を考えたり。
- 喧嘩の仲裁: ルール(順番、一緒に遊ぶ)を話し合う(根気が必要…)。
お下がりは、親の関わり方や工夫次第で、学びの効果を十分に引き出せる可能性があると感じています。
こどもちゃれんじを兄弟で別々に受講するメリット
お下がりの実態をお話ししましたが、もちろん兄弟それぞれが別々に新規受講するメリットも大きいです。
予算やスペースが許すなら、こちらも有力な選択肢。
その主なメリットを見ていきましょう。
下の子にも新品の状態でおもちゃや絵本が届く
やはり最大のメリットは、下の子もピカピカの新品教材でスタートできること。
お下がりの心配事(劣化、パーツ不足など)がなく、自分専用の真新しい教材が届くのは、子どもにとって特別な喜びです。
この「自分だけのもの」という感覚がもたらすメリットは、以下のような点です。
- 新品の喜び: きれいな教材で気持ちよく始められる。
- 自分だけの特別感: 所有意識が芽生え、物を大切にする心や学習意欲を育む。
- 消耗品の心配なし: ワークブックやシールも気にせず使える。
- 集中できる環境: 自分専用の教材で邪魔されずに取り組める。
特にワークブックなどは、新品だと気持ちよく取り組めますよね。
過去の感想などが反映されたアップデートVerのおもちゃになっていることも
こどもちゃれんじの教材は、常に進化しています。
下の子が新規入会すれば、お兄ちゃん(お姉ちゃん)の時よりも改善・改良された、最新バージョンの教材で学べる可能性があります。
具体的には、以下のようなメリットが考えられます。
- 最新教材で学べる: リニューアル内容が反映された教材を使える。
- 時代の変化に対応: 新しい学びの要素が取り入れられている可能性。
- より洗練された内容: 使いやすさや安全性が向上しているかも。
- 上の子との違いも楽しめる: 親子で変化を楽しむことも。
常に最新の、よりよい教材で学ばせたい、と考えるなら、新規受講は大きなメリットです。
おもちゃの取り合いの喧嘩を防げる
お下がりの大きな悩みである「おもちゃの取り合い」による喧嘩を大幅に減らせるのも、別々受講の大きなメリットです。
それぞれの所有物が明確になることで、家庭内の平和に繋がるかもしれません。
このメリットは、日々の育児ストレス軽減にも貢献します。
- 所有権が明確: 「自分だけのもの」で取り合いが減る。
- 平和な時間: 穏やかに遊んだり学んだりする時間が増える。
- 親の負担軽減: 喧嘩の仲裁ストレスが減る。
- 公平感: 兄弟それぞれに平等に与えられていると感じやすい。
もちろん、相手のおもちゃがよく見えることはありますが、「自分のおもちゃもある」安心感は大きいでしょう。
こどもちゃれんじをお下がりにするメリット
一方で、我が家のように「お下がり」を選ぶことにも、たくさんのメリットがあります。
コスト面だけでなく、意外な利点も含めて、改めて整理してみましょう。
おもちゃが増えて家が散らかるのを防げる
こどもちゃれんじのエデュトイは魅力的ですが、毎月届くとあっという間に物が増え、収納に困るご家庭は多いはず。
(我が家も常に散らかっています…)
お下がりなら、新しく物が増えないので、収納スペースの心配が減るのは大きな利点です。
具体的には、以下のようなメリットがあります。
- 物の総量が増えない: 新たな収納スペース確保が不要。
- 管理の手間軽減(?): 新規購入品がない分、管理対象は増えない。
- スッキリした空間: 家の中の物の増加を抑制。
- 片付け負担増なし: これ以上、片付ける物が増えない。
物理的に物を増やしたくない方には、お下がりが魅力的に映るでしょう。
兄弟受講だと約2倍かかる費用を抑えられる
これは言うまでもなく、お下がりの最大のメリットです。
兄弟ふたりが別々に受講すると、単純計算で費用は約2倍になります。
お下がりなら、下の子の分の受講費は一切かかりません。
この経済的なメリットは非常に大きいです。
- 圧倒的なコスト削減: 下の子の受講費がまるまる不要。
- 家計への貢献: 年間数万円の節約効果。
- 予算の有効活用: 浮いた費用を他に使える。
- 経済的な安心感: 教育費の負担を軽減。
教育費を賢く抑えたいご家庭にとって、非常に合理的な選択肢といえます。
下の子が学習を先取りできる
お下がり利用で、下の子が実年齢より少し上の教材に触れる「先取り学習」の機会が生まれます。
これは子どもの知的好奇心や可能性を広げる上で、意外なメリットです。
具体的には、以下のような効果が期待できるかもしれません。
- 早期の刺激: 知的好奇心が刺激される。
- 発達促進の可能性: 文字や数などの理解が早まるかも。
- 柔軟な学び: 子どもの興味に合わせて教材を選べる。
- 兄弟間の相互作用: 一緒に遊ぶ中で学びが深まることも。
上の子の教材に興味を示す下の子は多いもの。
年齢の枠にとらわれず、子どもの「やりたい!」気持ちに合わせて学びを提供できるのは、お下がりの面白い点ですね。
このように、お下がりにも多くのメリットがあります。
デメリットも考慮し、ご家庭の状況やお子さんの性格に合わせて、新規受講とお下がりのどちらが良いか、じっくり検討してみてくださいね。
もし迷ったら、まずはこどもちゃれんじの無料資料請求で、最新教材をチェックするのもオススメです。
こどもちゃれんじ兄弟利用に関するFAQ
最後に、こどもちゃれんじの兄弟利用に関して、よくある質問とその回答をQ&A形式でまとめました。
疑問点の解消に役立ててください。
Q1. キャンペーンや紹介制度について詳しく知りたい時の問い合わせ方法は?
A. 最新情報を確認したい場合は、主に以下の方法があります。
- 公式サイト: 最新キャンペーンや紹介制度のページを確認。(「こどもちゃれんじ 紹介制度」などで検索)
- 電話問い合わせ: 公式サイト記載の番号へ。オペレーターが対応してくれます。(複雑な場合は電話が確実)
- 会員向けメール: 定期的に届くメールマガジンをチェック。(僕もこれで情報を得ています)
不明点は気軽に問い合わせてみましょう。
Q2. 進研ゼミ(小学生以上)との兄弟割引・紹介制度はある?
A. この組み合わせについて、整理してお答えしますね。
- 兄弟割引: 原則としてありません。
- 紹介制度: こちらは利用できます! 進研ゼミ会員⇔こどもちゃれんじ入会者の紹介も可能です。特典もあるので活用しましょう。
直接的な割引はないけれど、紹介制度でお得に入会できます。
Q3. 紹介してくれる人がいなくても紹介制度は使える?
A. 「周りに紹介者がいない…」という場合でも、諦めないでください。
いくつか裏ワザ的な方法もありますが、注意も必要です。
- SNSやブログを探す: 「紹介します」という投稿を探す。(個人情報には注意)
- 自己紹介: 兄弟同時入会の場合、片方を入会させてから紹介する方法も(要確認)。
最も安心なのは身近な人に協力してもらうことです。
SNS利用時は信頼できる相手か慎重に見極めましょう。
Q4. ポピーなど、他の通信教育と比較してどう?
A. 他教材との比較ですね。
僕は「幼児ポピー」を1ヶ月試した経験があります。
あくまで僕個人の感想ですが、ポピーと比較すると以下のように感じました。
- ポピーの印象: 教材(ワーク)がシンプル、ボリューム少なめ。付録はほぼなし。
- お下がり適性(ポピー): 内容が薄く教材が傷みにくいため、お下がりには向いているかも。
- こどもちゃれんじ比較: 「遊びながら学ぶ」「知育玩具(エデュトイ)」の点では、ちゃれんじが優位。ボリュームも多い。管理は大変だが、子どもの食いつきは良い。
ワーク中心ならポピー、遊びや体験重視ならこどもちゃれんじ、という印象です。
他教材もそれぞれ特徴があるので、資料請求などで比較検討するのが一番ですね。
まとめ
今回は、「こどもちゃれんじの兄弟割引」をテーマに、紹介制度やお下がり活用について解説しました。
兄弟がいるご家庭での最適な選択のヒントは見つかりましたか?
この記事でお伝えした重要なポイントを、最後にもう一度確認しましょう。
- こどもちゃれんじに、恒常的な「兄弟割引」は原則ない。
- 期間限定キャンペーンの可能性はあるが、限定的。
- お得なのは「紹介制度」。紹介者・入会者双方に特典あり!
- 紹介制度は兄弟間でも利用可能。最新特典は公式サイトで要確認。
- ふたり目は「お下がり」も有効。コスト削減・先取り学習のメリット、喧嘩・劣化のデメリットあり。
- 別々に新規受講なら新品教材・最新内容・喧嘩減のメリット。費用・物が増えるデメリットも。
- 「新規」か「お下がり」かは、費用・収納・子どもの性格・教育方針で判断を。
兄弟姉妹がいるご家庭にとって、通信教育選びは悩ましい問題です。
この記事が、あなたのご家庭にとってベストな選択をするための一助となれば嬉しいです。
もし、「やっぱりこどもちゃれんじ、気になる!」「お得な紹介制度で始めたい!」と感じたら、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。
特に、無料の資料請求では、実際の教材サンプルがお試しできます。
まずはお子さんがどんな反応をするか見てみるのがオススメですよ。
資料請求だけでもらえるプレゼントが付いていることもあります。
しまじろうと一緒に、お子さんの学びの世界を楽しく広げてあげましょう!