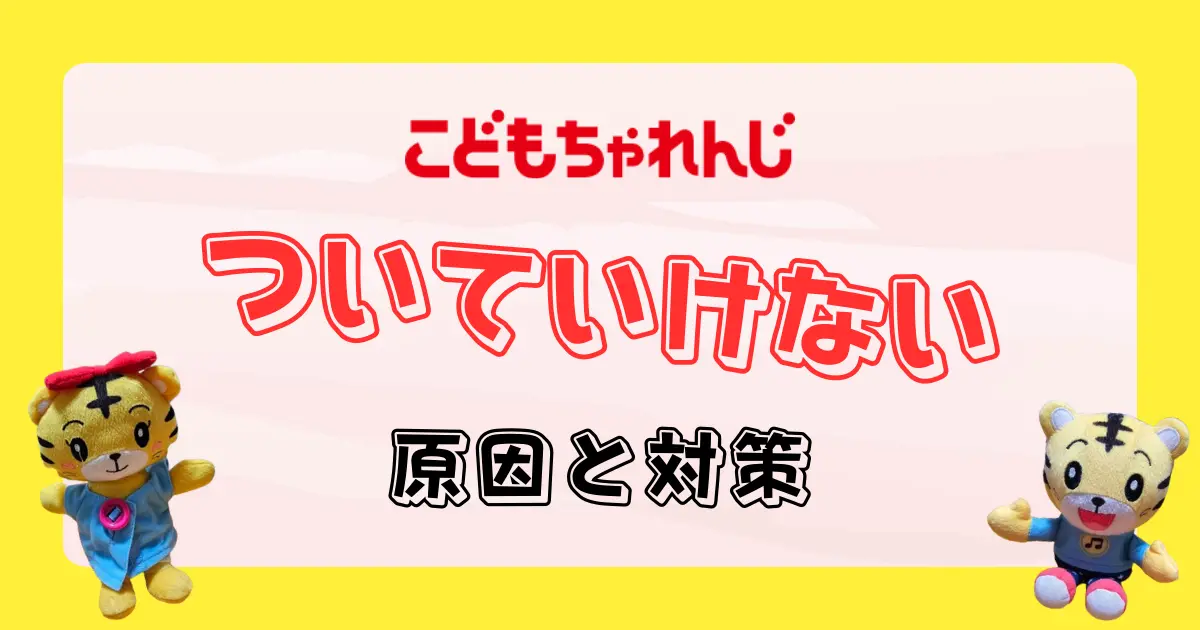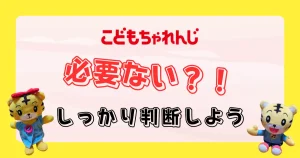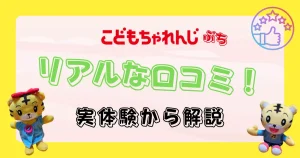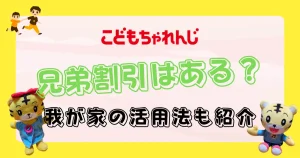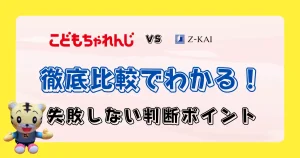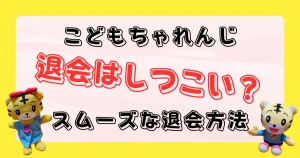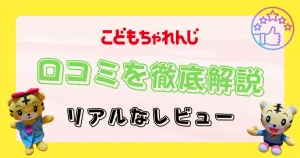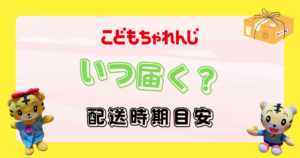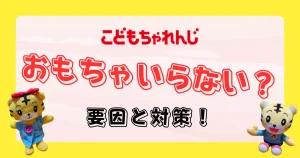「こどもちゃれんじ、うちの子だけついていけてないかも…」そんなふうに感じたことはありませんか?
同じ教材をやっているはずなのに、他の子はどんどん進んでいる。
でもうちの子は全然やる気を見せないし、内容もよく分かってなさそう…。
そんな場面に、僕も何度も直面してきました。
「このままでいいのかな?」「こどもちゃれんじが合ってないのかも…」と不安になる気持ち、すごくよく分かります。
でも、ついていけないと感じる理由はさまざま。
実は教材のせいでも、子どもが劣っているわけでもありません。
この記事では、こどもちゃれんじで「ついていけない」と感じる主な原因をわかりやすく解説。
さらに、今すぐ実践できる具体的な対策と、続けるかやめるかの判断基準まで丁寧にお伝えします。
こんな悩みがある方に特におすすめです。
- 子どもが教材に興味を示さない
- 内容が難しそうで理解できていない気がする
- やる気が続かず、途中でやめてしまう
- こどもちゃれんじを続けるべきか悩んでいる
この記事を読めば、親子でこどもちゃれんじをもっと楽しく取り組むヒントが見つかります。
- 「ついていけない理由」がはっきりして安心できる
- すぐにできる対処法が分かる
- 子どものペースに合った関わり方が見えてくる
僕自身、5歳と3歳の息子を育てながら、3年以上こどもちゃれんじを続けています。
その中で試行錯誤した経験もふまえて、パパママに役立つ情報をお届けします。
ぜひ最後まで読んで、悩みやモヤモヤをスッキリ解消していきましょう。
こどもちゃれんじについていけない原因は何が考えられる?
こどもちゃれんじを始めたけど、なんだかうまくいかない。
そんなふうに感じている方は意外と多いんです。
「うちの子、全然理解していない」「興味を示さない」など、ついていけてないように見えると、親としては不安になりますよね。
でも、そう感じる背景には、いくつかの共通する原因が隠れている場合があります。
まずは「なぜうまくいかないのか?」という視点から、原因を探っていきましょう。
年齢・月齢による理解力の差
こどもちゃれんじは年齢ごとにコースが分かれていますが、同じ学年でも月齢によって理解度に差が出ます。
たとえば、4月生まれの子と3月生まれの子では、実質1年近い差があります。
これは発達の早い幼児期にとっては、かなり大きな違いです。
「どうしてできないの?」と思ってしまう場面も、もしかしたら単に月齢差による理解力の違いかもしれません。
- 月齢が低い子は内容の理解に時間がかかる傾向がある
- 年齢だけで比べると「できない」と誤解しやすい
- 月齢に合わせた接し方で気持ちに余裕が持てる
「今はまだその時期じゃない」と受け止めてあげるだけで、親子ともに気持ちがラクになりますよ。
発達のスピードは本当に個人差がある
子どもの成長には、思っている以上に大きな個人差があります。
「他の子はできているのに…」と感じることがあるかもしれませんが、それは比較する相手が違うだけかもしれません。
例えば、言葉が早い子もいれば、運動が得意な子もいます。
学びのペースも、子どもによって全然違って当然なんです。
- 得意・不得意は子どもによってバラバラ
- 毎日のコンディションでも集中力は変わる
- 発達の早い・遅いに優劣はない
僕の次男は、同じ年の子に比べておしゃべりは遅めですが、音楽やダンスへの反応が抜群。
「言葉が遅い=発達が遅れてる」とは限らないんですよね。
子どもの「今できていること」に目を向けると、できないことばかりに目がいく焦りがスッと軽くなりますよ。
小さい頃は1年の差が大きいため、早生まれの子が感じやすい
こどもちゃれんじでは同じ学年で教材が届きますが、早生まれの子にとっては内容が難しく感じることもあります。
たった数ヶ月の差でも、幼児期の1年は大きな発達の差になります。
4月生まれと3月生まれでは、体の大きさや言葉の発達、理解力などに大きな違いが出て当然なんです。
教材に対する反応が鈍いからといって、能力が足りないわけではありません。
単に「まだその時期じゃない」だけということも多いんです。
- 早生まれの子は同級生と比べて不利に感じやすい
- 学年ではなく月齢の目線で見てあげると気が楽に
- 「今の段階でできること」を尊重するのが大切
実際、月齢の差があるだけで「うまくできない」と感じてしまうケースはよくあります。
でも、時期が来れば自然とできるようになる場面も多いんです。
早生まれの子には、その子のペースに合わせた関わり方が必要。
焦らず、成長を見守る気持ちで寄り添っていきましょう。
親の期待が高すぎる場合もある
子どもの成長を願うあまり、つい「もっとできるはず」と思ってしまうことってありますよね。
でも、親の期待が高すぎると、子どもにとってはプレッシャーになりやすく、逆にやる気をなくしてしまうこともあります。
教材を100%こなすことが目的になってしまうと、学びの楽しさが薄れてしまうことも。
- 期待が高すぎると、できないことにばかり目がいく
- 「ちゃんとやらなきゃ」と子どもが感じてしまうこともある
- 完璧を求めず、できた部分を認めることが大切
僕自身も、はじめは教材を最後まできっちりやりきってほしいと思っていました。
でも、その気持ちが強すぎて、子どもが嫌がるようになってしまったんです。
今は「1日1ページだけでもOK」と気持ちを切り替え、子どもの気分に合わせて進めるようにしています。
すると自然と笑顔で取り組むことが増えました。
親の期待も大切ですが、子どものペースや気持ちを尊重することが、長く続けるカギになりますよ。
そもそも教材の内容やレベルが合っていない
「なんだか難しそう」「全然興味を持ってくれない」と感じたとき、実は教材の内容やレベルが今の子どもに合っていない可能性があります。
こどもちゃれんじは年齢や発達をもとに設計されていますが、すべての子にピッタリ合うとは限りません。
特に苦手な分野が多く含まれていたり、興味のないテーマが続くと、子どもの集中力は一気に落ちてしまいます。
無理に続けると、やる気が下がるだけでなく、「できない」という苦手意識が芽生えてしまうことも。
- 教材のテーマが子どもの興味とズレていると飽きやすい
- レベルが高すぎると達成感を感じにくい
- 子どもが「やらされている感」を抱きやすい
僕の子どもも、ある号のワークが難しすぎて手が止まってしまい、やる気がガクッと下がったことがありました。
そのときは無理せずスキップして、得意な分野から再スタートしました。
教材に取り組む前に、「今この内容は、この子に合っているかな?」と一度見直すことが、学びをスムーズに進める大きなヒントになりますよ。
こどもちゃれんじについていけない時の具体的な対策
「うちの子、ついていけてないかも」と感じたとき、大切なのは「合ってないからやめる」ではなく、「どうすれば合うようにできるか」を考えることです。
子どもにとって無理なく楽しめる形で関わることで、教材の効果もグッと高まります。
ここでは、親子のストレスを減らしながらこどもちゃれんじを活かす具体的な方法を紹介します。
学年を1年遅らせる(学年を下げる受講)
今のコースが難しすぎると感じたら、思い切って1学年下のコースに切り替えるのも1つの方法です。
こどもちゃれんじでは、希望すれば実年齢とは異なるコースを選ぶことができます。
特に早生まれの子や、発達がゆっくりなタイプの子には「ちょっと背伸びすぎる」内容になることもあります。
- 今の発達段階に合った内容で楽しく取り組める
- 「できた!」が増えて自信がつきやすい
- 教材への苦手意識が薄れる
年齢に合わせるよりも、子どもの「今の理解力」に合わせた方がうまくいくケースはたくさんあります。
無理に今の学年にこだわらず、柔軟に選択してみましょう。
無理に先取りしない
「少しでも早く覚えてほしい」「周りの子に追いついてほしい」と、つい先取りしたくなる気持ち、ありますよね。
でも、子どもの発達段階に合っていない学習を無理に進めると、理解が追いつかず混乱したり、「勉強=つらいもの」という印象が残ってしまうこともあります。
こどもちゃれんじの教材は、その年齢・月齢の平均的なペースで組まれているため、先取りよりも「今を丁寧に」が大切です。
- 先取りは子どもの理解度や意欲を無視してしまうことがある
- 定着していないまま進むと、あとでつまずきやすくなる
- 「できること」を確実に増やすことのほうが学習効果が高い
僕自身も、早くひらがなを覚えてほしくて先取りした時期がありました。
でも、子どもはすぐに飽きてしまい、やる気をなくしてしまったことがありました。
結局、その子なりのペースで進めたほうが、楽しく学べて定着率も高くなると実感しました。
「急がば回れ」という気持ちで、今の理解を大切にしてあげましょう。
苦手な分野は飛ばす、戻る
教材をやっていて、子どもが明らかに嫌がったり、まったく集中しないときは、無理に進める必要はありません。
苦手な分野にぶつかったときは、いったんスキップしたり、少し戻って簡単な内容に触れることが有効です。
子どもの「今できること」から少しずつ広げていく方が、安心して学びを続けられます。
教材はあくまでツール。
子どもに合わせて柔軟に使うことが大事なんです。
- すべてのページを完璧にやる必要はない
- 「できない=進めてはいけない」ではない
- 苦手な分野は興味が出たタイミングで再挑戦すればOK
僕の子どもも、数字のワークになるとすぐ飽きてしまう時期がありました。
そんなときは思い切ってそのページは飛ばして、好きな工作ページから始めたところ、スムーズに流れが戻ってきました。
「飛ばしていい」「戻ってもいい」と思えるだけで、親も子どももずっと気持ちがラクになりますよ。
一緒に取り組む・遊びながら学ぶ
子どもが教材に乗り気じゃないときは、親がそばにいて一緒に取り組むだけで、ぐっとやる気が変わることがあります。
特に小さいうちは、親子の関わりそのものが学びになる時期。
「お勉強」ではなく「遊び」の延長で取り組むほうが、子どもも自然と楽しめます。
たとえば動画を一緒に見て笑ったり、付録のおもちゃを一緒に動かすだけでも、子どもの吸収力はぐんと高まります。
- 親が関わることで安心感と意欲が高まる
- 「遊びながら学ぶ」ことで記憶に残りやすくなる
- 一緒に楽しむ時間が親子の信頼関係を深める
僕も子どもと一緒に動画を見て真似したり、しまじろうの人形劇を自分で演じてあげたことがあります。
大げさに遊んでみせると、子どもも大爆笑して、自然とその日の教材にも取り組んでくれました。
「やらせる」ではなく、「一緒に楽しむ」。
それだけで、こどもちゃれんじはぐんと効果的になりますよ。
子どもが興味を持つ工夫をする
子どもが教材に興味を示さないときは、無理にやらせるよりも「どうしたら楽しんでくれるかな?」という視点で工夫してみることが効果的です。
興味を引き出すことで、自分から進んで取り組むようになり、「やらされている感」がなくなります。
ちょっとしたきっかけで、ガラッと反応が変わることもあるんです。
たとえば、キャラクターの声真似をして読み聞かせたり、工作やお絵描きと組み合わせて取り入れたりするだけで、教材への関心がアップします。
- 子どもの「好き」に寄せると、自然と集中できる
- 学びが遊びの一部になると抵抗感が減る
- 親の工夫が、子どもにとっての楽しい体験につながる
僕の家では、教材の付録にミニカーやブロックを組み合わせて遊び感覚で取り組ませたことがあります。
それだけで、まったく興味を示さなかった内容にも夢中になる姿が見られました。
ちょっと視点を変えるだけで、教材が「楽しいもの」に変わる。
そんなきっかけを、ぜひおうちの中で作ってみてくださいね。
他の教材も検討する
どうしてもこどもちゃれんじが合わないと感じたら、他の教材を試してみるのも選択肢の一つです。
どんなに良い教材でも、すべての子どもにフィットするとは限りません。
大切なのは、その子の「楽しい!」「やってみたい!」という気持ちを引き出せるかどうかです。
最近は、通信教材やアプリ、おもちゃ型の知育教材など、選択肢が豊富です。
こどもちゃれんじと併用してもいいし、一度お休みして他のものに変えるのもOK。
- 子どもに合ったスタイルで学びを続けられる
- 飽きやすい子でも新鮮な刺激が得られる
- 教材へのモチベーションが再び高まる可能性がある
僕の知人には、こどもちゃれんじに飽きてしまったお子さんに、図鑑付きのアプリ教材を使い始めたら、毎日夢中になったという話もありました。
「教材を変える=あきらめる」ではありません。
むしろ、より合った形を探す前向きな行動として、気軽に考えてみてくださいね。
こどもちゃれんじを続けるべきかどうかの判断基準
「このまま続けるべきか、やめるべきか…」迷ったときに、親として判断するポイントはいくつかあります。
感情だけで判断するのではなく、子どもの反応や家庭の状況に応じて、冷静に見極めることが大切です。
子どもが楽しんでいれば基本問題なし
まず大前提として、子どもが楽しんで取り組んでいるなら、多少ついていけていなくても大きな心配は不要です。
理解が遅くても、興味を持って関わっているだけで十分意味があります。
学びのベースとなる「好奇心」や「やる気」が育っている証拠です。
- 楽しんでいれば自然と力がついていく
- 「やりたい!」という気持ちが学びの原動力になる
- 続けることで徐々に理解が追いつくことも多い
僕の子どもも、最初は内容を理解していない様子でしたが、毎月届くのを楽しみにしている姿を見ると、「それだけでも続ける価値があるな」と感じました。
成果がすぐに見えなくても、「楽しい」が続いているうちは、見守りながらゆっくり進めていきましょう。
親子のストレスが溜まってきたらやめるか検討すべき
子どもが教材を嫌がったり、親がイライラしてしまう日が続くようなら、一度立ち止まってみることも大切です。
「せっかくお金を払ってるのに」「ちゃんとやらせなきゃ」と思うほど、プレッシャーが増えて親子関係がギクシャクしてしまうこともあります。
毎日の生活がストレスだらけになるよりも、教材を休む・やめるという選択で心に余裕が生まれることもあるんです。
- 「やらなきゃ」という義務感が親にも子にも負担になる
- 怒りながらやる学習は逆効果になりやすい
- 一度休むことで、改めて教材の価値を見直せる
僕も一時期、毎日のように「やって!」と声をかけては、子どもが泣き出してしまう日が続いたことがありました。
そのとき思いきって数週間教材をお休みしたら、驚くほど気持ちが軽くなったんです。
教材よりも、親子の笑顔がいちばん。
ストレスを感じるようなら、一度リセットしてみましょう。
別のおもちゃでしか遊ばないなら別の教材を試してみる
こどもちゃれんじの付録やワークに全然興味を示さず、いつも同じおもちゃばかりで遊んでいる場合は、教材の内容が子どもに合っていない可能性があります。
興味がわかない教材は、どうしても後回しになってしまい、「やらないこと」への罪悪感だけが残ってしまうことも。
その子が今どんなことに関心を持っているのかに合わせて、より適した教材や学び方を見直すタイミングかもしれません。
- まったく使われない教材は親のストレスになる
- 興味のない内容は定着しにくく、効果が出にくい
- 子どもに合った学び方を見直すことも大切
僕のまわりでも、「毎回届いても封を開けずにそのまま放置…」という家庭がありました。
思い切って教材を変えたら、驚くほどスムーズに取り組めるようになったそうです。
「遊び=学び」の時期だからこそ、子どもが夢中になれる教材を選ぶことがいちばんの近道です。
まとめ
こどもちゃれんじについていけないと感じたとき、焦る気持ちはとてもよくわかります。
でも、その原因は子ども自身ではなく、「月齢差」や「発達の個人差」「教材との相性」といった、自然な要素が多いんです。
親子で無理なく続けていくためには、以下のような視点がとても大切になります。
- 今の発達段階に合わせて内容を調整する
- 無理にやらせず、子どもが楽しめる形に工夫する
- ストレスを感じるなら一度休んだり、他の教材を検討する
大切なのは「続けること」より、「その子に合った形で学びと関われているかどうか」です。
もし今つらいと感じているなら、一度立ち止まってOK。
親子で笑顔になれる方法を見つけて、また歩き出せばいいんです。
この記事が、あなたとお子さんにとって、より楽しい学びの時間を見つけるきっかけになれば嬉しいです。