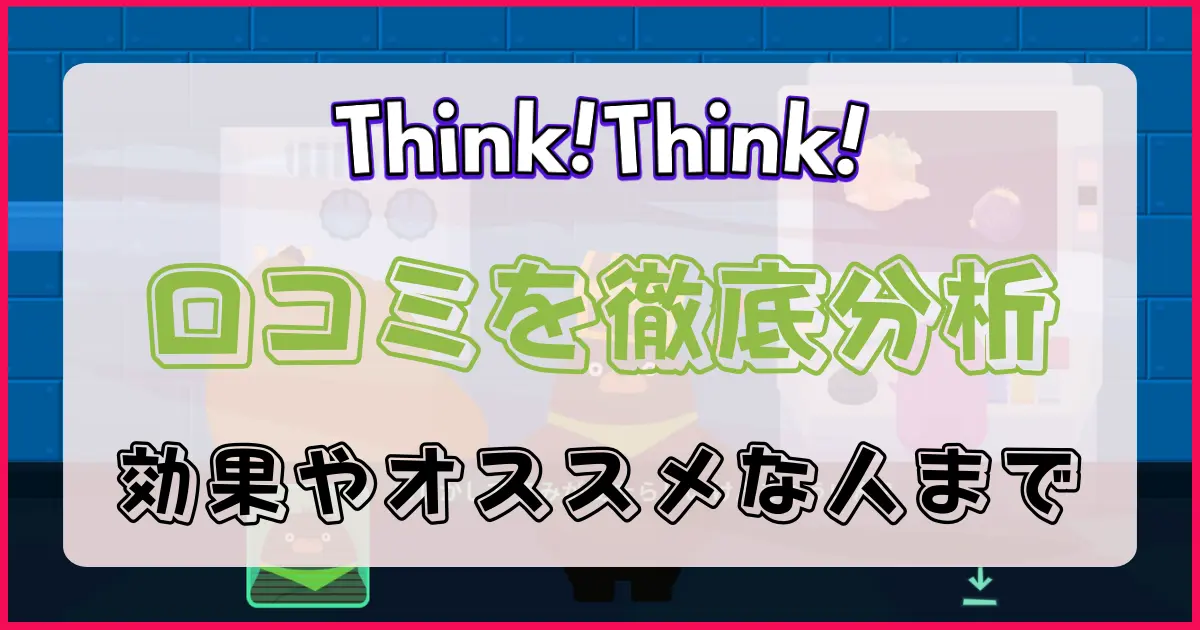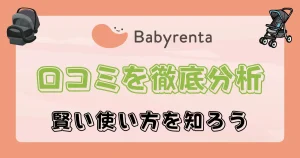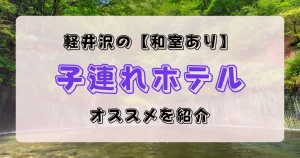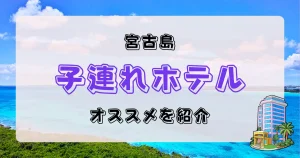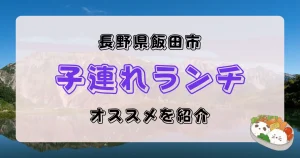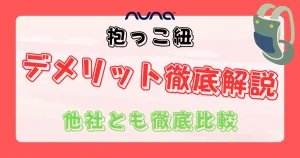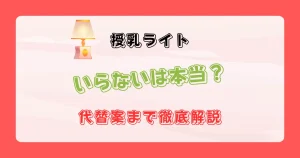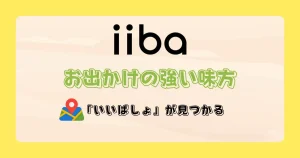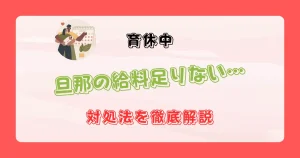- 知育アプリがありすぎて、どれを選べばいいか分からない…。
- シンクシンクのリアルな口コミや評判が知りたい。
- 本当に子どもの思考力アップに効果があるの?
- 料金プランやデメリットも正直に教えてほしい。
幼児期の知育アプリ選びについて、このようなお悩みはありませんか。
僕も5歳と3歳の息子を育てるパパとして、その気持ち、すごくよく分かります。
特に「シンクシンク(Think!Think!)」は、”思考力を伸ばす”というコンセプトが魅力的で、世界中で人気ですよね。
我が家でも長男が対象年齢に近づき、導入を検討し始めたのですが、やはり気になるのは実際の利用者の声。
「本当に効果があるの?」「悪い評判はない?」と、たくさん調べました。
この記事では、僕と同じようにシンクシンクに関心を持つパパママのために、ネット上の口コミや評判、そして公式情報を徹底的に分析。
よい口コミからわかるメリットはもちろん、悪い口コミから見えるデメリットや注意点、料金体系、期待できる効果まで、忖度なしで詳しく解説していきます。
この記事を読むことで、以下の点がクリアになりますよ。
- シンクシンクがどんな知育アプリなのか(特徴・対象年齢・問題内容)
- 実際に利用している人のリアルな口コミ・評判(良い点・悪い点とその対策)
- 期待できる効果(思考センス・算数基礎・IQへの影響など)
- 具体的なメリット・デメリット
- 料金プラン(スタンダード・プレミアム)の詳細と選び方
- よくある質問への回答(兄弟利用・解約・ワンダーボックスとの違い)
この記事を最後まで読めば、「シンクシンクが我が子に本当に合っているか」を自信を持って判断できるようになります。
知育アプリ選びで後悔しないために、ぜひ参考にしてくださいね。
きっと、お子さまの「考える楽しさ」を引き出すヒントが見つかるはずです。
まずはお気軽にアプリをダウンロードして、どんな問題があるか覗いてみるのもオススメですよ。
まず結論!シンクシンクはこんな人におすすめ
数ある知育アプリの中からシンクシンクを選ぶべきか、迷いますよね。
最初に結論からお伝えすると、シンクシンクは以下のようなご家庭に特にオススメできるアプリといえます。
楽しみながら思考力を伸ばしたい家庭
シンクシンク最大の魅力は、子どもがゲーム感覚で夢中になって取り組める点です。
「勉強」という堅苦しさがなく、遊びの延長線上で自然と「考える楽しさ」に触れることができます。
「うちの子、勉強は嫌がるけどゲームなら…」というご家庭や、学習へのハードルを下げたい場合にぴったりです。
子どもが「楽しい!」と感じる没頭体験を重視しており、知識の詰め込みではなく、学ぶこと自体の面白さを知るきっかけになります。
- 遊び感覚で学べる: 子どもが自ら進んで取り組みやすい。
- 学習意欲の向上: 勉強への抵抗感を減らし、知的好奇心を刺激する。
- 非認知能力への好影響: 自己肯定感や挑戦する意欲も育む。
知らず知らずのうちに思考力が鍛えられるので、親子で楽しみながら成長を実感できるでしょう。
小学校低学年までの算数・図形の基礎固めをしたい家庭
シンクシンクは、特に小学校低学年までに大きく伸びるといわれる「空間認識」「平面認識」といった能力を養う問題が豊富です。
これらは算数、特に図形問題の理解に不可欠な力であり、将来的な学力の土台となります。
パズルや迷路、立体図形の問題を通して、直感的にこれらの感覚を身につけることが可能です。
| 育成を目指す主な力 | 関連する問題例 |
|---|---|
| 空間認識 | 立体図形の回転、展開図、積み木など |
| 平面認識 | 図形の合成・分割、点つなぎ、タイル敷き詰めなど |
| 試行錯誤 | 迷路、論理パズル、条件整理など |
計算ドリルだけでは養いにくい「図形センス」や「イメージ力」を、楽しみながら効果的に鍛えたいご家庭にオススメです。
算数への苦手意識を持つ前に、図形に親しむよい機会になります。
手頃な価格で質の高い知育アプリを探している家庭
知育アプリや通信教育は数多くありますが、料金は気になるところですよね。
シンクシンクは、有料プランが月額450円(スタンダードコース)または980円(プレミアムコース)と、他の有料知育サービスと比べて比較的安価な設定になっています。
この価格で、算数オリンピックの問題制作などにも携わる教育のプロが作成した、120種類・20,000問以上の質の高い問題に取り組めるのは大きな魅力です。
- コストパフォーマンス: 低価格で高品質な思考力トレーニングが可能。
- 導入しやすい: 初めての有料知育アプリとしても試しやすい価格帯。
- 継続しやすい: 家計への負担が少なく、長く続けやすい。
「まずは手軽に思考力を伸ばすアプリを試してみたい」というご家庭にとって、シンクシンクは非常に有力な選択肢となるでしょう。
アプリの利用時間に制限を設けたい家庭
子どもが夢中になると、つい長時間アプリで遊んでしまいがち…そんな心配はありませんか?
シンクシンクは、1日のプレイ時間が最大10分程度(1回約3分×3回)に制限されています。
この時間制限は、子どもの集中力を維持し、遊びすぎを防ぐための工夫であり、保護者にとっては大きな安心材料です。
- 依存防止: ダラダラと長時間プレイするのを防ぐ。
- 集中力UP: 短時間だからこそ、集中して問題に取り組める。
- メリハリ: アプリの時間と他の遊びや学習の時間を区別しやすい。
- 保護者の安心: 目を離していても、自動で終了するので安心感が強い。
「アプリは使わせたいけど、時間はきちんと管理したい」と考えているご家庭には、シンクシンクの仕組みは非常に適しています。
「あと1回だけね!」といった声かけもしやすく、ルール作りにも役立ちます。
そもそもシンクシンク(Think!Think!)とは?
シンクシンク(Think!Think!)は、世界150ヶ国・300万人以上の子どもたちに利用されている人気の知育アプリです。
一体どのような特徴を持つアプリなのか、基本情報を確認していきましょう。
花まる学習会メソッドから生まれた「思考センス」育成アプリ
シンクシンクは、「花まる学習会」を母体とするワンダーファイ株式会社(旧ワンダーラボ)によって開発されました。
花まる学習会は、「メシが食える大人に育てる」という理念のもと、自ら考える力を重視した教育で知られています。
そのメソッドを凝縮し、アプリという形で提供しているのがシンクシンクです。
単なる知識や計算力の習得ではなく、物事を多角的に捉え、粘り強く考える「思考センス」を育成することに特化しています。
- 教育理念: 「考えること」自体の楽しさを体験し、学ぶ意欲を引き出す。
- 育成目標: 学力の土台となる「思考センス」(空間認識、平面認識、試行錯誤など)を養う。
- 開発元: 教育実績のある花まる学習会グループなので信頼性が高い。
この「思考センス」は、算数だけでなく、あらゆる学習や問題解決の基盤となる重要な力といえますね。
対象年齢は4歳~10歳がコアターゲット
シンクシンクの主な対象年齢は4歳から10歳とされています。
これは、空間認識能力などが大きく伸びる時期と重なります。
問題は直感的に操作できるものが多く、文字が読めなくても楽しめるように工夫されています。
年少さんから小学校中学年くらいまで、幅広い年齢の子どもがそれぞれのレベルに合わせて思考力を鍛えることが可能です。
| 年齢 | 主な発達段階とシンクシンクの関わり |
|---|---|
| 4歳~6歳 (幼児) | 図形やパズルに親しみ、空間認識や試行錯誤の基礎を楽しく学ぶ。直感的な操作でOK。 |
| 7歳~10歳 (小学生) | より複雑な問題に挑戦し、論理的思考力や問題解決能力を伸ばす。算数の学習にも繋がる。 |
もちろん、10歳以上の子どもや、脳トレとして大人が楽しむことも可能です。
アプリ内の問題はレベル分けされているため、年齢や発達段階に合わせて無理なくステップアップできます。
120種類以上の多彩な問題で飽きさせない工夫
シンクシンクには、パズル、迷路、図形問題など、120種類以上、累計20,000問以上もの豊富な問題が収録されています。
これらの問題は、算数オリンピックや世界算数への問題提供実績を持つ専門チームによって制作されており、質が高いのが特徴です。
毎日違う種類の問題が出題されるため、子どもを飽きさせません。
- 問題の多様性: パズル、迷路、図形、論理など様々なジャンル。
- 質の高さ: 教育のプロが作成した良問揃い。
- 飽きない仕組み: 毎日違う問題に挑戦できる。
- インタラクティブ性: アプリならではの動きのある問題で理解を助ける。(例: 展開図が立体になるアニメーション)
様々な角度から思考力を刺激することで、偏りなくバランスのよい「思考センス」を育むことを目指しています。
「今日はどんな問題かな?」と、子どもが毎日ワクワクしながらアプリを開くきっかけにもなりますね。
1日10分の短時間集中型で続けやすい
シンクシンクの大きな特徴のひとつが、1日のプレイ時間が約10分(1回約3分×最大3ゲーム)に制限されていることです。
幼児や低学年の子どもが集中力を保てる時間に設定されており、「もっとやりたい!」という気持ちで終われるように工夫されています。
この時間制限があることで、保護者は「いつの間にか長時間遊んでいた…」という心配をする必要がありません。
- 集中力の維持: 子どもの集中力が途切れにくい最適な時間設定。
- 習慣化しやすい: 短時間なので毎日のスキマ時間に取り組みやすい。
- 保護者の負担減: 時間管理の手間が省け、安心して見守れる。
- 柔軟な設定: プレイ回数は「1日3回」または「1週間21回」から選択可能。
忙しい毎日の中でも、無理なく学習習慣を身につけられる点が、多くの家庭で支持されている理由のひとつといえるでしょう。
手軽に始められるのも嬉しいポイントですね。
シンクシンクの口コミ・評判を徹底分析!利用者のリアルな声
アプリを選ぶ上で、やはり一番気になるのは実際に使っている人の声ですよね。
ここでは、シンクシンクに関する様々な口コミや評判を集め、よい点と気になる点を分析しました。
良い口コミ・評判:子どもが夢中になる!思考力が伸びる実感
シンクシンクの良い口コミとして、最も多く見られたのが「子どもが夢中になる」「楽しんでやっている」という声です。
ゲーム性が高く、直感的な操作で遊べるため、子どもが自ら進んで取り組みやすいようです。
また、「考える力がついてきた」「図形問題が得意になった」といった、効果を実感する声も多数ありました。
- 「とにかく子どもがハマる! 自分から『シンクシンクやる!』と言ってくる」
- 「ゲームみたいで楽しいらしく、勉強している感覚がないのがよい」
- 「図形を組み合わせたり、立体を考えたりする力が伸びた気がする」
- 「1日10分という制限が絶妙で、親としても安心できる」
- 「最初はできなかった問題がクリアできるようになると、すごく嬉しそう」
- 「大人でも『おっ』と唸る問題があり、親子で一緒に楽しめる」
「楽しさ」と「学び」が両立している点が、シンクシンクが高く評価される大きな理由といえます。
子どもの知的好奇心を引き出し、自発的な学びを促す効果が期待できそうですね。
悪い口コミ・評判:物足りなさや飽きも?対策と合わせて解説
一方で、シンクシンクには気になる口コミや、デメリットと感じられる点もいくつか見られました。
「問題が簡単すぎる・物足りない」という声や、「だんだん飽きてきた」という意見です。
また、時間制限が逆にもっとやりたい子どものフラストレーションになる可能性も指摘されています。
これらの点について、考えられる対策と合わせて見ていきましょう。
- 物足りなさ・簡単すぎる:
→ 対策: プレミアムコースへの変更を検討する。より高度な問題に挑戦できる。
→ 対策: シンクシンクは基礎固めと割り切り、他の教材と組み合わせる。 - 飽きてきた・難しくてやらない:
→ 対策: オリンピコ(ランキングイベント)などでモチベーションを刺激する。
→ 対策: 無理強いせず、一時的に休んだり、プレイ頻度を調整する(週21回設定など)。
→ 対策: 親子で一緒に挑戦したり、できたら褒めるなど声かけを工夫する。 - 1日10分では足りない:
→ 対策: 時間制限の意図(集中力維持、依存防止)を子どもに説明する。
→ 対策: 「もっとやりたい」気持ちを、他の知的な活動(読書、ボードゲーム、公式ブックなど)に繋げる。
どのような教材にも、合う合わないはあります。
悪い口コミも参考に、お子さんの性格や学習状況に合わせて使い方を工夫したり、コースを見直したりすることが大切ですね。
シンクシンクの効果は?思考力・学力への影響を検証
シンクシンクを使うことで、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか?
口コミだけでなく、アプリの目的や研究データなども元に、その効果を詳しく見ていきましょう。
思考センス(空間認識・平面認識・試行錯誤)が伸びる
シンクシンクが最も重視しているのは、知識の暗記ではなく、「思考センス」を育むことです。
これは、物事を理解し、問題を解決していくための土台となる力です。
特に、以下の3つの力を伸ばすことに重点が置かれています。
| 思考センス | どのような力か | シンクシンクでの関わり |
|---|---|---|
| 空間認識 | 物の位置関係や形を立体的に捉える力 | 展開図、積み木、影の問題などで育成 |
| 平面認識 | 図形を平面上で正しく捉える力 | 図形の合成・分割、タイル問題などで育成 |
| 試行錯誤 | 粘り強く様々な方法を試す力 | 迷路、論理パズル、条件整理問題などで育成 |
これらの力は、10歳頃までに大きく伸びるといわれており、幼児期から鍛えることが効果的です。
シンクシンクは、これらの思考センスを、ゲームを通して遊びながら自然に身につけられるように設計されています。
算数(特に図形問題)への基礎力が身につく
シンクシンクで養われる思考センス、特に空間認識能力や平面認識能力は、算数の学力、とりわけ図形問題の理解に直結します。
小学校の算数では、立体の体積や展開図、図形の角度や面積など、頭の中でイメージする力が求められる場面が多くあります。
シンクシンクの問題に取り組むことで、このような抽象的な概念を理解するための素地が養われます。
- 図形への抵抗感をなくす: 遊び感覚で図形に触れることで、苦手意識を防ぐ。
- イメージ力の向上: 頭の中で図形を操作する力が身につく。
- 問題解決能力の育成: 図形問題だけでなく、文章題などへの応用力も期待できる。
計算だけでなく、図形や論理的思考を含む算数全体の基礎力をバランスよく伸ばしたい場合に、シンクシンクは効果的なツールといえるでしょう。
IQスコア向上や非認知能力への効果も?
シンクシンクの効果は、思考力や算数だけにとどまらない可能性が示唆されています。
開発元のワンダーファイがカンボジアで行った1,500人規模の実証実験では、シンクシンクを利用した児童の算数およびIQの偏差値が有意に向上したという結果が報告されています。
具体的には、10ヶ月間の利用でIQ(田中B式)偏差値が最大7.17ポイント向上したとのことです。
- IQへの影響: 実証実験ではポジティブな結果が示されている。
- 非認知能力への影響: 学習意欲(内発的動機づけ)や自己肯定感(自尊感情)にもよい影響が見られた。
- 注意点: カンボジアと日本の教育環境は異なるため、日本の子どもに対するIQ向上効果を同等に期待できるかは慎重な判断が必要。
IQスコアへの直接的な効果は環境要因も絡むため断言はできませんが、シンクシンクが「考えることの楽しさ」を引き出し、結果として学習意欲や自信といった非認知能力によい影響を与える可能性は十分に考えられますね。
中学受験の準備にも役立つ?図形問題対策として
「シンクシンクは中学受験にも役立ちますか?」という質問もよく聞かれます。
結論からいうと、中学受験の算数で求められる思考力、特に図形問題や空間認識能力の基礎固めとして役立つ可能性は高いといえます。
中学入試の算数では、単なる計算力だけでなく、複雑な図形を正確に把握したり、多角的な視点から問題を解きほぐしたりする力が求められます。
- 図形・空間認識の強化: 入試頻出分野の基礎を楽しく養える。
- 思考の柔軟性: 様々なパターンの問題に触れることで、発想力が鍛えられる。
- プレミアムコース: より発展的で、受験算数に繋がるような問題も含まれる。
ただし、シンクシンクだけで中学受験対策が完結するわけではありません。
あくまでも低学年からの基礎固めや、思考力を楽しく鍛えるツールとして捉え、必要に応じて塾や他の教材と組み合わせることが重要です。
特に、受験を意識する場合はプレミアムコースの利用を検討するとよいでしょう。
シンクシンクを利用するメリット
これまでの情報や口コミを踏まえ、シンクシンクを利用するメリットを整理してみましょう。
多くの家庭で支持される理由が見えてきます。
ゲーム感覚で楽しく学べる
最大のメリットは、やはり子どもが「楽しい!」と感じながら学べる点です。
カラフルな画面、動きのある演出、クリアした時の達成感など、ゲームのような要素が満載。
勉強というより「遊び」に近い感覚で取り組めるため、学習に対するネガティブなイメージを持つことなく、自然と机に向かう習慣が身につきます。
- 自発的な取り組み: 親が促さなくても、子どもが自分からやりたがる。
- 学習意欲の向上: 「わかる」「できる」喜びが、次の学びへの意欲に繋がる。
- ポジティブな学習体験: 幼少期に「学ぶことは楽しい」という原体験ができる。
この「楽しさ」が、継続利用の鍵となり、結果的に思考力の向上に繋がっていくのですね。
思考力・算数の基礎(特に図形)が自然に身につく
シンクシンクは、学力の土台となる「思考センス」(空間認識、平面認識、試行錯誤など)を効果的に育成できるように設計されています。
特に、図形問題が豊富に含まれており、遊びながら空間把握能力や図形センスを自然に養うことが可能です。
これらは、小学校の算数、さらにはその先の数学や理科の学習においても非常に重要な力となります。
| シンクシンクで鍛えられる力 | 将来の学習への繋がり |
|---|---|
| 空間認識能力 | 算数(立体図形)、理科(天体、分子構造)、地図読みなど |
| 平面認識能力 | 算数(平面図形、面積、角度)、図画工作など |
| 試行錯誤力 | 算数(文章題)、理科(実験)、プログラミング的思考など |
目先の点数だけでなく、将来にわたって役立つ本質的な「考える力」の基礎を、幼児期から無理なく築ける点は大きなメリットといえるでしょう。
1日10分で集中力が続き、負担なく継続しやすい
1日のプレイ時間が約10分に制限されていることも、シンクシンクの大きなメリットです。
幼児や低学年の子どもが集中力を保てる時間は短いですが、シンクシンクなら無理なく集中して取り組めます。
また、短時間で終わるため、忙しい毎日の中でも習慣化しやすく、親子双方にとって負担が少ないのが特徴です。
- 高い集中力: 短時間で質の高い学びが期待できる。
- 習慣化: 「毎日10分」という手軽さが継続に繋がる。
- 負担軽減: 親が見守る時間も短く済み、共働き家庭などにも優しい。
「少しの時間でも、毎日コツコツ考える習慣をつけさせたい」というニーズに、うまく応えてくれるシステムといえますね。
時間制限でやりすぎを防げる
デジタルデバイスを使った学習で、保護者が最も心配することのひとつが「やりすぎ」や「依存」ではないでしょうか。
シンクシンクは、システム自体に1日10分程度の時間制限が組み込まれているため、その心配がありません。
子どもが夢中になっていても、時間が来れば自動的に終了します。
- 保護者の安心感: 時間管理をアプリに任せられる。
- メリハリのある生活: アプリの時間と他の時間の区切りがつけやすい。
- 適切な距離感: デジタルデバイスとの健全な付き合い方を促す。
「つい、もうちょっと…」がなく、「また明日ね!」と自然に切り替えられるのは、親子双方にとって精神的な負担が少ないといえます。
この安心感は、デジタル教材を選ぶ上で非常に大きなメリットです。
手頃な料金設定(他の教材と比較して安価)
シンクシンクの有料プランは、スタンダードコースが月額450円、プレミアムコースでも月額980円と、他の多くの有料知育アプリや通信教育と比較して非常にリーズナブルです。
家計への負担が少なく、気軽に始められて続けやすい価格設定は、大きなメリットといえるでしょう。
| コース | 月額料金 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| スタンダード | 450円 | 基本的な思考力問題、最大3ユーザー |
| プレミアム | 980円 | スタンダード+高度な問題、最大6ユーザー |
この価格で、質の高い思考力トレーニングができるのは、コストパフォーマンスが非常に高いといえます。
「まずは試してみたい」という家庭や、他の習い事と併用したい家庭にも導入しやすいですね。
アプリだけで完結し、手軽に始められる
シンクシンクは、スマートフォンやタブレットがあれば、すぐに始められる手軽さも魅力です。
特別な教材やキットが送られてくるわけではないので、場所を取らず、管理の手間もかかりません。
アプリをダウンロードし、コースを選択すれば、その日からすぐに思考力トレーニングを開始できます。
- 準備不要: スマホ・タブレットがあればOK。
- 場所を取らない: 教材の収納場所に困らない。
- スキマ時間に活用: 外出先や移動中でも手軽に取り組める。
- 管理が楽: 教材の紛失や破損の心配がない。
思い立ったらすぐに始められる手軽さと、場所を選せずに利用できる利便性は、忙しい現代のライフスタイルにマッチしていますね。
教育のプロ制作による質の高い問題
シンクシンクの問題は、花まる学習会グループのワンダーファイに所属する、教育のプロフェッショナルチームによって制作されています。
このチームは、算数オリンピックや世界算数への問題提供実績もあり、その質の高さは折り紙付きです。
単に面白いだけでなく、子どもの思考力を効果的に引き出し、伸ばすように緻密に設計されています。
- 教育的知見: 子どもの発達段階や認知プロセスに基づいた問題設計。
- 良問揃い: 思考力を多角的に刺激する、練られた問題。
- 信頼性: 教育実績のある企業が開発している安心感。
「ただ遊んでいるだけに見えても、実はしっかり考えさせられている」というのが、シンクシンクの問題のすごいところ。
質の高い問題に触れる経験は、子どもの知的な成長にとって非常に価値があります。
操作が直感的で子どもだけでも取り組みやすい
シンクシンクのアプリは、子どもがひとりで操作しやすいように、直感的なインターフェースで設計されています。
文字を読む必要が少ない問題も多く、タップやスワイプといった簡単な操作で進められるため、まだ文字に慣れていない幼児でも楽しめます。
保護者が常に隣についていなくても、子どもが自分で考えて進められる点はメリットといえるでしょう。
- 簡単な操作: 幼児でも迷わず使えるデザイン。
- 自立性の促進: 子どもが自分で考えて進める体験ができる。
- 保護者の負担軽減: 操作方法を細かく教える必要が少ない。
もちろん、親子で一緒に挑戦するのも楽しいですが、子どもが「自分でできた!」という達成感を味わいやすいように作られています。
この手軽さも、シンクシンクが多くの家庭で選ばれる理由のひとつです。
まずはアプリをインストールして、お子さんと一緒に触ってみるのが一番分かりやすいかもしれませんね。
シンクシンクを利用するデメリット・注意点
多くのメリットがある一方で、シンクシンクにはいくつか注意しておきたい点や、デメリットと感じられる可能性のある部分もあります。
導入後に「思っていたのと違った…」とならないよう、事前に確認しておきましょう。
学習領域が思考力・算数の一部(図形など)に限定される
シンクシンクは「思考センス」の育成に特化しており、特に空間認識や図形問題に強みを持つアプリです。
しかし、その反面、学べる領域が限定的である点は認識しておく必要があります。
例えば、計算練習に特化したアプリや、プログラミング、アートなど幅広いSTEAM分野を扱う教材と比較すると、カバー範囲は狭くなります。
- 計算練習: 計算力を集中的に鍛えたい場合は、他のアプリ(例: トドさんすうなど)の併用も検討。
- 国語・英語など: 他教科の学習機能はない。
- プログラミング・アート: これらの分野を学びたい場合は、ワンダーボックスなど他の教材が適している可能性。
シンクシンクはあくまで「思考力(特に算数・図形関連)」を鍛えるツールと割り切り、必要に応じて他の学習と組み合わせることが大切です。
アプリのみで紙教材や物理的なキットはない
シンクシンクは、学習がアプリ内で完結するサービスです。
手軽である反面、紙のドリルやワークブック、あるいはワンダーボックスのような物理的なキットを使った学習を好む家庭には、物足りなく感じるかもしれません。
画面上での操作だけでなく、実際に手を動かして学ぶ体験も重視したい場合は、注意が必要です。
- 学習形式: デジタル画面での学習が中心となる。
- 手書き学習: 鉛筆を持って書く練習にはならない。
- 実体験: 物理的な教材を使った試行錯誤や創造活動はできない。(公式ブックは別途販売あり)
とはいえ、アプリならではのインタラクティブな動きは、紙媒体では難しい理解を助ける側面もあります。
お子さんの特性や、どのような学習体験をさせたいかに合わせて検討しましょう。
子どもによっては飽きやすい、難易度でつまずく可能性がある
「子どもが夢中になる」という声が多い一方で、「途中で飽きてしまった」「難易度が上がったらやらなくなった」という口コミも存在します。
毎日違う問題が出るとはいえ、基本的なゲームの種類は限られているため、お子さんの性格によってはマンネリを感じてしまう可能性はあります。
また、思考力を鍛えるアプリなので、当然ながら難しい問題も出てきます。そこでつまずいて、やる気を失ってしまうケースもあるようです。
- 継続の個人差: 全ての子どもが必ずしも長くハマるとは限らない。
- 難易度への対応: つまずいた時のフォローや声かけが大切になる。
- 同じ問題への再挑戦不可: 特定の問題を繰り返し練習したい場合には不向きな面も。
飽きさせないための工夫として、親子で一緒に挑戦したり、目標を設定したり、アプリ内のイベント(オリンピコなど)を活用したりするのもよいかもしれません。
継続が難しい場合は、無理強いせず、一度お休みするのもひとつの方法です。
時間制限が物足りないと感じる子もいる
1日10分という時間制限は、やりすぎを防ぐメリットがある一方で、熱中している子どもにとっては「もっとやりたいのに!」というフラストレーションの原因になる可能性もあります。
特に、集中して問題に取り組んでいる最中に時間切れになると、不満を感じてしまう子もいるでしょう。
この点は、メリットと表裏一体のデメリットといえます。
- 子どもの欲求: もっと続けたいという気持ちに応えられない場合がある。
- 集中の中断: 「キリの良いところまでやりたい」ができない可能性がある。
- 声かけの必要性: 時間制限の意図を伝え、納得させる工夫が必要になることも。
「もっとやりたい」という気持ちは、学習意欲の表れでもあります。
そのエネルギーを、シンクシンクの公式ブックや、他の知的な遊び、学習に向けるなど、うまく誘導してあげることが大切かもしれませんね。
シンクシンクの料金プラン
シンクシンクを始めるにあたって、料金プランは重要な検討事項です。
現在提供されている有料コースの内容と料金、注意点などを詳しく解説します。
【注意】シンクシンクに無料プランは現在なし
まず重要な点として、現在シンクシンクには完全無料のプランはありません。
過去には一部機能を無料で試せる期間やバージョンがあったようですが、現在は有料のサブスクリプションモデルとなっています。
アプリのダウンロード自体は無料ですが、問題に取り組むためにはいずれかの有料コースへの登録が必要です。
- 無料利用不可: アプリダウンロードは無料だが、プレイには有料登録が必須。
- 過去情報に注意: 「無料でできる」という古い情報に惑わされないように。
- 体験期間: (※2025年4月現在、公式情報では明確な無料体験期間の記載は見当たりませんが、アプリ内で確認が必要です。過去にはキャンペーン等で提供されていた可能性あり)
利用を検討する際は、必ず有料コースへの登録が必要になる点を理解しておきましょう。
スタンダードコース:月額450円|基本の思考力を育む
スタンダードコースは、シンクシンクの基本的な思考力問題に取り組めるプランです。
月額450円という手頃な価格で、シンクシンクの魅力を十分に体験できます。
初めてシンクシンクを利用する家庭や、まずは基本的な思考力を楽しく養いたいという場合にオススメです。
- 月額料金: 450円
- ユーザー数: 最大3人まで登録可能
- プレイ回数: 1日3回 または 週21回
- コンテンツ: 基本的な思考力問題(空間認識、平面認識、試行錯誤、論理性、数的感覚など)100種類以上
- 対象: シンクシンク入門、家族での利用、基礎的な思考力育成
基本的な思考力を養うには十分な内容ですが、より高度な問題に挑戦したい場合は、プレミアムコースを検討することになります。
プレミアムコース:月額980円|より高度な問題に挑戦
プレミアムコースは、スタンダードコースの内容に加えて、さらに高度な思考力が求められる問題に挑戦できる上位プランです。
月額980円で、よりハイレベルな思考力を目指す家庭や、中学受験を視野に入れている家庭に適しています。
登録できるユーザー数も多く、兄弟が多い家庭にも便利です。
- 月額料金: 980円
- ユーザー数: 最大6人まで登録可能
- プレイ回数: 1日3回 または 週21回
- コンテンツ: スタンダードコースの全内容 + より高度な思考力問題(発展レベル、抽象的な立体図形など)
- 対象: ハイレベルな思考力育成、中学受験準備、兄弟での利用
スタンダードコースで物足りなさを感じた場合や、より思考力を深めたい場合に、プレミアムコースへのアップグレードを検討するとよいでしょう。
兄弟での利用は可能?ユーザー登録数について
シンクシンクは、ひとつの契約で複数のユーザー(子ども)を登録して利用することが可能です。
コースによって登録できる最大人数が異なります。
| コース | 最大ユーザー登録数 |
|---|---|
| スタンダードコース | 3人 |
| プレミアムコース | 6人 |
兄弟姉妹それぞれのアカウントを作成し、個々の進捗状況に合わせてプレイできます。
例えば、スタンダードコースなら3人兄弟まで、プレミアムコースなら6人兄弟まで対応可能です。
追加料金なしで兄弟一緒に使えるのは、非常に経済的で嬉しいポイントですね。
支払い方法と注意点
シンクシンクの有料コースの支払い(サブスクリプション登録)は、アプリをダウンロードしたプラットフォームを通じて行われます。
具体的には、App Store(Apple ID経由)、Google Play ストア(Googleアカウント経由)、Amazon Appstore(Amazonアカウント経由)のいずれかになります。
支払い方法や請求のタイミングは、各プラットフォームのルールに従います。
- プラットフォーム決済: アプリ内課金の形式をとる。
- 契約の紐づけ: 有料コースの契約情報は、最初に購入手続きを行ったアプリストアのアカウントに紐づく。
- 別OS端末での利用: 例えばAndroidで購入した契約をiPadで使いたい場合、一度解約してiPadのApp Storeで再購入が必要になる。
- 解約手続き: 各アプリストアのサブスクリプション管理画面から行う必要がある。
特に、契約情報が購入時のストアアカウントに紐づく点は少し分かりにくいかもしれません。
機種変更や利用端末の変更を考えている場合は、事前に公式FAQなどで確認しておくと安心です。
シンクシンクに関するよくある質問(FAQ)
シンクシンクについて、多くの保護者の方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。
気になる疑問をここでスッキリ解消しましょう。
Q. 兄弟で使えますか?何人まで登録できますか?
A. はい、ひとつの契約で兄弟姉妹での利用が可能です。
コースによって登録できる最大人数が異なります。
| コース | 最大ユーザー登録数 |
|---|---|
| スタンダードコース | 3人 |
| プレミアムコース | 6人 |
それぞれのお子さま用のアカウントを作成し、個別のデータでプレイできます。
追加料金はかかりません。
Q. 解約はいつでもできますか?
A. はい、有料コースの解約はいつでも可能です。
ただし、手続きはシンクシンクのアプリ内ではなく、契約時に利用したアプリストア(App Store, Google Play ストア, Amazon Appstore)のサブスクリプション管理画面から行う必要があります。
- 手続き場所: 各アプリストアで行う。
- 更新タイミング: 次回の請求日(更新日)の24時間前までに解約手続きを完了させないと、自動的に更新され課金が発生します。
- 払い戻し: 原則として、一度支払われた利用料金の払い戻しはありません。
解約を希望する場合は、早めに各アプリストアの管理画面を確認し、手続きを進めましょう。
Q. ワンダーボックスとの違いは?
A. シンクシンクとワンダーボックスは、どちらも同じワンダーファイ社が提供するサービスですが、内容や対象が異なります。
主な違いは以下の通りです。
| 項目 | シンクシンク (Think!Think!) | ワンダーボックス (WonderBox) |
|---|---|---|
| 主な焦点 | 思考センス育成 (特に算数・図形) | 総合的なSTEAM教育 (科学, 技術, 工学, アート, 数学) |
| 提供形式 | アプリのみ | アプリ + 毎月届く物理キット |
| 料金 (月額目安) | 450円 / 980円 | 約3,700円~4,200円 |
| 学習領域 | 限定的 (思考力中心) | 広範 (プログラミング、アート、実験なども含む) |
| データ引継ぎ | 不可 (シンクシンク→ワンダーボックス) | – |
簡単にいうと、シンクシンクは「思考力に特化した手軽なアプリ」、ワンダーボックスは「デジタルとアナログを融合させた総合STEAM教材」といえます。
思考力の基礎固めを手軽に始めたいならシンクシンク、より幅広い分野を体験的に学びたいならワンダーボックスがオススメです。
重要な注意点として、シンクシンクからワンダーボックスに移行する際、プレイデータは引き継がれません。
まとめ
この記事では、人気の知育アプリ「シンクシンク(Think!Think!)」について、口コミや評判、期待できる効果、メリット・デメリット、料金プランなどを徹底的に分析・解説しました。
シンクシンクは、「考えることの楽しさ」を教えてくれる、非常によくできた知育アプリです。
特に、以下の点に魅力を感じるご家庭には、自信を持ってオススメできます。
- ゲーム感覚で楽しく思考力(特に空間認識・図形)を伸ばしたい。
- 1日10分という時間制限で、メリハリをつけてアプリを利用させたい。
- 手頃な価格で、質の高い知育アプリを始めたい。
- アプリだけで完結する手軽な学習がよい。
もちろん、学習領域が限定的であることや、飽きる可能性、時間制限への不満といったデメリットも存在します。
しかし、それらを理解した上で、お子さんの性格や学習目的に合わせて活用すれば、子どもの知的な成長を力強くサポートしてくれるツールとなるでしょう。
僕自身、4歳の長男もまさにシンクシンクのコアターゲット。
この記事を書きながら、「これはぜひ試してみたい!」と改めて感じました。
遊びながら、将来に役立つ「考える力」の土台を作れるなんて、素晴らしいですよね。
もし、少しでもシンクシンクに興味を持たれたなら、まずはアプリをダウンロードしてみてはいかがでしょうか。
お子さんがどんな反応を示すか、実際に触れてみるのが一番です。
きっと、目を輝かせて問題に取り組むお子さんの姿が見られるはずですよ。
この記事が、あなたの知育アプリ選びの一助となれば幸いです。