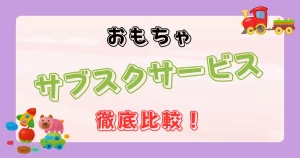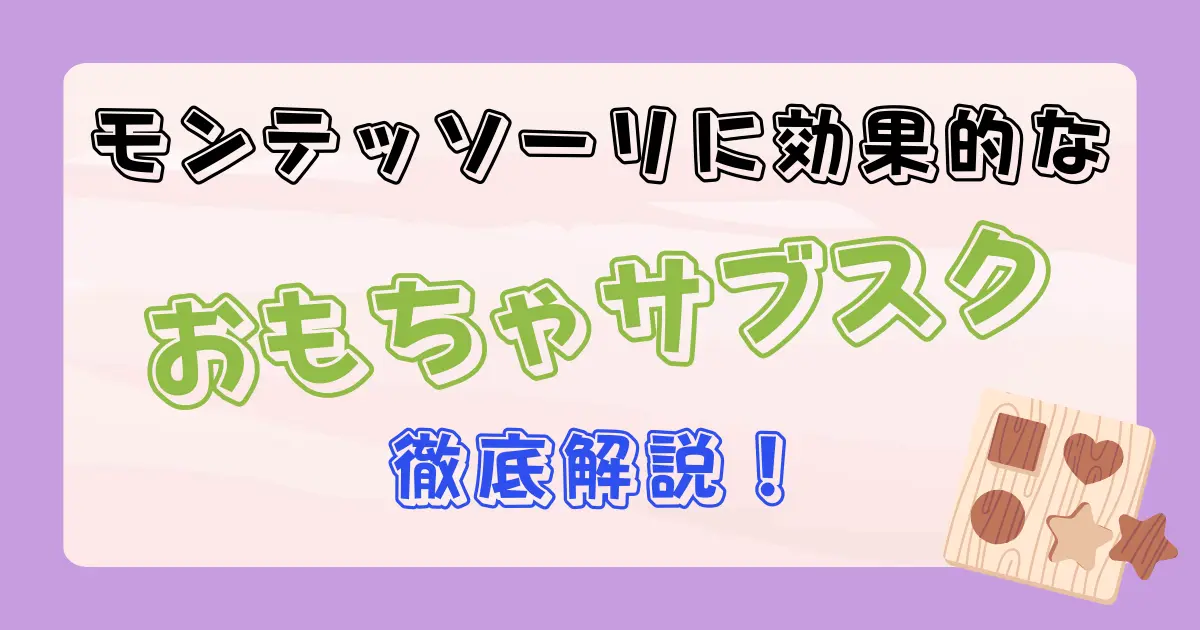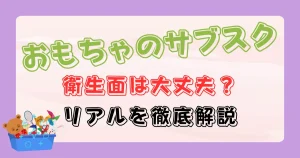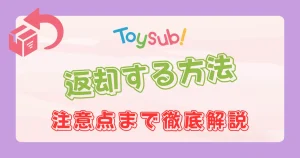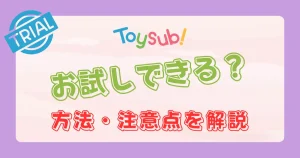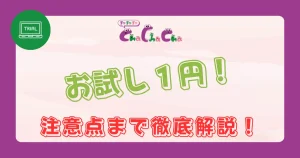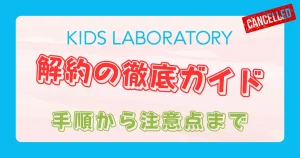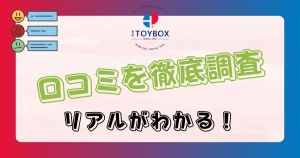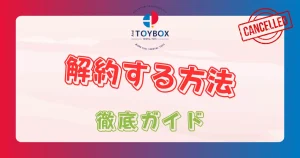「モンテッソーリ教育ってよく聞くけど、実際どんなことをするの?」
「うちの子にも合うのかな?」と感じているパパママは多いと思います。
僕も最初は同じように悩みました。
知育にいいって聞くけど、専門的で難しそう。
でも、モンテッソーリの考えをゆるっと取り入れていくことで、子どもがどんどん自分でできることが増えて驚きました。
この記事では、そんなモンテッソーリ教育の基本から、自宅での実践方法、
そして忙しい家庭でも手軽に取り入れられる「おもちゃのサブスク」活用法までをしっかり紹介します。
特に注目してほしいのは、モンテッソーリの理念に合ったおもちゃを定期的に届けてくれるサービスの選び方と、2025年最新版のオススメ7選。
- モンテッソーリ教育の基本とメリットがわかる
- おもちゃサブスクとの相性や選び方が明確になる
- おすすめのサービスを比較しやすい
- 家庭での実践ポイントも紹介
この記事を読めば、「うちの子にどんなおもちゃが合うのか」「どのサービスを選べばいいのか」がハッキリします。
- 子どもの自立心と集中力を育てられる
- サブスクでムダなくおもちゃ選びができる
- 親の悩みや手間もぐっと減る
僕自身も、5歳と3歳の兄弟を育てながら試行錯誤してきました。
この記事が、パパママたちの「おうちモンテ」ライフの第一歩になればうれしいです。
トイサブは、おもちゃのサブスクサービスで知名度トップクラス!
生後1ヶ月から利用でき、月齢に合わせた知育に最適なおもちゃが届きます。
そのほか、トイサブを利用することで以下のようなメリットがあります。
- 返却期限や延滞料金なし
- おもちゃが壊れても、基本的に弁償は不要
- 気に入った場合はお得に買い取ることも可能
初月は約2,000円OFFの1,990円~使用できるので、まずは利用してみるとよいでしょう。
>2ヶ月990円で利用できる妊娠中から生後1.5か月までの方はこちら
おもちゃのサブスクレンタルサービス12つを徹底比較した以下の記事も、合わせて参考にしてみてください。
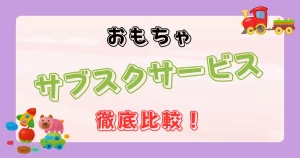
そもそもモンテッソーリ教育とは?
モンテッソーリ教育という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどのような教育なのかまでは知らないパパママも多いかもしれません。
ここでは、基本的な考え方や目的をわかりやすく紹介していきます。
モンテッソーリ教育の基本理念と目的
モンテッソーリ教育は、子どもを「自立したひとりの人間」として尊重することが大前提です。
大人が教えるのではなく、子ども自身が環境の中で学び、成長していくという考えが土台になっています。
その目的は、子どもの「自己教育力」を引き出すこと。
つまり、大人が手を出しすぎず、子どもが自分で考えて行動する力を育むのがモンテッソーリ教育のゴールです。
例えば、年齢に合ったお仕事(活動)を通して、自分のペースで取り組む。
そうすることで、自信や達成感を得られます。
家庭でも意識すれば取り入れられるシーンがたくさんあります。
自分で靴を履いたり、コップに水を注いだりといった何気ない動作の中にも、子どもの「やりたい」という気持ちが詰まっているんですね。
- 子どもの主体性を大切にする
- 失敗から学び、成功体験につなげる
- 環境づくりによって「自分でやる」を引き出す
子どもの「やってみたい!」という気持ちを見守る姿勢が、モンテッソーリ教育の出発点。
これは家庭でもすぐに意識できる部分なので、育児のヒントとして取り入れやすいといえます。
モンテッソーリ教育が注目される理由
モンテッソーリ教育は、いま世界中で再注目されています。
背景には「子どもの個性を大事にしたい」「自立心や集中力を育てたい」という、親の想いが強くなっていることがあります。
特に今の時代は、正解がひとつではない世界。
そんな中で、自分の頭で考えて行動する力は大きな武器になります。
モンテッソーリ教育は、その「考える力」「やり抜く力」の土台づくりに役立つといわれています。
また、実は有名な実業家やアーティストの中にも、幼少期にモンテッソーリ教育を受けたという人が多いんです。
そんな話題をきっかけに、SNSや書籍でも取り上げられることが増え、興味を持つパパママも増えています。
- 子どもの個性や自立心を育てることに注目が集まっている
- 教育の選択肢が広がり「オルタナティブ教育」への関心が高まっている
- 情報発信が増え、家庭でも実践しやすくなった
注目される理由は流行だからではありません。
実際に実践してみた家庭から「変化を感じた」という声が増えているからこそ、今あらためて見直されている教育法なのだといえます。
自宅で実践する「おうちモンテ」の魅力
モンテッソーリ教育と聞くと、「専門の園に通わないとできないのでは?」と感じるかもしれません。
でも実は、家庭でも十分に取り入れられるんです。
それが「おうちモンテ」と呼ばれるスタイルです。
おうちモンテの魅力は、日常の中で自然に教育の要素を取り入れられること。
特別な教材や高価な教具がなくても、「自分でできる」環境づくりが基本なので、今日からでも始められます。
たとえば、子ども専用の棚を用意して、毎朝自分で着替えを選ばせたり。
使ったおもちゃを自分で元に戻す流れを習慣づけたり。
それだけでも、子どもの中にはしっかり「やる力」が育っていくんですね。
- 家庭にいながらモンテッソーリ的な体験ができる
- 親子の関わりの中で自然に学びを育める
- 忙しい日々の中でも手軽に始められる
僕も日々の中で「おもちゃの置き方」「声のかけ方」を工夫することで、子どもが自分から動く姿を見る機会が増えてきました。
小さなことからでもいいので、無理なくできる範囲で「おうちモンテ」を楽しんでみるのがオススメです。
モンテッソーリ教具の特徴と選び方
モンテッソーリ教育に欠かせないのが「教具」と呼ばれる特別なおもちゃたちです。
これらは単に遊ぶための道具ではなく、子どもの発達に合わせて「学び」や「気づき」が得られるように工夫されています。
モンテッソーリ教具の基本的な種類と目的
モンテッソーリ教具は、大きく分けて3つのカテゴリに分類されます。
それぞれの教具には、子どもの発達段階に応じた「目的」があり、成長をサポートしてくれる仕掛けが隠れています。
どの教具も「自分で触ってみる」ことで理解が深まるように作られていて、大人が教え込む必要はありません。
あくまでも子ども自身の気づきが大切にされているんですね。
- 感覚教具:視覚・触覚など五感を使って学ぶ
- 日常生活教具:手指を使った作業で自立を促す
- 数・言語・文化教具:論理的思考や表現力を育てる
これらを知っておくことで、「どのタイミングでどんな教具を用意すればいいのか」がグッと分かりやすくなります。
次の章では、それぞれの教具をもう少し詳しく見ていきましょう。
感覚教具(視覚・触覚など)
感覚教具は、子どもの五感を刺激しながら「ものの違い」や「順序」などを自然と学ばせてくれる教具です。
たとえば、長さ・重さ・色・手触りの違いに気づくように工夫されていて、観察力や比較する力が育っていきます。
子どもは遊びの中で「あれ?これとこれはちょっと違うな」と感じ、自分の中で法則を発見していきます。
この「気づく→試す→納得する」の流れが、モンテッソーリ教育でとても大切にされています。
- 大きさや形、色などの感覚を磨ける
- 自分の手で操作することで集中力が育つ
- 正解がひとつでないので失敗からも学べる
代表的な感覚教具には「円柱さし」「ピンクタワー」「色板」などがあります。
どれも見た目はシンプルですが、じっくり遊ぶ中で子どもの中に大きな学びが芽生えていきます。
日常生活教具(手指運動・集中力)
日常生活教具は、子どもが「大人のまね」をしながら日常の動きを体験できる教具です。
食器を拭いたり、ひもを結んだりといった活動を通して、手指の動きや集中力を育てます。
この教具のねらいは、「できた!」という小さな達成感を積み重ねること。
子どもは大人のしていることに強く興味をもちます。
それを安全に、かつ自分のペースで試せるのが日常生活教具なんです。
- 実生活につながるスキルが自然と身につく
- 手先の巧緻性が高まり、字を書く準備にもつながる
- 自分でできる経験が、自信と自立心を育てる
水を注ぐ、布をたたむ、靴をそろえるなどの活動も立派な教具になります。
おうちでも、身近な道具を用意するだけで気軽に始められる点も魅力ですね。
数・言語・文化教具(論理的思考)
数・言語・文化に関する教具は、子どもの知的好奇心をくすぐりながら、論理的思考力や表現力を養うことを目的としています。
数字の概念、文字の形、地理や動物などの知識まで幅広く含まれます。
いきなり「教える」のではなく、「遊びながら自然と学ぶ」スタイルなのがモンテッソーリ流。
たとえば、数をブロックで数えたり、砂文字で文字の形をなぞったり。
体感を通して理解が深まるように設計されています。
- 数や文字に対して「楽しい」と感じられる
- 五感を使った体験で記憶に残りやすい
- 世界への興味や探究心が育つ
代表的な教具には「数の棒」「砂文字板」「地球儀パズル」などがあります。
抽象的な概念を、子どもにもわかりやすく「見える化」しているのがポイントです。
教具選びのポイントは「年齢」「発達段階」「興味」
モンテッソーリ教具を選ぶときに大切なのは、「その子に合っているかどうか」。
同じ年齢でも成長スピードはそれぞれ違うので、「できそう」「興味がありそう」と感じるものを選ぶのが基本です。
また、発達段階に合わない教具を与えても、子どもはピンとこないことがあります。
逆に、ちょうどのタイミングで渡された教具には驚くほど集中したり、自分から繰り返し使ったりする姿が見られます。
- 子どもの月齢や年齢を参考にする
- 「今どんなことに興味を持っているか」を観察する
- 成功体験が得られるちょうどよい難易度を選ぶ
おもちゃサブスクでも、年齢や興味に合わせたアイテムが届くサービスがあります。
100%モンテッソーリ教具ではなくても、選び方の基準を知っておくだけで、おもちゃ選びがグッと楽になりますよ。
0〜1歳にオススメの教具
0〜1歳は「見る・聞く・触る」など、五感を使って世界を感じ始める大切な時期。
そのため、視覚・聴覚・触覚をやさしく刺激するシンプルな教具がオススメです。
赤ちゃんは、まだ手先の動きが発達しきっていないため、「握る」「振る」といった基本的な動作がしやすいアイテムが適しています。
また、色や音の違いに反応するので、選ぶ際は素材やデザインにも注目したいですね。
- 視覚や聴覚をやさしく刺激する
- つかみやすく、誤飲の心配がないサイズ
- 素材は天然木や布など、安心感のあるもの
たとえば「ラトル(ガラガラ)」や「布ボール」「モビール」などが定番です。
親子で一緒に遊ぶことで、スキンシップにもつながりますし、赤ちゃんの反応もより楽しめます。
1〜2歳にオススメの教具
1〜2歳になると、歩けるようになったり「自分でやりたい!」という気持ちが強くなってきます。
この時期は、手や指をたくさん使える教具で「できた」を積み重ねることがとても大切です。
指先を動かす練習や、形・色の違いに気づく遊びを通じて、集中力や観察力が育っていきます。
少しずつ自分の行動をコントロールできるようになるので、繰り返し遊べる工夫がある教具がぴったりです。
- 手指を使って「はめる」「通す」などの操作ができる
- 色・形の識別ができるようになる
- 自分でできた達成感を味わえる構造
例としては、「リング通し」「型はめパズル」「ポットン落とし」などが人気です。
遊びながら「考える力」や「手の動き」が自然と育っていくのが、この時期の教具の魅力ですね。
3〜4歳にオススメの教具
3〜4歳になると、より複雑なことにチャレンジしたくなる時期です。
手先の器用さが増し、思考力や言葉への興味も高まるため、少し難しめの教具がちょうどよくなってきます。
また、「なんで?」「どうしてこうなるの?」という疑問を持つようになるので、考える過程を楽しめる教具がオススメです。
失敗してもくり返し試せる設計になっていると、集中して取り組めます。
- 少しずつ論理的な思考を育てられる
- 手先を使いながら問題解決する体験ができる
- 言葉・数・文化など広い分野への興味を促す
たとえば「ひも通し迷路」「簡単な数遊びブロック」「砂文字」などが人気です。
「あれ?違うな」「できた!」と試行錯誤しながら遊ぶ姿が見られるようになりますよ。
5歳以上にオススメの教具
5歳を過ぎると、より抽象的な概念や複数ステップの作業にも取り組めるようになります。
この時期は「なぜそうなるのか」を考えたり、物事のルールや構造に関心を持ち始める子が多くなります。
論理的思考や言語表現を深めるための教具がピッタリです。
また、自分の考えを作品として形にするような「表現系」の遊びにも夢中になりやすい時期です。
- 数や文字を使って「考える力」を育てる
- 自分の気づきやアイデアを形にできる
- ルールや順序を理解しながら楽しめる
たとえば「時計の読み方パズル」「地図や国旗の教具」「ひらがな・カタカナのカード遊び」などが人気です。
遊びながら学べる内容がグッと広がっていく時期ですね。
木製やシンプルなデザインがなぜよいのか?
モンテッソーリ教具といえば、木製で落ち着いた色味のものが多い印象ですよね。
それにはちゃんと理由があります。
子どもの集中力や感覚を育てるために、あえて「シンプルさ」を大切にしているのです。
派手な色や音があると、刺激が強すぎて子どもの注意が散ってしまいがち。
だからこそ、静かで自然な素材が選ばれているんですね。
木の温もりや手ざわりは、感覚をやさしく刺激してくれます。
- 素材の感触をじっくり味わえる
- 色や形の違いに集中しやすい
- 飽きが来にくく、長く使える
僕自身、子どもたちが木のおもちゃをじっと見つめて、静かに遊ぶ姿に驚くことがよくあります。
色が少ないからこそ「気づく力」が引き出されているように感じます。
おもちゃサブスクでモンテッソーリ教育はできる?
最近は、月額でおもちゃが届く「おもちゃのサブスク」が人気を集めています。
では、モンテッソーリ教育の視点から見て、このサービスは相性がいいのでしょうか?
おもちゃのサブスクがモンテッソーリ教育に向いている理由
モンテッソーリ教育では、子どもの「今の発達段階」に合った環境を整えることが大切だとされています。
おもちゃのサブスクは、まさにこの考えに近いサービスなんです。
年齢や成長に応じたおもちゃをプロが選定してくれるため、家庭での「おうちモンテ」のベースづくりに活用しやすいという声も。
子どもが飽きたら交換できるので、興味の変化にも柔軟に対応できます。
- 発達段階に合ったおもちゃを選んでもらえる
- 興味の変化に合わせてローテーションできる
- 自宅に適した環境づくりの助けになる
もちろん、届くおもちゃすべてがモンテッソーリ教具そのものではないかもしれません。
それでも考え方を意識して選べば、十分に活用できる手段といえるでしょう。
ただし、教具はすべてがモンテッソーリ準拠ではない
おもちゃのサブスクは便利なサービスですが、すべてのアイテムが「モンテッソーリ教具」であるとは限りません。
それぞれのサービスごとに選定基準やコンセプトが異なるためです。
特に、音や光が派手なものやキャラクター要素の強いものは、モンテッソーリ教育の観点からは少し離れることもあります。
そのため、「自分で操作できるか?」「感覚を使うか?」「繰り返し遊べるか?」などの視点で、届いたおもちゃを見てみるとよいかもしれません。
- 届いたおもちゃがすべて教育方針に合うとは限らない
- サブスクの方針やレビューを事前にチェックする
- 子どもが主体的に遊べるかどうかを見極める
サブスクは「選ぶ手間」を減らす便利な仕組み。
だからこそ、親が少しだけ「どんなおもちゃか」を見てあげることで、モンテッソーリの考え方に沿った使い方が可能になります。
おもちゃのサブスクでモンテッソーリ教育をする6つのメリット
モンテッソーリ教育と相性がよいおもちゃサブスク。
実際に取り入れてみると、子どもの反応や成長にうれしい変化が見られることも多いようです。
自立心が育つ
モンテッソーリ教育の大きな柱のひとつが「自立」。
おもちゃのサブスクを活用することで、子どもが「自分で選ぶ」「自分で片づける」という体験を自然に積むことができます。
例えば、届いたおもちゃを棚に並べて「今日はどれで遊ぼうかな?」と選ぶ。
それだけでも、自分の意思で動く習慣が育まれていきます。
- 選ぶ→遊ぶ→片づけるの流れが習慣化しやすい
- 「自分で決める」体験が日常の中に増える
- 大人が手を出しすぎなくてもよくなる
おもちゃを通じて「自分でできた!」の体験が積み重なると、子どもの心がグンと育ちます。
これは、おうちモンテでも大事にしたいポイントです。
感覚統合が促される
モンテッソーリ教育では「感覚」を育てることがとても重視されています。
見る、触れる、聞くといった五感をバランスよく使う経験が、子どもの脳の発達に影響すると考えられているからです。
おもちゃのサブスクでは、手触り・色合い・音などに配慮された知育玩具が選ばれることも多く、そうした感覚への刺激を日常的に与えることができます。
- さまざまな素材や形に触れる体験ができる
- 色・音・形の違いに気づく感覚が育つ
- 体と頭をつなげる「感覚統合」が進む
たとえば、木のビーズをつまんでひもに通すおもちゃなどは、触覚と視覚、そして手指の動きを連動させる絶好の教材になります。
こうした遊びは、将来の学習の基礎にもつながっていきます。
集中力が高まる
モンテッソーリ教育では、「集中する時間」をとても大切にしています。
子どもが自分で選んだ活動に夢中になる時間こそが、学びのゴールデンタイムだからです。
おもちゃサブスクでは、年齢や発達段階に合ったアイテムが届くので、子どもが「ちょうど面白い」と感じるおもちゃに出会いやすい。
この「ちょうどいい」が、集中力を引き出すカギなんです。
- 子どもが夢中になれるタイミングで遊べる
- 手と頭を使ってじっくり取り組めるおもちゃが届く
- 「飽きずに遊ぶ」経験が集中力を養う
一度ハマると、周りの声が聞こえないほど集中する。
そんな姿を見ると、「この時間を大切にしてあげたいな」と感じることがよくあります。
興味に応じておもちゃを変えられる
子どもの「今ハマっていること」は日々変わります。
昨日まではブロックに夢中だったのに、今日はひも通しにしか目がいかない。
そんな経験、ありませんか?
おもちゃサブスクの強みは、こうした子どもの興味の移り変わりに合わせて、柔軟にアイテムを入れ替えられること。
まさに、モンテッソーリ教育で大切にされている「今その子に合った環境づくり」とリンクする点です。
- 成長や関心に合わせて柔軟に入れ替えられる
- 無理に遊ばせる必要がなく、自然な学びが生まれる
- 子どもの「やりたい」に沿った体験ができる
モンテッソーリの教えでは「興味のあることに集中できる環境」がとても重要。
サブスクは、それを家庭で手軽に実現できる手段のひとつだといえます。
おもちゃを厳選できる=与えすぎ防止
ついつい増えがちなおもちゃ。
気づけば部屋がごちゃごちゃしていて、子どももどれで遊ぶか分からなくなっている……そんなことありませんか?
おもちゃのサブスクを活用すると、届く数に限りがあるぶん「選ばれたおもちゃだけがある環境」が自然と整います。
これはモンテッソーリ教育で重視される「整った環境」にぴったりな状態です。
- 遊びが分散せず、ひとつに集中しやすい
- 「与えすぎ」による刺激過多を防げる
- おもちゃの管理や片づけもラクになる
少ない数でも、子どもはじっくり遊び込めます。
「どれにしようかな」と悩むより、「これで遊ぼう!」と決められる環境が、集中力や自主性を後押ししてくれます。
親もおもちゃ選びで迷わなくて済む
「どのおもちゃが今の子どもに合うんだろう?」
そんなふうに悩む時間、意外と多くありませんか?
僕もよくお店で立ち尽くしたり、レビューを読みあさったりしていました。
おもちゃサブスクでは、発達段階や興味に合わせて専門家が選んでくれることが多く、親の悩みをぐっと減らしてくれます。
さらに、届いたおもちゃを通じて「今こんな力が育っているんだ」と知れるのも嬉しいポイントです。
- おもちゃ売り場で迷う時間が激減する
- 子どもの成長に合ったものが手軽に手に入る
- 「今何を伸ばせばいいのか」がわかりやすくなる
おもちゃ選びがスムーズになると、育児の負担もグッと軽くなります。
親のゆとりができれば、子どもにも余裕を持って関われますよね。
モンテッソーリ教育にオススメのおもちゃサブスク7選
「どのサブスクがモンテッソーリに合っているの?」と悩む方は多いはず。
でも安心してください。
選び方のポイントを押さえれば、自宅での「おうちモンテ」にぴったりのサービスに出会えます。
ここでは、木製の教具や感覚を育てるおもちゃを扱っていたり、リクエスト対応ができたりと、モンテッソーリ教育の視点でもオススメできるサービスを厳選してご紹介します。
- 子どもの「今」に合ったおもちゃが届く
- 家庭でもモンテッソーリ教育が実践しやすくなる
- 親の負担がグッと減る
トイサブ!
トイサブ!は、知育おもちゃのサブスクで業界最大級の利用者数を誇ります。
対象は0歳~6歳までで、発達に応じたおもちゃを5~6点ずつ定期的に届けてくれます。
嬉しいのは、プランナーが保育士などの資格者で構成されている点。
モンテッソーリ教育に適した木製や感覚系のおもちゃも多数扱っており、リクエスト時に「シンプルな手指を使うおもちゃを希望」と伝えれば、柔軟に対応してもらえるのもポイントです。
- 専門家が選ぶから、年齢・興味にぴったりのおもちゃが届く
- モンテッソーリ教具風のシンプルな玩具も多数
- 気に入ったおもちゃは延長・買取も可能
実際に使った家庭では「子どもが毎回食いつく」「親の悩みが減った」という声も多く、手軽におうちモンテを始めたい方にぴったりのサービスです。
キッズ・ラボラトリー
キッズ・ラボラトリーは、0歳から8歳までを対象とした知育おもちゃのサブスクです。
届くおもちゃは木製を中心に、感覚や手指を使った遊びを促すものが多く、モンテッソーリの考え方に通じる内容になっています。
特徴的なのは、初回のお届けからすぐに交換できる「返却保証」があること。
気に入らなければすぐ別のものに替えられるので、子どもの反応を見ながら柔軟に遊びを調整できるんです。
また、LINEでのやりとりもできるので、ちょっとした相談も気軽にできるのが嬉しいポイント。
- 木製・シンプルで集中できるおもちゃが豊富
- 届いてすぐの交換にも対応してくれる
- LINEで相談できるから親の不安も解消しやすい
「これ本当にうちの子に合うかな?」と不安な時期でも、サポート体制が整っているので安心。
遊びながらモンテッソーリ的な力を育てたいご家庭にぴったりです。
Cha Cha Cha(チャチャチャ)
Cha Cha Chaは、保育士や幼稚園教諭の資格をもつスタッフが監修するおもちゃサブスクです。
対象年齢は0歳3か月から6歳までと、ちょうどモンテッソーリ教育を意識した遊びが活きる時期にぴったり。
特に特徴的なのは、3つの専門プランから選べる点。
学研ステイフル監修の「知育強化プラン」、発達に配慮した「特別支援プラン」など、家庭のニーズに合わせてカスタマイズできる柔軟さが魅力です。
もちろん、モンテッソーリ要素を取り入れたい旨をリクエストすることも可能です。
- 保育士監修で安心感がある
- 目的に応じたプランを選べる
- 兄弟で1契約使い回せるのも嬉しい
Cha Cha Chaなら、教育的な観点でバランスよく選ばれたおもちゃが届くので、「モンテッソーリも少し意識したい」そんな家庭にぴったりの選択肢といえます。
And TOYBOX(アンドトイボックス)
And TOYBOXは、0歳3か月〜4歳11か月までの子どもを対象としたおもちゃの定額レンタルサービスです。
届くおもちゃの内容を事前に確認できて、しかも満足いくまで変更できる「プレミアムコース」が特徴的。
モンテッソーリ的な視点でおもちゃを選びたい場合にも、LINEで希望を伝えれば、保育士スタッフがそれに沿った選定をしてくれるのが心強いポイント。
シンプルで感覚を育てるアイテムが多く、集中して遊べる環境を整えやすいです。
- 事前におもちゃの中身がチェックできる安心感
- LINEで細かい要望を伝えられる
- 感覚遊びや手指を使うアイテムが豊富
「せっかく届いたけど好みに合わなかった…」というミスマッチを防げる仕組みは忙しいパパママにも嬉しい。
おもちゃ選びに妥協したくないご家庭にぴったりです。
biblioteca(ビブリオテーカ)
biblioteca(ビブリオテーカ)は、デザイン性と教育性のバランスを重視したワンランク上のおもちゃサブスクです。
特に木製・布製など自然素材のおもちゃにこだわっていて、見た目も美しく、まさにモンテッソーリの世界観にマッチします。
選定は保育士とモンテッソーリ教育を学んだ専門スタッフが担当。
一人ひとりの子どもに合った「今、育てたい力」に合わせたおもちゃをセレクトしてくれるのが魅力です。
まるでセレクトショップのような品ぞろえで、親の気分も上がるはず。
- ナチュラルでシンプルな玩具が中心
- モンテッソーリ教育を学んだスタッフが選定
- 部屋のインテリアにもなじみやすい美しいおもちゃ
おもちゃを通して「豊かな感性」や「じっくり考える力」を育てたいご家庭には特におすすめ。
使うたびに、親子で丁寧な時間を過ごせるはずです。
トイズレンタ
トイズレンタは、木製おもちゃ専門のサブスクとして注目されているサービスです。
シンプルで温かみのあるおもちゃを中心にラインナップされており、モンテッソーリ教育と非常に相性がよいのが特徴です。
感覚教具のような仕掛けがあるおもちゃや、日常生活に近い作業を再現するアイテムなど、「おうちモンテ」にピッタリなものがそろっています。
また、すべての商品がしっかりメンテナンスされていて、品質への信頼感も◎。
- 木製・感覚遊び中心のラインナップ
- デザインがシンプルで集中しやすい
- 丁寧にメンテナンスされた清潔なおもちゃ
「モンテッソーリに近い環境を整えたい」
「木のおもちゃに囲まれた穏やかな空間をつくりたい」
そんな想いを持つ家庭にはぴったりのサービスです。
サークルトイズ
サークルトイズは、大型おもちゃや乗り物系のアイテムをレンタルできる珍しいサブスクです。
三輪車・ジャングルジム・トランポリンなど、大きな動きを引き出すおもちゃがそろっており、粗大運動を重視するモンテッソーリ教育との親和性も高いです。
「遊ぶスペースが足りない…」という悩みも、レンタルだから期間限定で利用できるのがポイント。
運動能力やバランス感覚、挑戦する力など、心と体の発達をトータルにサポートできます。
- 粗大運動を促すおもちゃが充実
- 室内で全身を使った遊びができる
- スペース問題もレンタルなら解決できる
身体を動かすことが好きな子や、運動系の発達を伸ばしたいご家庭に特にオススメ。
遊びながら体幹や自信を育むきっかけになります。
おもちゃのサブスクをモンテッソーリ教育に効果的な使う方法
せっかくサブスクで良いおもちゃを取り入れるなら、その力をしっかり発揮できるように使いたいですよね。
ここでは、モンテッソーリ教育の観点から、サブスクおもちゃをより効果的に活用するためのポイントを紹介していきます。
おうちモンテの環境づくりをする
モンテッソーリ教育で大切にされているのは、「子どもが自分で選び、自分のペースで取り組める環境」です。
サブスクのおもちゃを取り入れるときも、この考え方をもとに空間づくりをすることで、学びの効果がグンと高まります。
具体的には、子どもの目線で見える高さに棚を設置したり、おもちゃを並べて自分で選べるようにすることがポイント。
大人の「これやってみたら?」より、子どもの「これで遊びたい!」が引き出せる環境が理想です。
- 棚やトレーを使って、おもちゃを“見える化”する
- 1軍だけを厳選して並べると集中しやすい
- 子どもが「自分で選べた!」と感じられる配置が鍵
環境を整えるだけで、同じおもちゃでも子どもの集中力や遊び方がガラッと変わります。
これはサブスクだからこそ定期的に見直しやすく、取り入れやすい方法のひとつです。
おもちゃの数と配置のポイント
モンテッソーリ教育では、「少ない数でじっくり遊ぶ」ことが重視されます。
だからこそ、おもちゃサブスクを活用する際も、たくさん並べるより“厳選して置く”ことがポイントになります。
選択肢が多すぎると、子どもは迷ってしまい集中しにくくなります。
一度に出すのは3〜5個程度に絞り、それぞれの活動がしっかりと見えるように配置するのがオススメです。
- おもちゃは「少なめ」が集中力を引き出すコツ
- 並べ方は横一列が基本、重ねない
- 毎日使わないものは、別に保管しておいてOK
おもちゃの数をしぼると、逆に遊びの「深さ」が生まれます。
サブスクで定期的にローテーションする仕組みは、この考え方ともぴったりですね。
年齢に応じたローテーションの工夫
モンテッソーリ教育では、「その子の今の発達」にぴったりの活動を用意することが大切だとされています。
そのため、おもちゃのローテーションも“なんとなく”ではなく、年齢や成長に合わせて見直すのが効果的です。
たとえば、1歳前後は「つまむ・入れる」など単純な動きが中心。
2歳になると「組み立てる・分ける」など少し複雑な動きに夢中になります。
子どもの様子を観察して「そろそろ飽きてきたかな?」というタイミングで交換すると、次のおもちゃにもスムーズに移行できます。
- 月齢や発達段階に応じて「できる」レベルに合わせる
- 飽きたら交換、ハマっていたら延長でOK
- 成長のステップに合わせて「難易度」を少しずつアップ
サブスクだからこそ、おもちゃの入れ替えが簡単。
子どもが夢中になれる「ちょうどいい刺激」を、つねに届けやすい仕組みです。
サブスク×教育効果を最大にする使い方
サブスクのおもちゃをただ「届いたから遊ばせる」だけでは、モンテッソーリの良さは引き出しきれません。
大切なのは、“遊び=学び”という視点を持って、子どもの反応や様子をしっかり見守ることです。
たとえば、「黙々と同じ動きを繰り返してるな」と感じたら、それは集中して“今その力”を育てているサインかもしれません。
そんなときは声かけを控え、静かに見守るのが◎。
逆に興味が薄そうなら、入れ替えのタイミングです。
- 「遊び=学び」ととらえると声かけが変わる
- 集中していたらそっと見守るのが正解
- 子どもの反応を観察しながら、遊びを調整する
サブスクは、定期的な入れ替えやリクエストで調整できるのが魅力。
そこに“学びの視点”を加えることで、モンテッソーリ教育の力を最大限に活かせるようになります。
まとめ
モンテッソーリ教育を家庭に取り入れたいけれど、「何から始めればいいのか分からない」と悩む方は多いですよね。
そんなとき、おもちゃのサブスクは頼れる味方になってくれます。
年齢や発達に合わせて届くおもちゃは、「ちょうどよい学び」を自然に引き出してくれます。
とくに木製やシンプルなデザイン、感覚を育てるものなど、モンテッソーリ的な価値観に合ったおもちゃも豊富に選べるのが魅力です。
- 「自立心」「集中力」「感覚統合」が育ちやすい
- おうちモンテの環境づくりにも使いやすい
- 親のおもちゃ選びの負担も減らせる
今回紹介したサブスク7選の中から、あなたの家庭にぴったりのサービスを見つけて、遊びながらモンテッソーリ教育を楽しんでみてくださいね。
小さな「できた!」の積み重ねが、子どもの大きな自信につながります。
トイサブは、おもちゃのサブスクサービスで知名度トップクラス!
生後1ヶ月から利用でき、月齢に合わせた知育に最適なおもちゃが届きます。
そのほか、トイサブを利用することで以下のようなメリットがあります。
- 返却期限や延滞料金なし
- おもちゃが壊れても、基本的に弁償は不要
- 気に入った場合はお得に買い取ることも可能
初月は約2,000円OFFの1,990円~使用できるので、まずは利用してみるとよいでしょう。
>2ヶ月990円で利用できる妊娠中から生後1.5か月までの方はこちら
おもちゃのサブスクレンタルサービス12つを徹底比較した以下の記事も、合わせて参考にしてみてください。