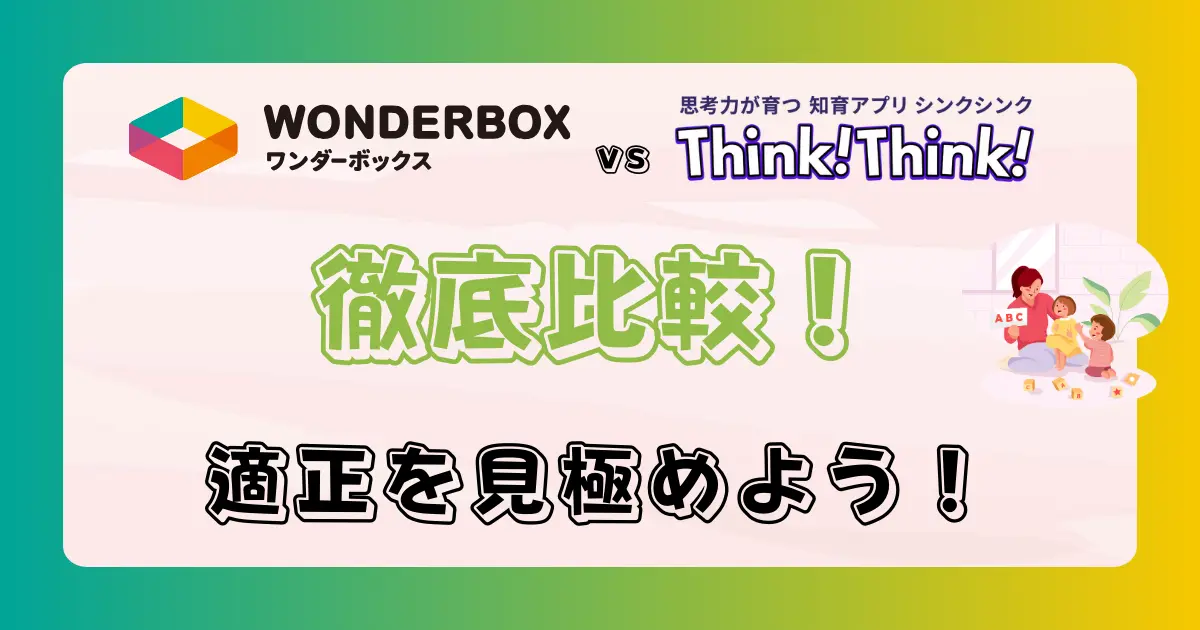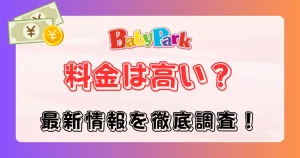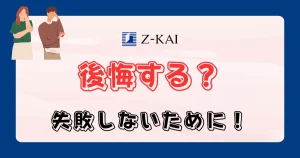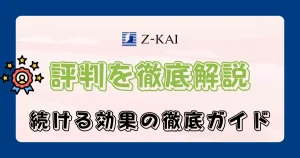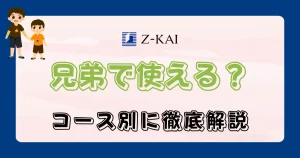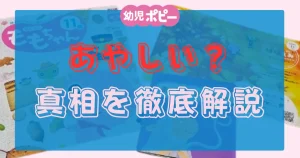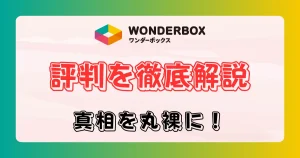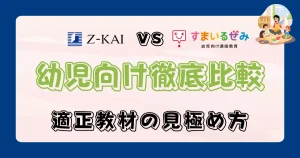- 教材選びで迷っている
- ワンダーボックスとシンクシンクの違いがよく分からない
- 料金や効果、続けやすさを比較したい
- 子どもに最適な学びの機会を与えたい
お子さんの知育教材について、このようなお悩みはありませんか。
大切なお子さんのための選択だからこそ、慎重になるのは当然ですよね。
特にワンダーボックスとシンクシンクは、どちらも思考力を伸ばす人気の教材ですが、具体的な違いや選び方のポイントが分かりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ワンダーボックスとシンクシンクで迷っているあなたのために、7つの重要な違いを徹底的に比較し、それぞれのメリット・デメリット、そして選び方のポイントを分かりやすく解説します。
どちらもお子さんの力を引き出す素晴らしい教材ですが、特徴が異なるため、ご家庭の方針やお子さんのタイプによって最適な選択は変わってきます。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- ワンダーボックスとシンクシンクの根本的な違い(7つの比較ポイント)
- それぞれの教材のメリット・デメリット
- 料金プランとコストパフォーマンス
- どのようなお子さん・ご家庭にどちらが向いているか
- よくある疑問とその回答
最後まで読めば、「うちの子にはこっちが合ってるかも!」と自信を持って判断できるようになるはずです。
教材選びの迷いを解消し、お子さんの未来につながる最適な学びを見つけるために、ぜひ参考にしてくださいね。
【結論】ワンダーボックスとシンクシンク、あなたのお子さんにはどっちがオススメ?
どちらの教材を選ぶべきか、まず結論からお伝えします。
もちろん、最終的な判断はお子さんの個性やご家庭の状況によりますが、大まかな方向性として参考にしてください。
好奇心旺盛で幅広い学びに触れさせたいなら「ワンダーボックス」
ワンダーボックスは、プログラミング、アート、科学実験、数理パズルなど、STEAM教育の幅広い分野をカバーしているのが最大の特徴です。
アプリだけでなく、毎月届くキット(教材)を使ったアナログな体験もできるため、五感をフル活用して学ぶことが可能です。
「特定の分野だけでなく、様々な体験を通して子どもの興味関心や可能性を広げたい」「遊び感覚で創造力や思考力を総合的に育みたい」と考えているご家庭には、ワンダーボックスが適しているといえるでしょう。
ワンダーボックスがフィットするポイントは以下の通りです。
- STEAM教育に興味がある
- デジタルだけでなく、手を使うアナログな学びも重視したい
- 子どもの好奇心を刺激し、様々な分野への興味を引き出したい
- 時間を気にせず、じっくりと取り組ませたい
- 創造力や表現力を豊かに育みたい
手軽に思考力(特に算数・図形)を伸ばしたいなら「シンクシンク」
シンクシンクは、思考力の中でも特に算数や図形、空間認識能力といった分野に特化した知育アプリです。
アプリだけで完結し、1日10分という短い時間で取り組める手軽さが魅力。
「まずは気軽に思考力トレーニングを始めたい」「スキマ時間を有効活用したい」「算数やパズルが好きなお子さんの力をさらに伸ばしたい」というニーズには、シンクシンクがピッタリです。
無料で始められるプランもあるので、知育アプリが初めてのご家庭でも試しやすいでしょう。
シンクシンクがフィットするポイントは以下の通りです。
- 費用を抑えて知育を始めたい(無料プランあり)
- アプリだけで手軽に取り組ませたい
- 1日10分程度の短時間で集中させたい
- 算数や図形、パズル問題に特化して思考力を鍛えたい
- 親の手間をかけずに、子ども主体で進めさせたい
そもそもワンダーボックスとシンクシンクとは?それぞれの基本情報と特徴
比較に入る前に、まずはワンダーボックスとシンクシンクがそれぞれどのような教材なのか、基本的な情報と特徴を確認しておきましょう。
ワンダーボックス:未来を生き抜く力を育むSTEAM教材
ワンダーボックスは、「未来を生き抜く力」を育むことを目的とした、アプリとキットを組み合わせたSTEAM教育プログラムです。
STEAMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Art(芸術)、Mathematics(数学)の頭文字を取ったもので、これらの分野を横断的に学ぶことで、これからの社会で必要とされる思考力や創造力、問題解決能力を養います。
毎月新しいテーマの教材が届き、デジタルとアナログの両面から子どもの知的なわくわくを引き出す工夫が満載です。
- 対象年齢:4歳~10歳(年中~小4)
- 教材形式:専用アプリ + 毎月届くキット教材(トイ、ワークブックなど)
- 学習領域:STEAM全般(プログラミング、数理パズル、アート、科学など)
- 利用制限:基本的に制限なし(保護者による時間設定は可能)
- 料金:月額3,700円~(税込、12ヶ月一括払いの場合)
シンクシンク:世界で人気の思考力育成アプリ
シンクシンクは、世界150ヶ国、300万人以上の子どもたちが利用している思考力育成に特化した知育アプリです。
パズルや図形、迷路といった120種類以上の問題を通して、楽しみながら算数や科学の土台となる「思考センス」を伸ばすことを目指しています。
1日10分という短時間設計で、ゲーム感覚で手軽に取り組めるのが特徴。
カンボジアでの実証実験では、IQや算数の成績向上効果も確認されています。
- 対象年齢:4歳~10歳(推奨)
- 教材形式:専用アプリのみ
- 学習領域:思考力(空間認識、平面図形、試行錯誤、論理、数的処理)
- 利用制限:1日1回(約10分)、3つの問題まで(※有料プランで緩和)
- 料金:無料プランあり。有料プランは月額450円~(税込、スタンダードコースの場合)
【一覧表】ワンダーボックスとシンクシンクの基本スペック比較
ここまで紹介した基本情報を、比較しやすいように表にまとめました。
主な違いが一目で分かります。
| 項目 | ワンダーボックス | シンクシンク |
|---|---|---|
| 教材形式 | アプリ+キット | アプリのみ |
| 学習領域 | STEAM全般 | 思考力(算数・図形特化) |
| 利用制限 | 基本なし(設定可) | 1日1回約10分(制限あり) |
| 料金(月額目安) | 3,700円~ | 無料~ |
| アナログ教材 | あり(毎月届く) | なし |
| 手軽さ | △(キット管理など) | ◎(アプリだけ) |
| 学習範囲の広さ | ◎ | △ |
| 無料体験 | 資料請求で体験キット+アプリ一部 | アプリDLで無料プラン利用可 |
【徹底比較】ワンダーボックスとシンクシンクの7つの違いを深掘り!
ここからは、ワンダーボックスとシンクシンクの具体的な違いを7つのポイントに分けて、さらに詳しく見ていきましょう。
それぞれの特徴を理解することで、どちらがお子さんやご家庭に合っているか、より明確になります。
違い1.料金プランとトータルコスト
教材選びで最も気になるポイントのひとつが料金ですよね。
ワンダーボックスとシンクシンクでは、料金体系が大きく異なります。
ワンダーボックスは月額制のサブスクリプションで、支払い期間が長いほど月あたりの料金が安くなります。
一方、シンクシンクは無料プランに加え、より多くの機能が使える有料プランが用意されています。
具体的には、以下のようになっています。
| 教材 | 料金プラン(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ワンダーボックス | ・月払い:4,200円/月 ・6ヶ月一括:24,000円 (4,000円/月) ・12ヶ月一括:44,400円 (3,700円/月) | ・別途入会金なし ・兄弟追加は月額1,850円 ・送料込み |
| シンクシンク | ・無料プラン:0円 ・スタンダード:450円/月 ・プレミアム:980円/月 (年払いの場合 7,800円) | ・無料プランでも利用可能 ・有料プランで問題数や機能が増える |
単純な月額料金だけを比べると、シンクシンクの方が圧倒的に安価です。
しかし、ワンダーボックスには毎月のアナログ教材(キット)が含まれていることを考慮する必要があります。
学習範囲の広さや教材ボリュームを考えると、ワンダーボックスの料金設定も納得できるという声も多いです。
ご家庭の予算や、教材に求める内容によって、どちらのコストパフォーマンスがよいと感じるかは変わってくるでしょう。
違い2.教材内容
教材の内容は、両者の最も大きな違いといえます。
ワンダーボックスは、デジタル(アプリ)とアナログ(キット)を組み合わせた複合的な教材です。
アプリではプログラミングや思考力ゲーム、アート作成などが楽しめ、キットではパズルや実験、ワークブックなど、実際に手を動かして学ぶ体験ができます。
これにより、多角的な視点や五感を刺激する学びが可能です。
一方、シンクシンクはアプリのみで完結するデジタル教材です。
手軽に始められ、場所を取らないのがメリットですが、アナログな体験はできません。
アプリ内には、図形、パズル、迷路など、思考力を刺激する様々なジャンルの問題が120種類以上収録されています。
教材内容の違いをまとめると、以下のようになります。
- ワンダーボックス:
・アプリ:多様なSTEAMコンテンツ
・キット:トイ教材、ワークブック、カードなど(毎月変更)
・特徴:デジタルとアナログの融合、体験型学習 - シンクシンク:
・アプリ:思考力問題(図形、パズル、論理など120種以上)
・キット:なし
・特徴:アプリ完結、手軽、思考力(算数・図形系)に特化
お子さんが手先を動かすのが好きか、タブレット操作が得意かなども考慮して選ぶとよいでしょう。
違い3.学べる領域
教材内容の違いは、学べる領域の違いにも直結します。
ワンダーボックスはSTEAM教育を掲げている通り、科学・技術・工学・芸術・数学という非常に幅広い分野をカバーしています。
プログラミング的思考、論理的思考、空間認識能力はもちろん、創造性や表現力、探求心といった多様な力を育むことを目指しています。
対してシンクシンクは、思考力、特に算数や図形に関連する能力の育成に特化しています。
具体的には、空間認識、平面図形、試行錯誤、論理、数的処理といった、算数的思考の基礎となる力を集中的に鍛えることができます。
学べる領域はワンダーボックスに比べて限定的ですが、その分、特定の力を効率よく伸ばすことに焦点を当てています。
どちらの領域に重点を置きたいかで、選択が変わってきますね。
学べる領域の比較ポイントです。
- ワンダーボックス:STEAM全般(科学、技術、工学、芸術、数学)→ 幅広い
- シンクシンク:思考力(算数、図形、パズル、論理)→ 特化型
違い4.期待できる効果
学べる領域が違えば、期待できる効果も異なります。
ワンダーボックスでは、多様な教材に取り組む中で、知識だけでなく「考え方」や「学びに向かう姿勢」そのものを育むことを重視しています。
具体的には、論理的思考力、問題解決能力、創造性、表現力、そして自ら学び続ける意欲(非認知能力)などが養われることが期待されます。
一方、シンクシンクは、思考力トレーニングに特化しているため、空間認識能力、図形センス、論理的思考力といった、いわゆる「地頭のよさ」に直結する力の向上が期待できます。
実際に、シンクシンクの継続利用によってIQスコアや算数の偏差値が向上したという研究結果も報告されています。
短時間で集中して取り組むことで、集中力アップの効果も考えられます。
期待できる効果のポイントを整理しましょう。
| 教材 | 期待できる主な効果 |
|---|---|
| ワンダーボックス | ・思考力(論理、問題解決) ・創造力、表現力 ・探求心、学びへの意欲 ・非認知能力 |
| シンクシンク | ・思考センス(空間認識、図形、論理) ・算数的思考力の基礎 ・集中力 ・IQ向上(実証データあり) |
お子さんにどのような力を伸ばしてほしいかを明確にすることで、より適した教材が見えてきます。
違い5.利用時間・回数の制限
教材への取り組み方に関わるのが、利用時間や回数の制限です。
ワンダーボックスのアプリには、基本的に利用時間やプレイ回数の制限がありません。
お子さんが興味を持ったコンテンツに、好きなだけじっくりと取り組むことが可能です。
ただし、保護者向けの機能として、1日の利用時間を設定できるタイマー機能は用意されています。
やりすぎが心配な場合も安心ですね。
対照的に、シンクシンクは「1日1回、10分程度、3つの問題まで」という明確な利用制限が設けられています(無料プランの場合)。
これは、子どもがゲームに熱中しすぎるのを防ぎ、集中力を維持したまま短時間で効果的に学べるように設計されたものです。
有料プランに加入すると、利用できる問題数が増えるなどの緩和措置があります。
利用制限に関する比較です。
- ワンダーボックス:原則制限なし。時間を忘れて没頭できる。保護者による時間設定は可能。
- シンクシンク:1日10分程度の制限あり。短時間集中型。やりすぎを防ぐ。
お子さんの性格(集中力が続くタイプか、切り替えが必要なタイプか)や、ご家庭での学習習慣に合わせて検討するとよいでしょう。
違い6.対象年齢
ワンダーボックスとシンクシンクは、どちらも主な対象年齢を4歳~10歳(年中~小学校4年生)としています。
この点においては、大きな違いはありません。
ただし、提供されるコンテンツの幅広さから、ワンダーボックスの方がより多様な発達段階の子どもに対応しやすい側面はあるかもしれません。
例えば、手先を使うキット教材は低年齢の子どもでも楽しめますし、プログラミングや少し複雑な思考問題は小学校中学年でもやりごたえがあります。
シンクシンクの問題も難易度は様々ですが、主にアプリ操作が中心となるため、タブレットやスマートフォンの操作に慣れているかどうかも考慮点になります。
とはいえ、どちらの教材も対象年齢内であれば、多くのお子さんが楽しめるように設計されています。
対象年齢に関する注意点をまとめました。
- 共通対象年齢:4歳~10歳(年中~小4)
- ワンダーボックス:幅広いコンテンツで、年齢による楽しみ方の変化に対応しやすい。
- シンクシンク:アプリ操作がメイン。年齢に応じた難易度設定あり。
年齢だけで決めるのではなく、お子さんの発達段階や興味関心に合わせて検討することが大切です。
違い7.お試し方法
本格的に申し込む前に、まずは試してみたいと考えるのは自然なことです。
ワンダーボックスとシンクシンクでは、お試しの方法も異なります。
ワンダーボックスは、公式サイトから資料請求をすると、体験キット(トイ教材とワークブックの一部)と、アプリの一部機能が試せる体験版IDが送られてきます。
実際に教材に触れて、アプリの雰囲気を確認できるのがメリットです。
一方、シンクシンクは、アプリをダウンロードすれば、すぐに無料プランで利用を開始できます。
利用できる問題数などに制限はありますが、基本的なゲーム内容や操作感を気軽に試すことが可能です。
有料プランを検討する場合も、まずは無料プランで使い心地を確認するのがよいでしょう。
お試し方法のまとめです。
- ワンダーボックス:
①公式サイトから資料請求
②体験キット(トイ・ワーク)とアプリ体験版IDが届く
③実際に触れて、アプリの雰囲気を確認 - シンクシンク:
①アプリストアからアプリをダウンロード
②無料プランでアカウント登録
③すぐに一部機能を無料で体験開始
どちらも無料でお試しできるので、迷っている場合は両方試してみて、お子さんの反応を見るのが一番確実かもしれませんね。
ワンダーボックスとシンクシンクを比較したそれぞれのメリット・デメリット
ここまで7つの違いを見てきましたが、それを踏まえて、ワンダーボックスとシンクシンクそれぞれのメリットとデメリットを整理してみましょう。
これにより、どちらの教材がよりご家庭のニーズに合っているかが見えてきます。
ワンダーボックスの7つのメリット
ワンダーボックスには、STEAM教育を軸とした多くの利点があります。
幅広いSTEAM分野に触れられる
最大のメリットは、科学、技術、工学、アート、数学といった多様な分野を横断的に学べる点です。
特定の分野に偏らず、子どもの興味や得意なことを見つけるきっかけになります。
将来必要とされる複合的なスキルを自然に身につける土台作りが可能です。
アプリとキットで飽きずに続けやすい
デジタルとアナログ、両方の教材があるため、学習に変化があり飽きにくいのが特徴です。
アプリで論理的に考え、キットで手を動かして試す、といったように、異なるアプローチで学ぶことで、理解が深まり、学習意欲も持続しやすくなります。
- デジタル(アプリ):ゲーム感覚で思考力、プログラミング、アートなどを学習
- アナログ(キット):パズル、実験、工作などで五感を刺激し、試行錯誤を体験
子どもの「知りたい」「作りたい」意欲を引き出す
ワンダーボックスの教材は、子どもの知的好奇心や創造性を刺激するように工夫されています。
「なぜ?」「どうすればできる?」と考えたり、「こうしたら面白いかも!」とアイデアを形にしたりする体験を通して、学びへの主体的な意欲を引き出します。
創造性や表現力も育める
アート系のアプリやキット教材を通して、論理的な思考力だけでなく、豊かな感性や表現力も育むことができます。
決まった答えのない課題に取り組む中で、自由な発想力や自分なりに表現する力が養われます。
思考錯誤する経験を積める
特にキット教材では、うまくいかないことや失敗も経験しながら、試行錯誤するプロセスを大切にしています。
すぐに答えを求めるのではなく、粘り強く考え、挑戦する姿勢を育むことができます。
利用制限がなく、子どものペースでとことん遊べる
アプリの利用時間や回数に制限がないため、子どもが夢中になった時に、その興味を妨げることなく、とことん探求できます。
自分のペースでじっくり取り組める環境は、深い学びにつながります。
兄弟で利用するとお得
兄弟追加オプションがあり、2人目以降は割安な料金で利用できるのも嬉しいポイントです。
ひとつの契約で、アプリはそれぞれの端末で利用でき、キット教材は共有して使うことができます。ご兄弟がいる家庭にとっては経済的なメリットが大きいでしょう。
ワンダーボックスの4つのデメリット
多くのメリットがある一方、ワンダーボックスには注意しておきたい点もあります。
シンクシンクより料金が高い
最大のデメリットは、やはり料金面でしょう。
シンクシンクの有料プランと比較しても、月額料金は高めに設定されています。
教材のボリュームや内容を考えると妥当ともいえますが、家計への負担は考慮する必要があります。
- シンクシンク(有料プラン): 月額数百円~
- ワンダーボックス: 月額3,700円~(12ヶ月一括の場合)
毎月キットが届くため、収納場所が必要
アナログな学びが魅力のキット教材ですが、毎月届くため、どうしても物が増えていきます。
遊んだ後の収納場所を確保したり、定期的に整理したりする必要が出てきます。保管スペースが限られているご家庭にとっては、負担に感じるかもしれません。
一部コンテンツは親のサポートがあった方が良い場合も
特に低年齢のお子さんや、複雑なキット教材に取り組む際には、保護者の声かけやサポートが必要になる場面があります。
完全に子ども任せにするのが難しい場合もあるため、ある程度の関与が必要になる可能性があることは念頭に置いておきましょう。
効果を実感するまでに時間がかかる可能性がある
ワンダーボックスは、目先の点数アップなどではなく、長期的な視点で子どもの能力や意欲を育むことを目的としています。
そのため、シンクシンクのように短期間で明確な効果(IQ向上など)を実感しにくい側面があるかもしれません。じっくりと子どもの成長を見守る姿勢が必要です。
シンクシンクの7つのメリット
手軽さが魅力のシンクシンクにも、多くのメリットがあります。
料金が安い(無料でも始められる)
無料プランがあるため、費用をかけずに思考力トレーニングを始められるのが最大のメリットです。
有料プランもワンダーボックスと比べると非常に安価で、家計に優しい価格設定になっています。
気軽に試せるのは大きな魅力といえるでしょう。
- 無料プラン:0円
- 有料プラン:月額450円~
スマホやタブレットがあればすぐに始められる手軽さ
アプリをダウンロードするだけで、特別な準備なしにすぐに始められます。
キット教材の受け取りや管理の手間もなく、思い立ったらすぐに取り組める手軽さは、忙しい保護者にとっても魅力的です。
1日10分で無理なく習慣化しやすい
「1日10分」という明確な時間設定があるため、毎日の生活の中に組み込みやすく、学習習慣をつけやすいのが特徴です。
短時間で集中して取り組めるので、飽きっぽいお子さんでも続けやすいかもしれません。
思考力(特に算数系)を効率的に鍛えられる
空間認識、図形、論理といった、算数や数学の基礎となる思考力に特化しているため、これらの力を効率的に伸ばすことができます。
小学校の算数や、その先の学習につながる土台作りとして効果的です。
世界的な実績と効果の裏付けがある
世界150ヶ国で利用され、IQや学力向上に関する実証データがある点は、教材の信頼性につながります。
多くの専門家や教育機関からも評価されており、安心して利用できる材料といえるでしょう。
親の手間がほとんどかからない
アプリの操作は直感的で分かりやすく、子どもがひとりで進めやすいように設計されています。
キットの準備や片付け、難しい問題のサポートなども基本的に不要なため、保護者の負担が少ないのもメリットです。
場所を取らない
アプリだけで完結するため、物理的なスペースを取りません。
タブレットやスマートフォンさえあれば、どこでも学習できるのも利点です。
シンクシンクの5つのデメリット
手軽な反面、シンクシンクにもいくつか考慮すべき点があります。
学べる領域が思考力に限定される
メリットの裏返しでもありますが、学べるのが主に算数・図形系の思考力に限定されます。
プログラミングやアート、科学実験といったSTEAMの幅広い分野には触れることができません。
多様な経験をさせたい場合には物足りなさを感じる可能性があります。
- ワンダーボックス:STEAM全般
- シンクシンク:思考力(算数・図形系)に特化
1日のプレイ時間・回数に制限がある(物足りない子も)
1日10分という制限は、集中力を保つメリットがある一方、もっとやりたい、没頭したいというお子さんにとっては物足りなく感じる可能性があります。
特に知的好奇心が旺盛なタイプの子には、制限がモチベーション低下につながる懸念もゼロではありません。
アナログな体験ができない
アプリのみのため、実際に手で触れたり、作ったり、試したりするアナログな体験はできません。
五感を使った学びや、試行錯誤のプロセスを重視したい場合には、デメリットと感じるかもしれません。
創造性や表現力を伸ばす要素は少ない
シンクシンクは論理的思考力を鍛える問題が中心であり、アートやものづくりといった創造性や表現力を直接的に育むコンテンツは多くありません。
これらの力を伸ばしたい場合は、他の教材や活動で補う必要があります。
問題に慣れると単調に感じる可能性
問題の種類は豊富ですが、アプリでの学習が中心となるため、長期間続けていると、人によっては問題形式に慣れてしまい、刺激が少なく感じる可能性も考えられます。
常に新しい発見や驚きを求めるタイプのお子さんには、少し単調に思えるかもしれません。
ワンダーボックスとシンクシンクに関するよくある質問(Q&A)
ここでは、ワンダーボックスとシンクシンクに関して、保護者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q. ワンダーボックスのアプリにシンクシンクは含まれる?
A. はい、含まれています。
ワンダーボックスのアプリ内には、「シンクシンク+(プラス)」と「バベロン+」という名称で、シンクシンクでお馴染みの思考力問題が含まれています。
ワンダーボックスを受講すれば、シンクシンクの主要なコンテンツも利用できると考えてよいでしょう。
ただし、ワンダーボックス版では、シンクシンク単体アプリのような1日の利用制限はありません。
- ワンダーボックスには「シンクシンク+」「バベロン+」として思考力問題が含まれる
- ワンダーボックス版では利用制限がない
Q. シンクシンクからワンダーボックスに移行するメリットは?
A. 学びの幅が広がり、アナログ体験もできる点が大きなメリットです。
シンクシンクで思考力の基礎を養った後、さらにプログラミングやアート、科学実験などSTEAM分野全般に興味を広げたい場合、ワンダーボックスへの移行は有効なステップです。
また、アプリだけでなくキット教材で実際に手を動かす体験ができるのも、シンクシンクにはない魅力です。
利用制限がなくなるため、子どもが満足するまでとことん取り組めるようになります。
- 学習領域が思考力特化からSTEAM全般へ広がる
- キット教材によるアナログな体験が加わる
- アプリの利用制限がなくなる
Q. ワンダーボックスとシンクシンクを併用するのはあり?
A. 可能ですが、ワンダーボックスにシンクシンクの要素が含まれるため、必須ではありません。
前述の通り、ワンダーボックスにはシンクシンク系の思考力問題が含まれています。
そのため、ワンダーボックスを利用していれば、別途シンクシンク(特に有料プラン)を併用する必要性は低いといえます。
ただし、シンクシンクの「1日10分」という制限の中で集中して取り組む習慣を続けたい場合や、ワンダーボックスに含まれないシンクシンク独自のコンテンツ(もしあれば)を利用したい場合は、併用も選択肢のひとつです。
その場合、シンクシンクは無料プランで十分かもしれません。
- ワンダーボックス利用者は併用の必要性は低い
- 併用するならシンクシンクは無料プランを検討
Q. 専用タブレットは必要?推奨端末やOSは?
A. 専用タブレットは不要です。ご家庭のタブレットやスマートフォンで利用できます。
ワンダーボックス、シンクシンクともに、専用のタブレットは販売されていません。
iOSまたはAndroid搭載のタブレットやスマートフォンがあれば利用可能です。
ただし、画面が大きいタブレットの方が操作しやすく、学習効果も高まるため推奨されています。
最新の推奨OSバージョンなどは、各公式サイトで確認するようにしてください。
| 項目 | 対応デバイス | 推奨 |
|---|---|---|
| ワンダーボックス | iOS/Android タブレット・スマートフォン | タブレット |
| シンクシンク | iOS/Android タブレット・スマートフォン | タブレット |
Q. 何歳から始めるのが効果的?
A. 対象年齢は4歳からですが、お子さんの興味や発達に合わせて始めるのが一番です。
どちらの教材も4歳(年中)から利用できるように設計されています。
特に幼児期は、遊びを通して様々なことを吸収する大切な時期ですので、早めに始めるメリットはあります。
しかし、重要なのは年齢よりも、お子さん自身が「楽しい!」と感じて、主体的に取り組めるかどうかです。
焦って始める必要はありません。無料体験などを通して、お子さんが興味を示すタイミングで始めるのが最も効果的といえるでしょう。
- 公式対象年齢:4歳~10歳
- 開始時期のポイント:年齢よりも子どもの興味関心
- 迷ったら無料体験でお子さんの反応を見る
Q. 中学受験対策として役立つ?
A. 直接的な受験対策ではありませんが、土台となる思考力を養う上で役立ちます。
ワンダーボックスもシンクシンクも、特定の問題集を解くような直接的な受験対策教材ではありません。
しかし、両教材で養われる論理的思考力、空間認識能力、試行錯誤する力、問題解決能力などは、中学受験で問われる応用問題に取り組む上で非常に重要な土台となります。
特に近年の中学受験では、単なる知識だけでなく、思考力や記述力が重視される傾向にあるため、これらの教材で遊びながら考える力を伸ばしておくことは、将来的に大きなアドバンテージになる可能性があります。
- 直接的な受験問題演習ではない
- 受験に必要な思考力、問題解決能力の土台作りに貢献
- 早期から「考える楽しさ」を体験できる
まとめ
この記事では、人気の知育教材「ワンダーボックス」と「シンクシンク」について、7つの具体的な違い、それぞれのメリット・デメリット、そして選び方のポイントを詳しく解説してきました。
ワンダーボックスは、アプリとキット教材を組み合わせ、STEAM領域全般を幅広く学べるのが特徴です。
思考力だけでなく、創造力や探求心も育みたい、デジタルとアナログ両方の体験をさせたい、時間を気にせずじっくり取り組ませたいご家庭に向いています。
料金はシンクシンクより高めですが、その分、教材のボリュームと学びの幅広さが魅力です。
一方、シンクシンクは、アプリだけで完結し、思考力(特に算数・図形系)に特化して手軽に学べるのが特徴です。
費用を抑えたい、まずは気軽に思考力トレーニングを始めたい、1日10分の短時間で集中させたい、親の手間をかけずに進めさせたいご家庭に適しています。
無料プランから試せる手軽さも大きなメリットといえるでしょう。
どちらの教材にも素晴らしい点があり、最終的にどちらを選ぶかは、お子さんの個性や興味、ご家庭の教育方針、予算などによって異なります。
この記事で比較したポイントを参考に、ぜひお子さんと話し合ったり、無料体験や資料請求を活用したりして、最適な教材を見つけてください。
お子さんが「楽しい!」と感じながら、未来につながる力を育んでいける、そんな素敵な学びの機会が見つかることを願っています。